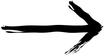※
「あんた、そこをおどきよ! 客人が斬られたんだ」
タケは家に入るなり仁八をどやしつけた。一目と酒を酌み交わしていたほろよい加減の仁八は、慌てて立ち上がる。
平二を背負ったミケーレが入って来た。後ろから円狐が平二を支えている。円狐がその手を離すと、土間へぼとぼとと血が流れ落ちた。相当な血の量だ。
「おい、これは一体全体どうしたんだ」
「説明している暇はないよ。いいから、あんたは湯を沸かしておくれ! それとそっちの大きい人…イチさんは平二さんを奥に運んでちょうだい」
言われた一目はミケーレの背から平二を受け取ると、ゆっくり家に上がり込んだ。床板の軋む音が鳴り響くのも構わず、奥へと進む。
「そっちの奥の部屋でいいから、早く!」
言われるまま、一目は平二を俯せにして床に寝かせた。
タケは平二が着ている上着を、手早く小刀で切って脱がせていく。
背中の傷が露わになった。左の脇腹から右の肩まで一直線に斬られた傷から、血が溢れ出している。
「ああ、なんて…」
タケはそれを見て、諦めと絶望の混じった声を吐いた。
「退いて。あたしがやるから」
円狐が平二の傷口へ、血を押し戻すように両手を押し当てる。
「これじゃいくらなんでも無理だよ。こんなに深いんじゃ…」
傷が浅ければ、なんとかなるかと思っていたのだろう。タケは、平二の傷口と血の量を見て、泣きそうな顔をしている。
「……ついこの間も、大怪我をしてるんだ。腹を割かれて、中身が出たって平気だったんだ。これぐらいの怪我なんて…」
円狐は後ろにいる一目に声を掛けた。
「そこにある酒を取っておくれ。まずは傷をきれいにするんだ。――タケさん、血を止めるのに、さらしがいる。手ぬぐいでもなんでもいい、持ってきておくれ」
言われたタケは、跳ねるように立ち上がった。一目が酒の徳利を円狐に手渡す。それを口に含むと、円狐は平二の背中に噴きかけた。
「こんなものしか…」と言って、タケが使い古しの黄ばんださらしや、手ぬぐいを持ってきた。円狐は仁八が持ってきた湯に手ぬぐいを通すと、それで真っ赤に血塗れた平二の背中をぬぐう。何度やっても血があふれてくるので、円狐はあきらめて、その手拭いで傷口を抑えた。
「ミケーレ、そこの襖を閉めてくれないか。あと……」
円狐は言いかけて黙った。襖を閉めると、一目たちのいる土間からは、円狐たちが見えなくなる。
「どうしまシタ?」
ミケーレが訊くと、円狐が声を落として話す。タケは桶に入った湯を替えに行ったところだ。
「……少しばかり妖力を使う。タケや仁八には見えないだろうが、万が一の場合には、お前がなだめて欲しい」
「ヨウリキというのは…?」
「宿場でお前を治したろう? それと同じことをするんだ。――妖力で血を止めて、傷口を塞ぐ」
平二の背中に押し当てた円狐の手が、薄ぼんやりと青い光を放ち始めた。ミケーレはそれを見て「オウッ」と声を上げる。そこへタケが戻ってきた。ミケーレの横に座って様子を見るが、円狐の手の光に気付いた様子はない。
流れる血の量が減ってきている。円狐は平二の背に手を押し当てたまま、一言も喋らなくなった。
沈黙に耐えられなくなったのか、タケがミケーレに話しかけた。
「ミケーレさん、さっきのお侍は相馬様でしょう?」
あの暗がりでは、長次郎がよく見えなかったはずだ。だが、見知った相手であるだけに、誰であったかは見当がつくのだろう。
「いきなり斬りかかってくるなんて、正気の沙汰じゃありませんよ。いくらミケーレさんが異人だからって、なにもあそこまでしなくてもいいじゃないですか。大体、知らない仲じゃあるまいし」
「ええ、たしかに…」
ミケーレは、なんとなくタケに話を合わせようと思った。あまりにも事情が複雑で、説明できる自信がない。それに、事情を知らせて、タケや仁八をこれ以上巻き込みたくはない。
すると襖がゆっくり開いて、仁八が顔をのぞかせた。
「おい、なんだか外が騒がしい。なんか、様子が変だ」
仁八の言葉に皆が顔を上げた。タケは、門の番人に素性を知られている。しかし、住んでいる家までは知らないはずだ。まだ役人たちが来るには早すぎる。
タケは土間に下りて、外の様子をうかがった。何人かが家の前を走る様子が聞こえるが、タケの家で立ち止まる気配はない。細く開いた戸の隙間から、役人らしき侍が、小走りに行くのが見えた。
「なんだろうね、これは――なあ、お前さん、ちょっと様子を見てきておくれよ」
仁八はぎょっとした顔を見せた。そんな危険なことを自分がさせられるとは、思ってもみなかったようだ。
「大丈夫だよ。役人たちはここを探している風じゃないし。それにあんたは顔も見られてないだろう?――このままじゃ、ミケーレさんが役人に斬られちゃうんだよ。いくら切支丹だからって、そんな酷いことあるかい」
幕府は長い間、キリスト教の布教を認めてきてはいない。ヨーロッパ諸国から政治的圧力があったために、近年は表立った弾圧こそないものの、差別的な扱いは存分に残っている。
「しかし…いくらなんでも…」
渋っている仁八を見かねたタケは、土間にいる一目に声をかけた。
「イチさん、あんたもここにいたから顔は見られてないだろう?――頼むよ。うちの旦那と一緒に行ってやっておくれよ、ね?」
それを聞いた一目は、首を縦に振ると立ち上がった。
「おお、イチさんが一緒なら怖くないな。あんたが用心棒なら俺も安心だ」
酒でまだ顔の赤い仁八は、一目の太い腕を撫でながら言った。仁八が触っても、一目は舌打ちをしない。どうやら二人で飲んでいるうちに、意気投合したようだ。
仁八は外の様子が静かになったところで、音を立てないよう戸を開ける。仁八が外に出ると、一目もそれに続いた。
円狐は平二の治療に専念するあまり、一目たちが外へ出て行ったことに気が付かなかった。ミケーレもまた、円狐の様子をじっと見守っている。肌寒い季節にも関わらず、円狐の額には汗の玉が無数に浮いている。
「円狐サン、大丈夫デスカ?」
ミケーレが訊くが返事はない。
どうやら円狐の手が青白く光る様子は、タケには見えないらしい。自分に見えてタケには見えないのはどういう訳だろうか。そもそも、円狐の言ったヨウリョクというのが、何を指すのかがわからない。ただ間違いなく、平二の傷は癒えてきている。もう傷口からは血が出てきていない。
「ミケーレ、タケから針と糸を借りてきておくれ」
ミケーレが、言われた通り針と糸を頼むと、タケは裁縫道具の入った木箱を渡してくれた。
木箱の中には、針山に縫い針が何本かと、小さく丸められた木綿糸が入っている。ミケーレはそれを円狐へ見せた。
「もう少し傷が癒えたら、それで傷口を縫っちまうから」
そう言うと円狐はまた黙った。もうずっと同じ姿勢で平二の背中に手を押し当てている。滴るほどに汗を流し、顔の血色は全くない。もともと肌が白いせいか、まるで透けてしまいそうなほどだ。
「円狐サン、もうやめたほうがいいデス。もうあなたのほうが倒れてしまいマス」
円狐は答えない。
「円狐サン、お願いですから…」
「……」
哀願するミケーレに、円狐は口を開いた。
「…あたしのせいだ。あたしがこいつをからかったから、人殺しだなんて言ったから…。碌に刀も使えないのに、殺さないよう手加減しちまったんだ」
ミケーレは思い出した。円狐は、平二と山中で斬り合いをした時のことを言っている。
「それはあなたのせいじゃナイ。――私だって、平二サンに、誰も殺してはいけないと言いまシタ。そして平二サン自身も、誰かを傷つけたくはなかったのデス」
「でもね……あたしが手は離したら、また平二の傷口が開いちまう。――この前は山ン本がいたから、すぐに直ったんだ。でも今は、あたししか平二を治せない」
「円狐サン……」
「ミケーレ、その針を火で炙っておくれ」
針山から針を抜いて立ち上がったミケーレは、それをろうそくの火にかざす。
時折、外から人の走る音が聞こえる。追われているのは自分たちだ。間違いない。ここにいるのが見つかるのも時間の問題だ。一体円狐はどうするつもりなのか。平二を治療したとしても、この大怪我では、すぐには動けまい。それに捕まってしまえば、それでおしまいではないか。自分の置かれた境遇に、大いに不安を抱きながら、ミケーレはろうそくの炎を見つめた。
タケが桶に入った湯を持ってきた。それを円狐の脇に置くと、円狐は手ぬぐいを湯につける。それで平二の背中にこびりついた血を拭っていった。傷口からはもう血が出ていない。それを見たタケは、驚きの声を上げた。
先刻まで血が溢れ出していた傷口は、薄い桃色の肉が露出していて、肩のあたりには骨まで見えている。それを認めたミケーレは、こみ上げてくる吐き気を無理に飲み込んだ。
「ミケーレ、あたしは少し休むよ。――悪いが、その間に平二の傷を縫い合わせてくれないか?」
「ええ、私がデスカ?!」
円狐は黙って頷くと、体を倒して壁にもたれかかる。すると、そのまま目をつぶって眠ってしまった。
火であぶった針を持ったまま、ミケーレはタケと顔を見合わせた。
「…あたしは無理ですよ。そんなお医者のまねごとなんて、できやしませんから」
ミケーレはそのまま立ち尽くしてしまった。聖職者が医学に明るいのは珍しいことではないが、あいにくミケーレはその方面の知識は皆無だ。
「とりあえず、もっと湯を沸かしますから」
そう言って、タケは土間の方へ行ってしまった。
円狐は、静かな寝息を立てて寝入っている。よほどヨウリョクというのを使って疲れたのだろう。
膝をついて平二の傷と相対したミケーレは、箱から木綿糸を取り出して針穴に通す。傷の長さに合わせて長めに糸を切った。
裁縫は修道院にいた頃に覚えた。自分で着る服は、すべて自分で繕わなくてはならなかったからだ。しかしまさか、日本まで来て、人の背中の肉を縫うことになろうとは思ってもみなかった。
ミケーレは、平二の背に手を触れる。血を流しすぎたせいだろうか、その体は冷たい。傷口は円狐が拭ったので綺麗ではあるが、見えている肉からは血が沁み出してきている。それを見たミケーレは、また吐き気が込み上げてきた。
「ミケーレさん、がんばってちょうだい」
タケが湯の入った桶を傍らに置いて、ミケーレを励ます。
ミケーレはえずきながらも、最初の一針を平二の背に刺し入れた。針を持った指先に、ぷつりと皮を突き抜ける感触が伝わる。その感覚だけで背中に寒気が走り、鳥肌が立ってくる。
「ミケーレさん、ほれ。これ飲んで」
アルコールのにおいが鼻をついた。ふと顔を上げると、タケが茶碗を差し出している。それを受け取ると、碗に入った酒を一気に喉へ流し込んだ。
覚悟を決めたミケーレは息を吐き出すと、針をまた一針、一針と丁寧に傷口を合わせながら縫っていく。なんとか全部縫い終えると、ミケーレは大きくため息をついた。縫っている最中は気がつかなかったが、ほとんど息をしていなかった。口の中もからからで、舌が上あごにへばりついている。
縫い終わった平二の背中には、痛々しい跡が残った。傷口が糸に締め付けられて盛り上がっている。まだ血がこびりついている平二の背中を、タケが丁寧に手ぬぐいで拭いた。
「ミケーレさん。この人、前にも背中を斬られたのかしら」
タケが拭いた平二の背中を見ていった。血の跡でわからなかったが、確かに今日斬られた傷と交差するように、長い傷跡が残っている。もう塞がっているが、明らかに刀で斬られたものだ。
芭尾に割かれた腹の傷、長次郎に斬られた傷、そしてもうひとつの背中の傷。これほどまで傷ついても、それでも平二はまだ生きている。この男の生き様は、如何に過酷なのであろうか。
「上手にできたじゃないか」
いつの間にか目を覚ましていた円狐が、壁に持たれたままミケーレの方を見ていた。円狐は、袂から布袋を取り出すと、まだ血で汚れている手で中身を探った。指で摘んだ木の実を口の中へ放り込むと、小気味良い音を立てて食べ始める。
ひどく疲れた表情の円狐は、ゆっくりと体を起こすと、平二の背中の縫い跡に指を滑らせた。
「これで後は、平二が眼を覚ますのを待つだけだ」
「本当に、これで大丈夫なんデスカ?」
「さあね。あたしたちができることは全部やった。後は平二次第だよ。平二には山ン本の――天狗の眼があるから」
タケは、円狐の言うことを聞いてもさっぱりわからないという顔をして、ミケーレの方を向いた。ミケーレに説明を求めているのだろう。ミケーレは両肩を押し上げて、自分もわからないという素振りを見せる。ここまで世話になっているのだから、事情を素直に話したいところだが、当のミケーレもよく理解はしていないから、説明のしようもない。
円狐の言うのは、平二の光る右眼のことだろう。平二は腹を割かれて死にかけても、その眼のお陰で生き延びたと言っていた。にわかに信じがたいことだが、確かに平二はこれだけ傷つきながらも、いまなお生きている。
「これは――もう使えないね。洗ったら使えるのもあるだろうけど」
そう言って、タケは真っ赤になった手ぬぐいを集めると、桶に入れて立ち上がった。タケはそのまま部屋を出ていく。
「ねぇミケーレ、タケもあれかい、切支丹なのかい?」
タケが土間で片付けを始める音が聞こえると、円狐がミケーレに話しかけた。その声は疲れが抜けないのか、まだ少し息が荒い。
「ええ、私がここに来る前からデス。教会の手伝いをしているうちに、ご夫婦で改宗したんだそうデス」
「そう、それでかい」
「なにがデスカ?」
「いきなり押しかけてきたあたしらを、簡単に家に入れてしまうし、平二の介抱まで手伝ってさ、役人に見つかったら、ただじゃすまないのにね。――『人』はさ、他の奴のことなんてお構いなしじゃないか。誰が死のうが、知らない奴なら気にも留めない」
「この国で、イエス・キリストを信じるものたちは、長い間、非道い扱いを受けてきまシタ。それは今でも続いていマス。だから、余計にキリシタン同士の結束が強いのデス」
「まったく、大したお人好しだよ」
「それは、あなたも同じデス」
「…どういう意味さ?」
円狐の口調が低くなった。疲れた表情ながらもミケーレを睨む。
「あなたは…平二サンが嫌いだと言っていたのに、平二サンの命を助けようとしてイル。とても必死にデス」
「違う。あたしがこいつをからかったせいで、こいつが『人』を斬らなくなった。そのせいでこんなになったんだ。ただの帳尻あわせだよ。この阿呆に借りを作りたくないだけだ」
タケを気にして声を荒げないが、その口調には明らかに怒りを含んでいる。しかしミケーレは、それに臆する様子はない。
「償いのためだけに、そこまで必死になれるとは思えまセン」
「……何が言いたいんだい?」
「見返りを求めない献身的な愛は、国が変わっても同じデス。あなたがしたことは…」
「やめな、くだらない!」
円狐は寄りかかっていた体を起こすと、ミケーレに顔を寄せた。近づいた円狐の顔が、目の前でどんどん変わっていく。ミケーレはその光景に思わず息をのんだ。円狐の輪郭がぼやけていくと、鼻と口が前にせり出していく。黒かった髪の毛は、深く黄みがかった金色になり、それが顔から首へそして全身へと拡がっていく。
狐の姿になった円狐は、鋭い眼付きでミケーレを見据えた。
円狐の本当の姿を前にしたミケーレは、そうっと自分の懐に手を入れた。そこに入っている木枝の十字架に触れるためだ。
「あたしは見ての通り物怪だ。『人』の姿しか知らなくて、嘗めてたんだろう?…」
そう言うと、円狐は手を持ち上げた。人の姿であったときの真白な細い指とは違う、毛むくじゃらで短い獣の指だ。その指に生えた、鋭い爪をミケーレの喉元へ向ける。
「…いいかい、瞳術が効かなくても、お前をどうにかすることはできるんだ。――わかったら、そのくだらない説教はやめな」
「…そ、それでも、あなたは愛する心を持ってイマス。あ、愛することは、自分を犠牲にすることデス。あなたは今、まさに自分を犠牲にしたじゃないデスカ!」
円狐の爪が、ミケーレの首に食い込んだ。首の皮膚が破れるぎりぎりのところで止まっている。
「あなたは私を殺しまセン、あ、あなたは嫌いなはずの『人』を助けたじゃないデスカ。――あなたは、私を殺しまセン!」
歯をむき出した円狐が、ミケーレを睨み付ける。その形相に怖じ気づいて、ミケーレは眼を閉じた。歯の根が震えて、がちがちと音を鳴らす。
ミケーレには、どうしても円狐が悪いものには思えなかった。自分が人外のものだと言う円狐は、己の身を削るようにして、平二を救ったのだ。
彼らは互いを思いやる方法を知らない、その気持ちを表現する方法を知らないだけだ。それを知れば、復讐などという忌まわしい呪縛から解き放てるのかもしれない。
目をつむっていたミケーレの首から、食い込んでいた爪の感触が消えた。円狐が手を下ろしたのだ。ミケーレは恐る恐る眼を開けると、そこには人の姿をした円狐が座っていた。
「こいつは…自分が許せないんだ。芭尾に女房を殺されたことを、自分のせいみたいに思っている」
円狐は、平二の傷に指を沿わせた。
「――それが、なんだか不憫に思えたんだ」
円狐と平二は反目しながらも、お互いの境遇に共感していたのかもしれない。彼らは思った以上に純粋で情け深い。それだけに芭尾に対しての怒りも大きいのだ。
芭尾さえいなければ、彼らは今でも平穏な暮らしを送っていられたのだろう。血だらけになりながら、こんなところまで芭尾を追ってくる必要もなかった。不憫なのは平二だけではない。
ミケーレが円狐に声をかけようとした時、家の扉が勢い良く開く音が聞こえた。それに驚いたタケの悲鳴が聞こえてくる。
ミケーレはふすまを開いた。すると、ぜいぜいと激しく息をする仁八が扉を開いて立っている。
転がるように床に膝をついた仁八は、堰を切ったように叫んだ。
「た、大変だ、火事だ! あちこちから、火が上がってるんだ!」
それを聞いたタケは、すぐさま箪笥の引き出しを開けて、中の物を手際よく取り出し始める。
「できるだけのものを持って出るんだよ!――ミケーレさん、直ぐに逃げる用意をして下さいな! 平二さんを連れて早く!」
街は、木と紙でできた家屋が密集している。ひとたび火災が起これば、あっという間に燃え広がってしまう。延焼を防ぐには、火事の起こった周辺の家屋を崩して、火災現場を隔離するしかない。火事に近ければ、燃えていなくても家が壊されてしまうこともある。とにかく、金目の物は全部持ち出して逃げるのが最善の策だ。
急に慌ただしくなった様子に、ミケーレはどうしていいのかわからない。呆然としているミケーレに円狐が言った。
「ミケーレは平二の持ち物をまとめておくれ!――おい、仁八とやら、一目はどうしたんだい!」
「イチモクって…ええと、イチさんなら、ほら」
仁八は、扉の外を指差した。そこには大きな影が見えている。
「一目、平二を抱えておくれ!」
言われた一目は、のっそりと家の中に入る。そのまま下履きも脱がずに上がり込んだ一目を、仁八もタケも咎めようとしない。当の仁八も、草履をつけたままで家中を走り回っている。ミケーレは、平二の刀二本を破れた服でまとめると、それを抱えた。
逃げる支度に追われている仁八とタケに、円狐が声を掛けた。
「仁八、タケ、ちょっといいかい?」
「どうしたの、こんな時に⁉」
「あんたたちには、世話になった。――それに、巻き込んじまって、すまなかった」
「そんなこと言ってる場合じゃない。みんな一緒に逃げるんだよ」
「いや、あたしたちはもう行くよ。行かなきゃ。――もし万が一、役人に咎めを受けるような事になったら、賊に脅されたって言うんだ。ミケーレも、賊に攫われた事にしておくれ」
「お前さんたち、一体…?」
円狐は黙ったまま首を横に振った。聞いてくれるなという意味だ。それを察したタケは、言いかけた言葉を飲み込んだ。
「ごめんよ、あんたたちは何も知らない方がいい」
円狐はそう呟いて踵を返すと、外へ出ていった。一目も平二を背に乗せて後に続く。
「仁八サン、タケサン……」
ミケーレは眼に涙を溜めている。
「あらミケーレさん。なんで泣いてるの?」
「あなた方には本当に感謝していマス。――どうか、神のご加護がありますヨウニ」
ミケーレはそう言って胸の前で十字を切った。
「ミケーレさんにも、神様のご加護がありますように」
タケと仁八は、いつものように満面の笑みを見せた。思ったような宣教活動も出来ず、毎日を鬱々と過ごしていた。そうした日々においても希望があったのは、この夫婦の、この笑顔があったからだ。
ミケーレは二人に向けて深く頭を下げた。日本人が感謝の意を示すときは、そうするのだと聞いていた。だが実際にやってみたのは今日が初めてだ。
もう二人には会えないかも知れない。そう思うと涙が出てくる。
袖で顔を拭ったミケーレは、円狐たちが待つ扉の外へと出て行った。