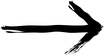※
日本人街は、居留地の西側に広がっている。小高い丘の上や港近くは、外国人の邸宅や各国代表団の建物が並んでいるのに対して、日本人の住処は、ぬかるんだ湿地を埋め立てたばかりのところがほとんどだ。立っている家は木造のあばら屋ばかりで、外国人が住む西洋風の豪奢な邸宅とは、雲泥の差がある。
平二たちは、そのあばら屋が所狭しと隣接している街中を、ミケーレの案内で歩いて行く。人通りはまばらだが、皆一様に平二たちに眼を向ける。異人が一人、太刀を差した片目の男が一人、尋常でない大男と、あとは女。目立つのは当然だ。
タケの家には、雇っている都合もあって何度か脚を運んでいた。居留地にいる外国人は、横浜から東海道の一部を含む、かなり広い範囲を許可なく訪れることができる。だが幕府はミケーレのような宣教師に同じ権利を与えなかった。タケの家を訪れるにも、常に相馬長次郎のような役人がお供について来た。
「確か、この辺りだと思いマス」
ミケーレは誰に言うでもなく言葉を漏らした。いつもは道案内がいるので、あまりよく道を覚えていない。それに日が落ちかけた今は、街の様相がすっかり違って見える。
「思うって、間違えないでくれよ。この面子で家を間違えたら、下手すりゃ人を呼ばれるぞ」
全くおかしな取り合わせの一行は、慎重に辺りの家を見渡す。
ここに住む日本人にとって、異人はもう珍しいものではなくなっていた。居留地ができた頃には、往来する異人をはやし立てたり、物珍しそうにつけ回す輩も多かったが、今はもう慣れたもので、道端ですれ違っても気にする者はいない。異人の夜間外出は、遊郭街を除いて厳しく制限されてはいるが、余程のいざこざでもない限り問題にはならなくなった。これも徐々に、異人、日本人ともに環境に順応していった結果だろう。
ミケーレは、並んでいる家の一つに近づいて扉を叩いた。
「タケサン、すいまセン? タケサン…」
何度か扉越しに囁くと、そろそろと引き戸が開いて、中から恰幅のいい中年の女性が顔を出した。
「あれまあ、やっぱりミケーレさんだ。声を聞いて、すぐにわかりましたよう。旅先で病気になったって聞きましたよ。みんな心配していたんだから」
女性は早口でまくし立てると、返事も聞かずに、家の中へ振り向いて、声を上げた。
「お前さん、ミケーレさんだよ。ミケーレさんが帰ってきたよ」
家の奥から、「おおっ」と歓声が上がると、更に戸が開いて、小柄な男性が顔を出した。
「ああ、タケサン、仁八サン、こんな夜にすいません。実は…」
言いかけたミケーレの言葉を皆まで聞かず、タケは引き戸を開くと、中に入れと言って家に招き入れようとする。
「ちょっと待ってくだサイ。タケサン、ちょっと待ッテ。――平二サン、ちょっとこっちへ来てくだサイ」
ミケーレは慌てて平二の名を呼んだ。近づいてきた平二を見た二人の顔が曇る。野良着の上から毛皮の胴服を羽織り、片目を隠して刀を腰に差した男が現れたのだ。訝しがるのも無理はない。
「あれ…、ミケーレさんの知り合いなの?」
タケが怪訝そうにミケーレに話しかける。
「ええ、あの人が私を助けてくれた平二サンデス。それと、向こうにいるのが…」
「女の方が〝エン〟。あっちの大きいのが〝イチ〟だ」
平二が口を開いた。ミケーレに任せていたのでは、いつまで経っても、早口のタケを黙らせることができない。
平二が咄嗟に言った名前が気に入らなかったのか、円狐は露骨に顔をしかめている。
タケは、平二を見定めるように眺め回すが、一目の姿に眼を止めて、驚嘆の声を上げた。仁八も、呆然とその巨体を見上げている。
「随分と変わったお名前だね…」
「甲斐の田舎から来たんだ。あっちじゃ珍しい名前じゃない」
「甲斐から…ねぇ」
「ミケーレを助けた縁でね、ここまで俺たちで送って来たんだ」
ミケーレは、平二の言葉にうんうんと頷いて見せる。
「皆さん、見た目は怪しいですが、良い人たちデス」
円狐がまた顔をしかめた。ミケーレに、怪しい見た目だと言われたことか、『人』と紹介されたことが気にいらないのか。
相変わらず訝しい表情のタケと仁八に、ミケーレが言った。
「この人たちにイエスのことを話しまシタ。彼らは、洗礼を受けるためにここまできたんデスヨ」
一瞬顔を見合わせたタケと仁八は、すぐに笑顔を見せた。
「そう、ミケーレさんがそう言うなら。でも、その腰の物騒なものは下ろしておくれよ」
そう言ってタケは平二たちも家の中へ招き入れる。
家の中は、狭い土間に六畳の部屋が二つ、部屋は襖が開け放たれて、奥の様子が見える。住んでいるのは、タケと仁八だけらしい。
平二と円狐に続いて、大きく腰と首を曲げて一目が入ってくると、タケはうわあと驚きの声を上げた。家の中に入ると、比較する物があるせいで、その大きさがよりはっきりと分かる。
「あんた、すごく大きいねえ。異人さんたちも大きい人はたくさんいるけど、あんたほど大きい人はいないよ」
一目が足を上げて家に上がりこもうとすると、床が軋んで悲鳴を上げた。咄嗟に足を引いた一目は、そのまま土間に座り込む。
「ああ、大きすぎて床が抜けちまうね。ちゃんと掃除はしてるからさ、そこで我慢しておくれよ」
言われた一目は、心なしか、いつもより小さい音で舌打ちをした。
タケがミケーレを床に座らせると、平二と円狐も並んで座る。すると平二は、ミケーレに小声で話しかけた
「さっきの〝せんれい〟ってなんだ?」
「あなたたちが、キリシタンになるためにここに来たと言ったんデス。タケサンも、仁八も、実はキリシタンなんデスヨ」
ぎょっとした顔でミケーレを見る平二をよそに、タケはミケーレの目の前に座った。
「いやはや難儀でした。まさか旅先で倒れるなんてねぇ」
「それを助けてくれたのが平二サンたちデス。薬をくれて、私をここまで送ってくれまシタ」
「そうだったんだね。――ミケーレさんを助けてくれて有難う」
タケは平二に向かって敬々しく礼を言う。ばつが悪い平二は小さく頷くと俯いてしまった。
「タケサンでないと、頼めないことですカラ…。それで、着いてすぐに、タケサンのところに来まシタ」
「まさかミケーレさんが、あたしを頼って来てくれるなんて。嬉しいですよ。――それで、この人たちも教会まで行くんですね?」
「ええ、居留地の教会の話をしたら、是非そこで洗礼を受けたいというのデス。でも教会に行くには、タケサンと一緒に掃除の仕事で行かないといけまセン」
「わかりました。――あんたたちもイエス様に会いたいんだね? 素敵な教会だよ。教会にはイエス様がいるんだから、楽しみにしておいでなさい」
平二は無言で頷いた。正直、異国の神様のことはよくわからない。
「それで、実は…」
ミケーレは言いにくそうに一旦言葉を濁したが、すぐに意を決して言葉を続けた。
「出来るだけ早くに教会へ行きたいのデス。お願いできマスカ?」
「次の掃除の日は明後日だけど、あたしも気になることがあるからね。いいですよ。明日の朝一番で行きましょう。あんたたちは、今日はここで泊っていくといいよ」
タケは勢いよく言うと仁八が口を挟んだ。
「お前、こんな狭い家で六人も寝れるかい。それにあそこのお人なんて、土間で座ってるじゃないか」
「あいつはあそこで平気。寝るのもあそこでいい。明日の朝まで辛抱しておくれよ」
円狐が言うと、口を尖らせていた仁八は、鼻の下を伸ばしてうんうんと頷いた。それをタケが呆れ顔で眺めている。
「全く、美人が言うことは素直に聞くんだから。――ミケーレさんも、狭いところですけど、我慢して下さいね」
「ハイ」と答えてミケーレは微笑んだ。
仁八は小間使いとして、タケは賄いとして、ミケーレのいる教会で夫婦揃って働いている。ミケーレが知る大半の日本語は、この二人から教わったものだ。特にタケは持ち前の明るさで、陰鬱とした生活を送るミケーレを元気づけた。しばしば喋りだすと止まらなくなるきらいはあるが、ミケーレにとっては、ありがたい存在である。
「ところでタケサン、気になることと言うのは何デスカ?」
「いえね、今日教会にお給仕に行ったんだけれでも、ロベールさんがいなかったんですよ。夕食の時間になっても戻らないから、心配してたんです。あの方、お酒好きでしょう? だからまた、誰かのお宅でワインでも頂いてるんじゃないかしら」
タケの話す内容に、ミケーレは不安げな表情を見せる。街に血の匂いが立ち込めていると円狐が言っていた。きっと、芭尾が人を殺して喰ったのだと言っていた。そんな時に、ロベール・デュボワ神父の行方が知れないとは。デュボワは、出かけるときに必ず行き先を言ってから出かける。何かあったに違いない。
青い顔で黙ってしまったミケーレに、平二が声を掛けた。
「ミケーレ、どうした?」
「……え、あの、私の知り合いの行方がわからなくなっているらしいんデス」
「まさかな…、なんか勘違いじゃないのか?」
「だと、いいのデスガ」
尋常でない様子のミケーレを、タケも心配そうに見ている。
「心配なら今から行くか?」
平二が訊いた。
もうすっかり日が暮れた。この時間になると、日本人街と居留地との往来は厳しく制限される。遊郭街からは比較的簡単に入れると聞いたことはあるが、神父であるミケーレは遊郭を知らない。そもそも、その門を通れるのは遊郭で遊ぶ異人だけで、日本人は門に近づくこともできない。
「この時間だと、平二サンたちは一緒には入れまセン。私ひとりでなら、なんとか……」
重い声を吐き出したミケーレに、タケが言った。
「ミケーレさん、岩亀楼のとこにある門から入る気でしょう? あそこは遊びをした人たちが通るところじゃないですか。神父のミケーレさんが行ったら、後で非道い噂をされますよ。――あそこまで行かなくても、別の門からだっていくらか掴ませれば通れますって」
「…?」
ミケーレは怪訝そうな顔を見せた。タケの言っている意味が分からないらしい。
「岩亀楼で遊びすぎた異人さんで、遊郭の門から帰ると都合の悪いお方は、こっちの方の門番に頼んで通してもらうんです。――奥方連れでいる方も多いですからねぇ」
居留地の出入りは厳格に管理されていると思っていたが、それほどいい加減だったのだろうか。まさか、そのような手立てがあるとは思ってもみなかった。
「そんな簡単に入れるんデスカ?」
「そりゃ少しはお金がいりますよ」
「いくらで通れるんだい?」
円狐が身を乗り出して言った。入れるならば、早いに越したことはないだろう。
「さあ、異人さんたちは、百文ぐらいは渡してるんじゃないかね」
「あたしたちは?」
「いいや、日本人はだめよ。なんで居留地の出入りが厳しいか知ってるかい? 昔、異人さんが沢山斬られたんだよ。居留地が壁で囲われているのはね、異人が嫌いだって言う日本人を入れないため。だから門番は、異人さんが通る分には大目に見てくれるけど、日本人は絶対に入れてくれないのよ」
タケの話を聞いた円狐は、ふんっと鼻を鳴らした。『人』同士がいがみ合おうが構わない。しかしお互いを壁で囲って分けているおかげで、芭尾にあと一手のところで届かない。
「私は行きマス。デュボワ神父が心配デス」
「俺たちはどうするんだ? お前なしで居留地には…」
言いかけた平二をタケが遮った。
「あんたたちは、ちゃん明日の朝になったら教会へ連れて行ってあげますから。――それにしたって、そんなに焦らなくてもいいじゃないですか。確かに、ロベールさんは心配ですけどねぇ」
事情を知らないタケには、ミケーレたちの焦り様が不可解なのも仕方がない。
早速立ち上がったミケーレに、円狐が声を掛けた。
「ミケーレ、お前、いくらか持っているのかい?」
「…?」
「お金だよ、門番に渡す袖の下が必要だろ」
「…いえ、持ってはいまセン」
円狐は「それなら」と行って立ち上がると、土間に降りて履物に足を通す。
「あたしが一緒に行って出してやるよ。別に通れなくても、門まで行くのは構わないだろう?」
「それじゃ、俺も行く」
そう言って平二も立ち上がる。
「〝イチ〟は目立つから、ここで待っておいで」
円狐は土間に座った一目に言った。
タケが、家を出て行こうとする平二たちに声を掛ける。
「ちょっとお待ちよ。あんたたち、門がどこにあるのか知ってるのかい?――ミケーレさんだって、こちら側の事は殆ど知らないじゃないですか。仕様がないから、あたしも行きますよう」
「そしたら、俺はこっちの大きいお方と留守番だな。――なあ、あんた、少しは飲みなさるだろう?」
仁八はそう言って、徳利片手に一目の方へ這い寄っていく。一目もまんざらでないのか、分厚い唇の端を持ち上げた。