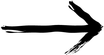六、暗転
火の手はまだ遠く離れた所にある。半鐘の音で眼を覚ました人々が、続々と通りに出てきている。道を行く人々中には、既に持てるだけの家財道具を抱えて逃げていく者たちもいる。
円狐は、人々が逃げていく方向とは反対に歩き出した。一目も黙って、それについて行く。
「円狐サン、そっちは駄目デス。そっちは火事が…」
「いいんだ。今は芭尾と出くわしたくない」
「え、どうして…」
「この火事は、あたしらを燻り出すためだ。火と反対の方へ逃げれば、きっと芭尾に待ち伏せされる」
徐々に慌ただしくなっていく人ごみを、すり抜けるようにして歩く円狐の足取りは、心なしか重い。やはりまだ疲れているのだろう。ミケーレは円狐に遅れをとらないよう、小走りに後を追って行く。
円狐の力を目の当たりにしたミケーレは、複雑な感情を抱いていた。骨が露出するほどの深い傷を、医療器具や薬もなしに止血したのだ。目の前で起こったことは、奇跡としか言い様がない。聖書の記述にあるような奇跡を目の当たりにしたばかりなのに、どうにも釈然としない。
円狐が聖職者、少なくともキリスト教信徒であれば、わだかまりなく受容できるのだろう。しかし、彼女はイエス・キリストの名も聞いたことがない、獣の姿をした人外の化け物だ。
円狐が見せた本当の姿は、ミケーレにとって衝撃的ではあったものの、さほどの恐れはなかった。むしろこの状況にあっては、それに縋るような思いさえある。無論、信仰心とは別だ。神への崇拝はミケーレにとって無類のものだ。だからこそ、目の前を歩く不可解な存在に対して信頼を寄せている自分自身が、どうにも解せない。
「タケの言っていた岩亀楼の門って、お前は知っているのかい?」
円狐がミケーレに訊いた。
「いえ、私はそちらの方には足を踏み入れたことがないのデス。どの方向かぐらいしか…」
「それで十分だ。芭尾の手下やらに見つかる前に、居留地に入ってしまおう。それで様子を伺ったほうがいい」
円狐はミケーレが指差した方向へ向きを変えると、また小走りに歩きだした。逃げる人々の数はどんどん増えていき、あちらこちらから怒号が聞こえてくる。
どうも様子がおかしい。円狐は立ち止まって、あたりを見回した。火の手を避けて逃げていく人々と、また別の方向へ逃げる人々がいる。互いに出会い頭で道を塞ぎ合って、言い争いが起こっているのだ。
「円狐サン、どうしたんデスカ? 急ぎまショウ」
「なんだか、逃げる方向が、皆ばらばらじゃないか?」
円狐たちと同じように、火の手の上がっているはずの方角へ逃げようとする者たちもいる。ミケーレは自分たちが来た方向、タケの家の方を見た。暗いはずの空が、うっすらと赤く染まっている。
「円狐サン…あっちにも火が…」
回りをよく見ると、四方あちこちから火が上がっている。火事が起こったのは一箇所ではなかった。芭尾は街のいたるところに火を放ったのだろう。円狐たちは、他の住民たちとともに、街の中に取り残されてしまった。
「むちゃくちゃだ。――あたしたちと一緒に街全部を燃やす気だ」
如何に物怪とはいえ、火に焼かれれば死なないことはない。それにしても、街ごと焼き殺そうとするとは思ってもみなかった。あの門のところで、芭尾の手下となった役人と鉢合わせたせいだ。もっと慎重に事を進めるべきだった。
逃げ場を失った街の住人は、大混乱に陥っていた。どの方向へ行っても火の手が迫っている。火勢はどんどん広がって、夜の暗い空を赤く照らしている。まだ直接火が見えないものの、肌で感じるその温度が恐怖を駆り立てる。ぶつかり合って、進むべき方を見失った人々は、悲痛な叫び声を上げながらお互いを罵り合った。
すると、一人の男が叫んだ。
「居留地の方はまだ燃えてねえ! 門だ。大通りの門へ行け!」
居留地と日本人街の間には、二つの地区を分けるように運河が流れている。確かに居留地の方には、まだ火の手がない。男の声に、皆そうだそうだと言って、一斉に同じ方角へ走りだした。
押し合い圧し合いするものだから、あちこちから悲鳴と怒号が聞こえてくる。その勢いに、あっけにとられていた円狐たちは、いつの間にか道の端へ追いやられてしまった。
人々は居留地へ入る門へと向かって行く。円狐たちが、タケの案内で詰めかけた門だ。
徐々に逃げる人の数が減ってくる。呆然と立ち尽くしていた円狐は、なにやら嫌気を催す気配を感じた。思わず一目の方を見る。同じように感じたか、円狐と眼が合うと、一目は大きく頷いた。
ミケーレが絞り出すように声を発した。
「円狐サン、あそこに……います」
ミケーレが指差した先、逃げ惑う人々の隙間に、阿鼻叫喚の火事場には似つかわしくない西洋の外套をまとった女と、見覚えのある役人が立っている。女の着ているキャメル色の外套は、遠目にもその艶がわかるほどの上等なビロードでできている。そして傍らに立つ役人は長次郎だ。上半身裸で腹には晒しを巻いているが、その脇腹の辺りは黒く濡れている。暗くても濡れているとわかるのは、そこから血が滴っているからだ。
外套を来た女は、人の波の向こうからじっとミケーレたちを見つめている、その眼は冷たく、妖しく、威圧的で不気味だ。逃げまとう人々を挟んで、互いにしばらく動かない。
人々の喧騒が遠くなり始めた頃、円狐が口を開いた。
「お前、芭尾だね」
外套を着た女は、そうっと首を傾げて笑った。その笑みは、ミケーレたちを見下すかの如く、気安ささえ漂っている。まるで旧知の縁者にばったり出会ったかのようだ。
「え、円狐サン、この人デス」
ミケーレの言葉に芭尾が応えた。
「ミケーレ・ラブティ、まさか戻って来られるとは思わなかった。――その物怪たちと一緒ということは、私のことも、とうに知っているのだろう?」
鉢合わせたのか、待ち伏せされたか、いずれにしても、円狐たちにとって分が悪い。傷を塞いだとはいえ、まだ平二の意識は戻らないし、円狐の妖力も万全ではないのだ。
「そっちは私と同じ妖狐で、大きい方は一つ目か。――はるばる横浜までようこそ。わたしが芭尾だ」
芭尾は、一目のほうを指差した。
「長次郎。あれが、お前が斬った男か?」
「背負われているのが、そうだ」
芭尾からは、一目に背負われた平二の頭しか見えていない。
「おい狐のほう――お前の名は?」
「黙れ。卑しい人食いめ!」
「……」
罵る円狐の言葉にも、芭尾は眉一つ動かさない。先ほどから笑ったままの顔は、面が張り付いたように表情が変わらない。
「その口ぶりだと、お前『人』を喰ったことないだろ?――こんな餓鬼なんか寄越して、太秦坊も焼きが回ったか…」
「山ン本を馬鹿にするんじゃないよ!」
いつの間にか右手に握っていた黙儒の突先を、円狐は芭尾に向けた。すると長次郎が、芭尾を庇うように前に出た。その手は既に、刀の柄に触れている。
「ふうん、なにやらおかしな剣だ。そんなものを持ち出してくるなんて、太秦坊も必死だねぇ」
円狐の持った黙儒が、音を立てて火花を散らす。
「それでも貴様らは私を殺せない。私を追い詰めたと思ったか? 実のところ、追い詰められたのは貴様らだ。こっちの日本人街には、どこへも逃げ場がない。――焼け死ぬか、私に殺されるか、選べ」
芭尾の表情は相変わらず笑ったままだ。火の手が迫ってきたか、辺りが明るくなっていく。
「こっちには逃げ場がないって、どういう意味だ?」
「私の手下が通れないよう、あちこち道を塞いだのさ。当然、居留地にも入れない」
「この…っ!」
円狐は強く唇をかんだ。口惜しさで体に震えが起こる。ここまで追い詰めていたはずだった。なのに、圧倒的に不利な状態で追い込まれている。円狐が思っていた以上に、芭尾は狡猾だった。追っ手が来ることを見越して、手ぐすね引いて待ち構えていたのだ。
ならばもっと、早く追うべきだったか。否、芭尾は追っ手を煙に巻くために、わざわざ自分の皮を『人』のものと取り替えまでしたのだ。芭尾の今の顔を知る平二は必要だった。しかし、その平二が斬られたおかげで窮地に陥っている。結局全て、『人』に関わったせいでこうなった。
苦々しい顔で睨む円狐と対照的に、芭尾は口端を歪ませると、けらけらと笑い始めた。
「…何が可笑しい?」
円狐は低くつぶやくように言った。芭尾の笑い声は止まらない。
「何が可笑しい? お前のおかげで、どれだけあたしが苦労したと思う? 同じ妖狐というだけで!お前が、お前がやりたい放題したせいだ。――笑うなっ! あたしの前で、お前は笑うなっ!」
円狐は怒りにまかせて言葉を叩きつけた。それでも芭尾の表情は変わりない。
「ふふっ、だからなんだ? 私が謝ったら満足か?」
「黙れっ!」
激高した円狐が地面を蹴った。だが前に出た長次郎が、円狐の行く手を阻む。長次郎が抜いた刀が円狐の胸元を切り裂いた。しかし着物は切れたものの、肌には傷一つない。円狐が前に出ようとすると、長次郎が身をひねって体を当ててくる。
一目が長次郎に迫った。平二を背負っていると思えない速さで大きな一歩を踏み出すと、臼のように太い臑で長次郎を蹴り飛ばす。後ろへ押し飛ばされた長次郎の体が、背にした家の戸を突き破った。
その間に芭尾は、円狐の黙儒が届かないところに退いていた。傍らには、役人らしき男が数人付いている。いつの間にか円狐たちは、大勢の役人に囲まれていた。
「太秦坊の言いつけなど聞かず、お前も『人』を喰えばいい。そうすれば私を殺せるかもしれない。そこのでかいのが、ちょうど一人背負っているじゃないか。それともそっちの異人にするか?」
芭尾はそう言って、ミケーレに眼を向けた。
徐々に近づく火勢は、すぐそこまで迫ってきている。刀を抜いた役人は、じりじりと距離を詰めてくる。じっと芭尾を見据えたままの円狐は、大きく息を吐き出した。
「……逃げるよ」
小さくつぶやいた円狐の声に、一目とミケーレが振り向いた。芭尾にもその言葉が聞こえたか、その表情から笑いが消える。
太い腕でミケーレを抱え上げた一目は、勢いよく駆け出した。同時に、円狐も同じ方へ走り出す。
「急ぐよ!」
「ど、どこへ、逃げるんデスカ? 火事で逃げる場所なん…」
一目の腕の中で揺られているミケーレは、舌を噛みそうになって口を閉じた。大きい分、走る時の振動もすごい。
「門を開けるんだ。早くしないと、タケたちが焼け死んじまう」
芭尾に遭遇した驚きで全く気がつかなかった。仁八とタケ、そして逃げていった人々もまた、行き場を失っているはずだ。
円狐は走りながら、何度か後ろを振り返った。芭尾に操られている役人たちが追ってくるものの、芭尾は動こうともしない。
芭尾を前にして逃げるのは、歯噛みするほどの思いだ。しかしこの数日間、追っ手を待ち受けて準備をしてきた芭尾相手に、今のままではまず敵わない。今は逃げても、火事後の混乱に乗じて芭尾に近づく機会は必ずあるはずだ。
来た道を引き返すように走る一目と円狐は、随所で焼け落ちた家の上を飛び越えて行く。芭尾ならともかく、炎をかいくぐるような芸当は『人』である役人にはできない。
燃えさかる炎を何度か飛び越えた時、一目が唸った。
目の前に芭尾がいる。まさに一目が降り立とうとする場所に突然現れた芭尾は、着ていた外套の前合わせを両手で開いた。その外套の内側には、びっしりと黒い何かが蠢いている。芭尾の妖力の塊、巫蟲だ。外套の中で激しくのたうち回っていたそれは、落ちてくる一目に向かって一斉に飛びかかった。たまらず一目は、平二とミケーレを放り投げると、襲いかかる巫蟲の群れに包まれていく。
「一目っ!」
円狐は駆け寄ると同時に、真っ黒い塊になった一目の上半身に向けて黙儒を振るった。一目の体をかすめる黙儒が、体にまとわりついた巫蟲をはじき飛ばす。一目の大きな手が真っ黒い巫蟲をちぎり取るように投げ捨てていくものの、一向にその数は減らず、どんどん一目の体の中に入り込んでいく。
投げ飛ばされたミケーレは、一目の吼えるような雄叫びに慌てて振り返った。その悲痛な声は、鼓膜を破かんばかりに響き渡る。
ミケーレの眼にも巫蟲が見えている。だがそれが、自分の体内にもいたことは知る由もない。
反射的に立ち上がったミケーレは、胸元にしまい込んだ木枝の十字架を握りしめた。
ロザリオを失ったミケーレにとって、唯一自分がキリスト者だと自覚する証だ。たとえ急ごしらえであっても、この十字架が心の拠り所だった。今の自分にはこれしかない。いや、平二や円狐たちのような特別な力はないが、自分にはこれがある。
ミケーレは十字架を取り出すと、一目へと走る。
「ミケーレ、駄目だ!」
叫ぶ円狐を尻目に、ミケーレはうずくまる一目の背に手を当てた。触れた手は蠢く黒い巫蟲の群れに埋まっていく。それが腕に絡みつくようにのたくると、ミケーレは背筋に鋭い寒気を覚えた。手を引きたいのを必死に堪えると、ミケーレは一気に手を突っ込んでいく。腕が肘までめり込むと、手の先が、堅い一目の背に触れた。
「私には、芭尾の力が効かないはずデス!」
ミケーレは十字架を胸前にかざすと、イタリア語で祈りを唱える。
「神よ、私は悪魔を恐れない。イエス・キリストの力は悪霊を退ける。悪霊達の群れよ、イエス・キリストの御名において、汝を滅ぼし、神の創りし者から立ち去らせん!」
ミケーレの祈りは悪魔祓いの儀式、エクソシズムで唱えるものだ。エクソシストでないミケーレは、悪魔を祓う祈りを碌に覚えなかった。必要ないと思っていた。こんなことなら覚えておくのだった。
ミケーレは、知っている祈りの言葉を何度も繰り返し唱える。
今、自分ができるのはこれだけだ。円狐が平二を救ったように、自分も一目を救いたい。皆が必死なのに、自分だけ傍観者であってはいけない。何より火事で逃げ場を失った人々を、救いに行かなくてはいけないのだ。
ミケーレの祈りの言葉が繰り返されるとともに、一目に取り付いた巫蟲の動きが鈍くなり始めた。火勢のせいで汗だくになりながらも、ミケーレは自分の思いを祈りの言葉に込めていく。すると巫蟲は、一匹、また一匹と地面に落ちて蒸発するように消えていく。
芭尾はその様子に眼を見張った。デュボワを殺した時、確信したはずだった。この西洋の坊主供は物怪の自分には何もできないはずだと。殺される間際でさえ、その力は全く自分に及ばなかった。にも関わらず、ミケーレは芭尾の巫蟲を弱らせて霧散させていく。
ほとんどの巫蟲が落ちると、一目は体をゆっくりと起こす。大きく開いた口から、黒い巫蟲の束を吐きだした。液体のように流れ出た黒い塊は、地上に落ちた先から掻き消えていく。
「ミケーレ・ラブティ、貴様は一体何をした?」
苦々しい顔をした芭尾が、一目の傍らにいるミケーレに言った。ミケーレは、持っていた十字架を芭尾に向ける。しかし向けた先には芭尾がいない。
「お前は、少々厄介だ」
ミケーレは、芭尾の声を耳元で聞いた。驚いて、思わず声の方へ向こうとした瞬間、首を強く固定される。すぐ傍らに来ていた芭尾の手が、ミケーレの喉元を握りしめたのだ。両手で引き離そうとするが、芭尾はびくとも動かない。
「どうやってあの蟲を滅した? 何をした、答えろ!」
ますます力を込める芭尾に、そばにいた一目の拳が飛んだ。芭尾は空いているもう一方の片手でそれを受け止める。そこへ円狐が黙儒を振るうが、芭尾はミケーレを盾にする。
「私がこいつと話をしている。邪魔をするな」
そう言い放った芭尾が突き飛ばすと、一目の巨躯が宙に浮いた。
「デュボワとかいう男が、私を悪魔と呼んで祈祷しても全く効かなかった。なぜお前のは効いた?何が違う?」
「……デュボワ神父は、あ、あの方は……どうしたのデスカ?」
絞られた喉は、うまく声を出すことができない。
「味見はしたが美味くなかった。肝は先ほどの蟲を作る材料にして、残りは全部捨てたよ」
芭尾がにたりと笑う。ミケーレは言葉を失った。自分がいない間に、デュボワ神父が殺されていた。戻って来るのが遅かった、間に合わなかったのだ。既に、この横浜で沢山の人が殺されている。
ミケーレの顔が苦しそうに引きつる。それは喉元を絞められているからだけではない。芭尾は、悲痛な表情のミケーレに問いかける。
「さあ答えろ。なぜだ?」
「知りまセン。私にもわからナイ」
「考えろ。答えなければ殺す」
ミケーレは芭尾の「殺す」という言葉に恐れを感じたものの、すぐに口を開いた。
「なら…それなら、私を殺しなサイ。例え殺されても、私の魂はデュボワ神父と同じく、神の下へ召されるでショウ」
その時、芭尾の背後の家が崩れた。燃える瓦礫が芭尾とミケーレの頭の上に降ってくる。
芭尾は咄嗟にミケーレを突き飛ばして避ける。駆け寄った円狐が、転げたミケーレの手を引いた。芭尾とミケーレのいた場所に、家一件分の瓦礫が広がる。
その瓦礫を挟むように、芭尾と円狐たちは相対した。
「……一目、ミケーレを連れて先に行くんだ」
一目が唸った。その背中には平二が乗っている。
「あたしがこいつを足止めする。あわよくば退治してやるから」
首を横に振った一目は、その場を動かない。
「そ、それなら、私も残りマス」
ミケーレが首をさすりながら言った。その首には、芭尾が絞めた跡が痣になって残っている。
「駄目だ。お前も行くんだよ」
「私の祈りの言葉を芭尾は恐れていマス。――一目サン、早く行ってタケサンたちを助けてあげてくだサイ。お願いシマス」
ミケーレは、平二の太刀を差し出した。一目は躊躇したものの、押しつけられるようにされたそれを、渋々受け取った。
「お前は足手まといなんだ。邪魔なんだよ」
「あなたは自分を犠牲にする気デス。放っておけまセン」
ミケーレは円狐を見据えて言った。ミケーレが芭尾の巫蟲を撃退してみせたのは、決して偶然ではない。もしまた先ほどのようなことがあれば、ミケーレの助けは是非にも必要になる。何より芭尾は、ミケーレに対して脅威を感じている。
「…わかった。でも無理しちゃいけない。いいね。――一目は先に行って逃げ道を作っておくれ」
円狐は、一目の背にいる平二を見た。まだ気を失ったままだ。
「早い者勝ちって約束だ。あたしが先にやる。寝ているお前が悪いんだよ」
囁くように言った円狐の指先が一目を押した。もう行けという意味だ。一目は無言で後ずさると、意を決したように、踵を返して走り出した。