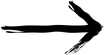※
「一人で行ってさ、万が一に芭尾に見つかったらどうするんだい」
先を歩くタケに聞こえないよう、円狐がミケーレに囁いた。
「……芭尾の力は私には及ばないのでショウ? それなら…」
「確かに、お前に瞳術は効かないさ。でも、お前は何ができる?」
円狐が急ごしらえの十字架を触って「痺れる」と言っていたのを思い出した。十字架は、木枝で作った一時しのぎのようなものだ。円狐は全く動じなかった。きっと、芭尾も同じに違いない。
「それでも、やはり心配なのデス。私は行きマス」
日本人街の細い路地に人通りはない。タケが持っている提灯を頼りにしなければ、足元もおぼつかないほど暗い。連なる家屋の窓からは、中にいる人々の気配はある。だが夜も更けると、余程でなければ外を出歩く者は無い。
先を歩くタケが振り向いて、ミケーレに声をかけた。
「門はそこの角を右に曲がったところ。門番とは、あたしが話しますから」
外国人居留地へ入る門は存外近かった。元々、その門から出てくる異人たち目当てに店を構えようと、人が集まってできたのがこの日本人街だ。門への道は日本人街の中心に位置している。
ミケーレはタケに伴って角を曲がる。真っ暗な中、遠くにぼんやりと灯りが二つ見える。門の前に立つ灯籠の火だ。その火に照らされて、二人の門番の影が揺れている。
近づいてきたミケーレたちを見咎めた門番たちが、手に持った杖を構えて待ち受ける。
「おい、何の用だ? ――あんた、タケさんじゃないか」
門番の一人がタケに気がついた。日々この門を往来しているタケは、門番たちをよく知っている。
「おいタケさん、そこにいるのは異人じゃないのか?」
「こんばんは。こちらは、教会のミケーレ・ラブティ神父です」
「教会って…おい、あれだ…」
二人の門番は顔を見合わせている。様子が変だ。
「実は、ミケーレさんを中に入れて欲しいんですよ。旅に出ていて、さっき戻られたんです。着いた時には、門が閉まっちゃって…」
事情を説明するタケを遮って、門番の一人が言った。
「いや、駄目だ。今はまずい」
「そんな。もちろん手間賃ぐらいは…」
「いや、そうじゃない。今は駄目だ。とにかく家に帰ってくれ」
門番は焦った様子で、早口でまくし立てる。
「どうしたって言うんだい? 少し事情を教えておくれよ」
タケの後ろから円狐が言った。円狐は手を伸ばして、手の平を門番たちに見せるように向けている。その手には銀貨が二つ載っていた。暗がりの中で互いに顔を見合わせた門番たちは、躊躇なく手を伸ばして、それを一つずつ懐に入れた。
「……わかったよ。聞いたらすぐに帰れよ。――実は、居留地の中で殺しがあったんだ」
それを聞いて、思わずタケが「えっ!」と声を上げた。それを門番に制されて、慌てて口を押さえる。
「女中が二人、異人さんの家の庭に打ち捨てられていたそうだ。それと異人も一人殺されていたんだ。それが…」
ミケーレは息を飲み込んだ。先ほどの門番たちの様子から、ずっと嫌な予感がしていた。彼らの自分を見る眼が、まるで哀れんでいるかの様に見えたのだ。
「…それが、教会の人だそうだ」
それを聞いた瞬間、ミケーレは膝から崩れ落ちた。先ほど制されたにも関わらず、タケは門番に大声で詰め寄った。
「殺されたって、どうしてなんです? 一体、誰がそんな事を。殺された異人さんの名前は?」
「俺たちもよく知らねぇよ。でも爺さんだって聞いたぜ。――それより、もうすぐ中から、その女中のホトケが運ばれてくるんだ。あんたらにここに居られると、都合が悪いんだよ。だから早くどっかへ行ってくれ!」
その時、門の向こう側から、どんどんと扉を叩く音が聞こえた。扉の閂は、日本人街と居留地側の両方に掛かっている。両方の閂を外さなければ扉は開かない。
「おい、まずい。早くその提灯消して、その辺に隠れてろ」
門番は慌ててタケに向かって言うと、閂に手を掛けた。平二らは、すすり泣くミケーレを引きずっていくと、家と家の隙間に滑りこんだ。タケが提灯を消したのを見届けると、門番が閂を持ち上げる。
閂の外れた扉を門番二人がゆっくりと前に引くと、半開きのところで止めた。まだしゃくりあげているミケーレの口を抑えた平二は、顔を出して様子を探る。しかし、隠れている平二たちからは、扉が邪魔をして居留地側の様子は見えない。
「おい、今、誰と話してた?」
門番たちとは違う、低い声が言った。
「いえ、酔っぱらいが絡んできたんでさぁ。もう追っ払いました」
「言ったと思うが、このことは他言無用だ。こんな夜更けに亡骸を運び出す意味は、わかるだろう?」
門番たちが「へい」と口を揃えて返事をすると、ぎぃぎぃと大八車を引く音が聞こえてきた。荷台は筵で覆われていて、載っている女中たちの亡骸は見えない。
大八車の周りを、四人の役人が囲んでいる。そのうち先頭を行く男が、車を引く男に指示をすると、車はゆっくりと道を進み始めた。一行は平二たちの前を通り過ぎて行く。
暗い中ではっきりとは見えないものの、大八車を囲んでいる役人の様子はどこか虚ろだ。互いに話すでもなく、目配せもない。じっと前を見つめて歩いて行く。
ミケーレは、その役人の中に見覚えのある顔を見付けた。その役人の顔を確かめようと身を乗り出す。すると無理な体勢であったためか、前のめりになって、脚を大きく踏み出してしまった。
ミケーレは音を立てて、一歩前に出てしまう。その気配に気付いた役人の一人が振り返った。
それは相馬長次郎であった。旅先で病に倒れたミケーレを置き去りにして行ってしまった。その後どうなったかと心配していたが。
長次郎と眼があったミケーレは、思わず彼の名を呼んだ。
「長次郎サン…」
他の役人は脚を止めてミケーレの方を見るが、動く様子はない。
長次郎が、表情を変えずに口だけを開いた。
「ミケーレさん、ご無事でしたか。良かった」
先ほど門番に話していたのと同じ、抑揚のない低い声色だ。宿場では心神喪失したようであった長次郎も、もうすっかり元に戻ったのだろうか。普通に話をしている。安心したミケーレは、止める平二の手を振り払って、更に前へ出た。
「長次郎サン、教会で人が殺されたと聞きまシタ。まさかデュボワ神父では…?」
灯籠の火で照らされた長次郎の表情は変わらず、じっとミケーレを見据えている。
「……ああ、その事ですか。――もう少しこちらに来てください。もう夜も遅いですから、大きな声を出したくない」
そう言って長次郎は、ミケーレに向かって手招きをした。
何の躊躇もなく、ミケーレは脚を踏み出した。影に隠れた平二は、か細い声で「行くな」と言うが、まるでミケーレには聞こえていないかのようだ。
数歩来たところで、ミケーレは長次郎の眼の中にうっすらと青い光を見た。伏し目がちに自分を見る二つに瞳が、まるで蝋燭の炎のように揺れている。それは平二の右眼とは違う、鬱々として寒気を催させる光だ。その光は、長次郎の眼の中で徐々に強くなっていく。
ミケーレは脚を止めた。怪訝そうな表情を浮かべるミケーレに向かって、長次郎が言った。
「どうしました? さあ」
長次郎の声はひどく重苦しい。こんな喋り方をする男であったか。
「おふうさんは、どうしまシタカ?」
「もう少し、近くへ来てください」
「オールトサンは? あの後、一体何があったのデスカ?」
「近くへ来てください。そうしたら話します」
やはり様子がおかしい。他の役人たちも、ミケーレと長次郎のやり取りが聞こえているはずなのに、何も言わぬどころか、微動だにもしない。
ミケーレは、今更になって、長次郎に強い恐怖を感じ始めた。
怖気づいたミケーレが、足を後ろに引いた瞬間、長次郎が視界から消えた。
いや、長次郎の膝が曲がって、体が沈み込んだのだ。腰の刀に掛けた手が、音もなく刀身を鞘から引き出していく。一連の動作が眼にも止まらぬ速さでなされていく。
ミケーレの引いた脚が地につく前に、その体が後ろに引っ張られた。飛び出てきた円狐が引いたのだ。長次郎の横薙ぎに振った刀は、ミケーレの鼻先皮一枚の差で宙を薙いでいった。
後ろへ吹っ飛んだミケーレを飛び越えて、円狐が長次郎の前に出た。その手には象牙の霊刀、黙儒が握られている。そんな長い物をしまう所などないのに、円狐はどこに隠し持っていたか。
それを認めた長次郎は、後ろへ飛び退くように下がると、また刀を鞘に納めて、体を沈み込ませるように構える。他の役人も鞘から刀を抜いて集まってきた。
「こいつら、一体なんだ?」
平二が円狐の横に並んだ。手には既に太刀を構えている。
「長次郎とか言ったね。宿場で芭尾に瞳術を掛けられた侍だよ。ミケーレが言っていたじゃないか」
それを聞いて、平二は思い出した。萬澤宿までミケーレと一緒にいた役人だ。
長次郎と役人たちは、全く動こうとしない。しかし、その目線は平二たちを見据えたままだ。
「こいつら、芭尾に操られている。――厄介だね」
「どういうことだ?」
「相変わらず頭が悪いね。右眼で見てご覧よ」
円狐に言われて、平二は慌てて右眼を隠す布を引き上げた。長次郎と他の役人たち全員の両目が、青黒い光を放っている。幾つもの蝋燭の火のように緩い光が、平二たちの方を向いていた。
「こいつら、この前と同じか」
「ああ、瞳術で操られているんだろうさ。それにしても…」
「…?」
「…こんな大勢に暗示をかけるなんて、あたしには無理な芸当だ」
長次郎が、にじり寄るように脚を滑らせて距離を縮めていく。それに合わせて、平二と円狐も後ろへ徐々に下がっていく。
長次郎の体が沈み込んだ。それと同時に腕が前に伸びる。鞘から飛び出した刃が光ったと思った時には、もう円狐の鼻先まで刀の突先が届いている。それを、すんでのところでかわした円狐は、平二を横へ突き飛ばした。横に流れた長次郎の刃は、平二のいた場所を下斜めから切り裂いていく。その間、ほんのわずか。
慌てて体勢を立て直した平二に、円狐が叫んだ。
「平二、長次郎はあたしが相手をする! お前は他の奴らを抑えな。――ミケーレは、タケを連れて逃げるんだ。そしたら一目を呼んでおいで!」
早口でまくし立てた円狐は、ミケーレとタケを背にして長次郎と相対する。
少し離れた位置から、平二は回りこむように移動する。悔しいが、長次郎は円狐に任せた方がいい。昨晩、平二は円狐相手に散々切りかかったにも関わらず、刀は掠りもしなかったのだ。剣や体術では、円狐の方が上だ。
平二が動くと、長次郎の後ろに構えた三人が刀を向けてくる。後ろに回り込もうとした平二の意図に感づいたらしい。いずれも小奇麗な着物に銀杏髷を結っている。野良着に髪を引っ詰めただけの平二とは対照的だ。
三人の注意を自分に引きつけたまま、平二は門の方へ走った。
突然始まった斬り合いを傍観していた門番二人は、一応、平二に向けて杖を向ける。しかし勢いよく駆けてくる平二に慄いたのか、避けるように飛び退いてしまった。
平二は三人を背にしながら、門の閂を支えている金具に脚をかけると、宙高く飛び上がった。真っ暗な中空を飛ぶ平二を、青い六つの眼が見上げている。
平二の体が、三人を飛び越えて降り立つと、目の前にいた男に向けて、力いっぱい刀を振り下ろす。ごきりっという鈍い音がして、男が崩れ落ちた。
平二が手にした太刀の刃は、自分の側に向けられていた。峰打ちで首筋を叩かれた男は、切られなかったとはいえ、骨ぐらいは折れただろう。衝撃と痛みで刀を落とした男の足元を、力いっぱい横薙ぎにする。脛に分厚い刀の峰がめり込んでいく。男は叩かれた脛を押さえて、その場に倒れた。
これも右眼の力なのか、男たちの動きが遅れて見える。それに比べて自分の動きが速いので、むしろ調子は合わせにくい。
残り二人が、平二に向けて同時に詰め寄ってくる。
平二は、大八車の後ろへ回りこむと、片手で取っ手を持ち上げて、男らの方へ思い切り押し出した。腰の辺りを打ち付けられた男が後ろへひっくり返ると、大八車の上に載っていたものが、その男の上に転げ出した。
裸に剥かれた二つの亡骸は、腹を大きく割かれて、がらんどうになっている。眼玉も両方抜かれたか、眼孔も空っぽだ。いずれも死に際に地獄を見たのだろう。口は大きく開かれて、眉間に幾重もの皺を寄せている。
平二は大八車を、倒れた男の上に来るように押した。遺骸に組み敷かれて動けない男は、更に大八車が乗っかって、もう身動きが取れなくなった。
平二は残った一人に刀を向けながら、円狐を横目で探す。
視界の中に、ミケーレとタケが見える。二人は道端に座り込んで動けないでいた。その傍には、相変わらず長次郎を相手に、黙儒を構える円狐がいる。
平二は、視線を目の前の役人に向けたままで言った
「円狐、ミケーレたちを連れて逃げられそうか?」
「…さあね。やってみるかい?」
円狐はそう言いながらも動かない。いや、動けないのだ。長次郎は円狐を狙っていない。その向こうにいるミケーレを狙っている。
平二と相対していた男が動いた。大きく刀を振り上げて、平二の目の前に踊り出る。平二は、それを刀で受けると、男の腹を蹴り飛ばした。後ろへよろけた男の膝に、斜め上から振り下ろす。刀の峰が膝の皿を砕いて、更に奥へとめり込んだ。これでもう立てまい。
平二は振り向いて長次郎に刀を向けた。刃は自分に向けたままだ。
「平二、お前は手加減できる程の腕じゃあるまい。生意気するのはおやめよ」
横目で平二を見た円狐が言った。
平二は「うるせえ」と返すと、長次郎ににじり寄る。
先ほどまで動かなかった長次郎が、少し下がって体の向きを変えた。円狐と平二、両方の真中に向くように立つ。
「近づき過ぎるんじゃないよ。こいつのは抜刀術だ。さっき見たろ、すこぶる早い上に、遠くまで届く」
その言葉を聞いて、平二はじりじりと近づけていた足を止めた。
他の男たちと比べると、長次郎の剣捌きは群を抜いている。芭尾に操られているにも関わらず、こうして対峙していても一分の隙もない。瞳術で幻惑されながら、ここまでの業を見せるのは、元々が相当な手練なのだろう。
戦のない世では、侍も碌に剣を振ったことのない輩が増えたが、この長次郎は、よほど鍛錬を積んだに違いない。その実力は、自我を失ってなお鋭い剣筋を見せ付ける。
「あたしがこいつを抑える。お前はミケーレたちを連れて逃げな」
「勝手を言うな。お前が逃げろ」
その時、先ほど膝を砕かれた男が、片足飛びで平二に襲いかかった。男が手にした刀を振るうと、思わず平二は飛び退いた。飛んだ先には長次郎がいる。
長次郎は、この好機を逃さなかった。近づいた平二の背に、斜め下から強烈な一閃を浴びせる。飛び込んだ勢いで、刀は平二の体に、深くめり込んだ。刀はそのまま肩口へ抜ける。
刀が抜けた瞬間、平二の肩から赤黒い血飛沫が吹き上がった。
「平二っ!」
円狐が黙儒を長次郎に突き出した。倒れてきた平二を避けようと動いた長次郎は、円狐の動きに対して一寸遅れた。精一杯の妖力を込められた黙儒が、長次郎の左脇腹に触れた瞬間、激しい炸裂音とともに、青白い稲妻がほとばしる。その勢いで長次郎が吹き飛んだ。
平二に飛びかかった男が、砕かれた膝を引きずりながら円狐に向かっていくが、それも黙儒で切り払われる。
「ミケーレ、平二が斬られた! 早く、早く手を貸してっ!」
円狐が悲痛な声を上げて、ミケーレの助けを乞う。
ミケーレが慌てて平二に駆け寄ると、仰向けに倒れた平二の下に、みるみる黒い染みが広がっていく。血が流れ出しているのだ。
「糞っ、糞っ! なんでこんなことに!」
円狐は平二を抱き起こすと、血で汚れるのも構わずに、傷口を手で押さえた。
「すぐにここから逃げるんだ。早く平二を!」
屈んだミケーレが、平二の下に潜り込むと、その体を背負った
「でも、どこへ行けば…」
「ミケーレさん、とにかく、あたしの家へ」
「でも…、もうタケサンに迷惑をかけられまセン」
ミケーレは、タケの申し出に躊躇した。これ以上彼女を巻き込んではいけないと思ったからだ。
「迷惑だなんて思わないよ! こういうのはね、『乗りかかった船』って言うんだ。早くしないとその人が死んじまうよ!」
そう言うとタケは、手招きしながら、急ぎ足で歩き出した。
黙ってそれに付いて行くしかない。
真っ暗な街中を、月の明かりを頼りに歩いて行く。背負った平二から流れ出す血が、手に絡んで滑る。何度か抱え直しているミケーレを見て、円狐が平二の体を後ろから支えた。血の跡が地面に残らないよう、着物の袂を平二の背中に押し付ける。
一行は小走りでタケの家へと向かった。
一連の様子を見ていた門番たちは、どうしたものかと困惑した。目の前では、女中の亡骸と、大八車の下敷きになった侍が呻いている。しかし、二人共々腰でも抜けたか、立つことさえ出来ない。
「なあ、お前たち」
視界の端から声が聞こえた。恐る恐るそちらを向くと、長次郎が立っている。先ほど、大きな音とともに吹き飛ばされた男は、脇腹の辺りを押さえながら、門番たちを見下ろしている。
手で押さえた辺りが、妙にへこんでいる。脇腹の肉が吹き飛んでしまったのだ。だから中身が出ないように手で抑えている。それに気付いた門番たちは、恐怖のあまり失禁した。
「なあお前たち、見ていたか?」
「い、いい、いえ、その、く、く、暗くて、み、見えな…」
「聞こえないな、もっと近くに来て言ってくれ」
長次郎は門番たちを見下ろして言った。
二人は怯えた様子で動けないでいる。
「近くに来てくれと言っている」
そう言った刹那、長次郎の刀が、門番二人の喉元を横一線に切り裂いた。
斬られた箇所に赤い筋が浮かぶと、二人の首からほぼ同時に血が溢れ出す。心臓の鼓動に合わせて、血がごぼり、ごぼり、と流れ出してくる。
「だから、近くに来いと言った。――来れば、ひと思いに首を跳ねてやったのに」
長次郎は口端を持ち上げて、にやりと笑う。
血にまみれて絶命していく門番たちをよそに、長次郎は一人、居留地へと戻っていった。
※
長次郎が眼を開けた時、ミケーレたちは立ち去った後であった。
何が起こったのか分からなかった。夜更けの街中でうずくまる侍たちと、転がる女の亡骸。腹からは血が溢れ出し、袴を濡らしている。痛みより、血濡れた袴が足にまとわりつく方が不快であった。
はらわたが傷口からずり落ちそうになる感覚さえある。それを手で押えると、やっと自分が怪我していることに気がついた。それが分かると、痛い気がしないでもない
一体何があったのかと自問するも、何も思い出せない。
記憶にあるのは、ヨハン・オールトとミケーレ・ラブティに同道して行った旅の途中まで。二人の顔、辿り着いた宿場でのこと。着いて真っ先に番所に行ったのだ。
――はて、なんで番所に行ったのか。
そこまで思い出して、青黒い光を湛えた二つの瞳を思い出した。
長次郎の双眸を突き刺すように見つめる、青く光る瞳。それは異人の青い瞳とは違う、蝋燭のような淡い光を湛える瞳だ。その光がなんであったか、思い出そうとする長次郎は、また徐々に自我を失っていく。脇腹はもう痛くなかった。
そうして長次郎は、門番らの首を斬った。門を抜けて居留地へ戻ると、ふらふらと歩いて行く。行き先はオールトの邸宅だ。
横浜に着いてから、長次郎は自分の家に帰っていない。石畳の舗装された道路の上に血痕を残しながら歩いて行く。街のあちこちに役人が立っているが、皆、長次郎と同じ眼をして、ぼうっと立ち尽くしている。
オールト邸に着くと、関兵衛が扉を開けた。お互いに言葉も無く黙ったままだ。灯されたランプの明かりに沿って屋敷の奥へ進むと、大きな居間に突き当たる。ソファの上には、オールトがふんぞり返っていた。まるで体中の骨という骨を抜かれたように、だらりとソファに体を預けている。その口はだらしなく開いていて、端からよだれを垂れ流している。文字通り、骨抜きだ。
部屋の窓際には、青いドレスに身を包んだ芭尾が立っていた。窓の外から見つめる先には、横浜の港がある。海は暗くて何も見えないが、港に停泊した船の灯りが微かに見える。
「誰にやられた?」
芭尾が窓の外を見ながら長次郎に声を掛けた。
「…ミケーレ・ラブティ。他に、見たことのない男と女」
長次郎が答えると、芭尾が振り向いた。冷淡な目付きで睨む。
ミケーレ・ラブティは、長次郎たちと一緒にいた神父だ。瞳術が効かず、巫蟲を飲ませて置き去りにした。万が一に宿場から逃げた時の備えもした筈であったが、なぜ横浜に居るのか。
「それは間違いないのか?」
「そう自分で名乗っていた。それにあの顔は見知っている」
長次郎も関兵衛同様、極端な忠誠心を発揮する部類らしい。主人に纏わり付いて離れず、理不尽な要求も、二つ返事で受け入れる。
病的なまでに偏った精神を持っている者は扱いやすい。それが持つ心の偏りを別の方へ向けさせる。芭尾は、関兵衛や長次郎の忠義心を、暗示で自分に向けさせた。
長次郎は何度か正気を取り戻したものの、都度、瞳術をかけることで、もうほとんど自我を失っている。芭尾のために考え、行動する下僕に成り下がっていた。
「それで?」
「門破り、そして番人殺しの下手人として手配した」
「男と女、どんな奴らだった」
「女は紫の着物で、白い刀のようなものを持っていた。男は浪人らしい風体だ。片方の眼が赤く光っていた。――こいつは斬った」
芭尾はそこまで聞くと、また窓の方に振り返った。
白い刀を持った女と、眼が赤い男というのは、太秦坊の手の者に違いない。それが追う過程で、どういうわけかミケーレ・ラブティを徒党に組み入れた。どのような追手か知らないが、後少しというところで気を揉ませてくれる。
港に見える船の灯は、芭尾が乗る商船団の船だ。デュボワを殺した後で、オールトに澳門へ行く意思を伝えた。オールトの国にも行ってみたいとも伝えた。だから、すぐに船を出せと言った。言葉は関兵衛に訳させたが、上手く伝わったようだ。オールトは小躍りし、出港を早める為に、夜通しで準備をさせているらしい。
全て上手くいっているにも関わらず、そこまで追手が来ている。しかも奴らはラブティと一緒にいる。芭尾が居留地にいることを知っているのだ。間髪入れず、こちらへ押し入って来るに違いない。
長次郎が、ラブティらを下手人に仕立てたのはいいが、それでも不安だ。奴らも物怪である以上、人外の力を持っている。
「斬ったという男はどうなった」
「逃げた」
「なら死んでないのか?」
「多分。だが傷は深い」
芭尾は思った。その眼の赤い男が物怪ならば、何故、長次郎の刀で斬れたのか。物怪はただの刀では切れぬ。ならそれは『人』か。それにしては、片目だけ赤く光るとは、一体どういうことか。
太秦坊は一体、何に自分を追わせているのか。不明瞭なことばかりで、心中穏やかでない。
「…長次郎、日本人街に火を点けろ。そいつらを炙り出せ」
それを聞いた長次郎の顔が強ばる。じっと眼を見開いたままで、返事をしなくなった。
日本人街にある家屋は、ほとんど木と紙でできている。火をつければ、あっという間に燃え広がっていく。しかも今はもう真夜中だ。こんな時間に火事になれば、どれだけの人が巻き込まれることか。
長次郎の眼の奥で、青黒い光が明滅し、徐々に弱くなっていく。命令の理不尽さに、必死で心が抵抗している。
「…だ、駄目だ」
そう言って長次郎は、激痛が走る脇腹を押さえた。血が長次郎の下半身を真っ赤に汚して、既に床まで染みを作っている。
「その怪我のせいで、いくらか自分を取り戻したか。――まったく素直じゃない」
眉間に皺を寄せると、芭尾はため息をついた。
脇腹の痛みがきっかけで、徐々に意識が明瞭になっていく。痛みが自分ものだと自覚する度に、自己を取り戻していく。はっきりとしていく意識の中で、今しがた、自分が三人も斬ったのを思い出した。焦りと後悔の念が湧き上ると、一気に自分自身が覚醒する。
――私は一体何をした?
部屋を出ようと踵を返した長次郎の前に、芭尾が立ち塞がった。怯えた眼で後ずさりする長次郎の口に、黒いものを握った手を押し当てる。芭尾の作った巫蟲が、次々と体に入り込んでいくと、長次郎は呻き声をあげた。
「これで怪我も痛まない。暗示から醒めることもあるまい」
巫蟲の束は、うねりながら長次郎の唇をこじ開けて、そっくり中へと入り込んでしまった。巫蟲は寄生した宿主を喰らう時、神経を麻痺させる麻薬のような分泌液を出す。体内がそれに満たされるにしたがって、宿主は喰われながらも痛みを感じず、咀嚼される不快感に苛まれる。これでもう長次郎は、中身を食い尽くされるまでは暗示から抜け出せないであろう。
どうせこの男は長くない。最後にもう一働きしてもらう。芭尾は、その青い光を湛えた瞳で、長次郎の眼を覗き込む。
「その男と女のことが気になる。――私もそいつらを見ておきたい」
船が出るまでにはまだ時間がある。むしろ不安は早い内に消してしまった方がいい。
芭尾は関兵衛に外套を持ってこさせる。オールトが用意した上品なキャメルのコートは、芭尾の体をくるぶし辺りまで覆う。
追手は夜襲を仕掛けてこようとした。ならば今度は、こちらが追い詰めてくれる。
芭尾は長い舌で口元を舐めると、長次郎を従えて部屋を出た。