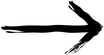五、横浜
平二は横浜の港が見渡せる丘の上に立っていた。
そこからは、港に隣接した外国人居留地と、それを囲むように広がる日本人街が見渡せる。もう日が落ちる頃だというのに、街中の人通りは一向に減らない。居留地には整然と区画整理され、石造りの屋敷ひとつ一つが大きい。それに比べて日本人街は、木造の平屋が所狭しと立ち並んでいる。
一八五八年に締結された日米修好通商条約を皮切りに、神奈川と兵庫に外国人居留地が設けられることになった。神奈川に関しては、元々がうら寂しい漁村であった横浜村を、幕府が外国人居留地として開港した。東海道沿いの神奈川宿に居留地を構えることを切望していた各国の使節団は、話が違うと抗議した。しかし幕府は、既に横浜の湿地帯を干拓し、埋め立てを終えていたのだった。桟橋も整備され、大型船が常時十数隻は停泊できるようにまでなっていた。
世界中から富が集まる港へと発展した漁村は、年々その規模を拡大している。外国人たちが持ち寄った富に、人が群がる様に集まって来る。居留する外国人の数は年を追うごとに増えていき、当初の埋め立て地だけでは到底足りなくなった。そのため、干拓は絶えず続けられている。
居留地内は縦横直角に交差する通りが敷かれ、各国の区画が割り当てられている。屋敷の多くは石造りの二階建てだが、中には日本風の木製家屋を建てる者もあり、町並みは混沌としている。
横浜から東海道の神奈川宿へとつながる道沿いには、居留地に近い所から物売りの店が連なっていった。漆器、象牙、磁器や水晶、そうした高級品や美術品を外国人に売りつけるためだが、ガラクタから江戸の商人が持ち込んだ一級品まで、玉石混合の様相を呈している。初めのうちは物珍しさもあって、外国人たちがこぞってそれらを買い求めたが。今では目が肥えたのか、滅多な物にしか手を出さなくなったし、片言の日本語での値段交渉は当たり前になった。
横浜居留地に隣接する港崎遊郭は、幕府が横浜居留地の外国人にあてがった遊郭街である。オランダ公使の要請によって作られたこの遊郭には、近隣の日本人と外国人の男たちが、夜の愉しみを求めてやってくる。特に岩亀楼という遊女屋は、幕府のお墨付きで外国人向けの遊女を置いていた。外国人たちはこの遊郭街自体を「ガンキロー」と呼ぶ程にこの遊女屋を親しんだ。
一八五八年に開港されてから、たったの八年で、横浜は巨大な貿易港に発展した。日々なだれ込む異国の文化を吸収し、急速に発展していく横浜に、日本人はそれなりに順応してきている。
丘の上から見下ろした景色は、平二が初めて見る光景だった。間断無く小さな家が密集している日本人街の向こうには、曲がりくねった運河を挟んで、大きく彩り豊かな屋敷がならぶ外国人居留地がある。そして海には、お互いがぶつかりそうなほどに密集している無数の船が見える。小さな船の多くが、日本でよく見る平底の帆船だが、大きなものはおおよそ見たこともない形をしていた。それらが頻繁に鳴らす汽笛の音は、平二たちのいる丘の上まで鳴り響く。
身延を出てもう丸三日が経っていた。箱根の関所辺りからは、円狐の妖力で所々姿を消しながらやって来た。太秦坊から渡された呪符は、円狐が傍に居て、見る者に妖力で暗示を掛けねば姿は消えない。およそ眼が会う程度でいいらしいが、一度にたくさんは無理だという。結局、面倒がる円狐のために、林や人気のないところを選んで走った。おかげで思ったより時間を食ってしまった。
街を見下ろす平二の傍らには、気を失ってから、ずっと眼を覚ましていないミケーレが横たわっている。平二が揺さぶって目を覚まさせると、ミケーレはうつろな表情で目を開けた。
「眼が覚めたか」
「……」
「もう着いた」
ミケーレは「エッ」と声を上げて、ゆっくりと体を起こした。眼前に見覚えのある港の景色が広がっていた。今は夕方頃だろうか、地平線の近い所に太陽がある。ふと股間の涼しいのに気づいて見下ろすと、いつの間にか、服も着物に着替えていた。
「眠りこけているから、抱えて連れてきた。そういや、あんたは宿場を出てから一歩も歩いてないだろ」
平二は笑いながら、ミケーレの傍らに座り込んだ。
「悪いが、勝手に呪符とかいうのを貼らせてもらったぞ」
ミケーレは手を額に当てるが、もうあの紙はない。
「円狐と一目はとりあえず腹拵えをしてる。とは言え、あいつらの場合は飯を喰うのじゃなく、妖力とか言うのを溜めるらしい。木の実やらをしゃぶってりゃいいんだと。便利なもんだ」
「……」
「お前、一目の顔を見たんだろ? 俺だってまだ見てないんだ。どんなだった?」
平二に言われたことで、ミケーレは気を失う前に見た光景を思い出した。自分を見下ろす一つ目の大男だ。不思議と恐怖はなかったものの、衝撃的ではあった。
「…あなた方は、一体何者なのデスカ?」
「切れぎれに聞いてるから、よくわからんだろ。――円狐が、自分らがいない間に話してやれとさ。あれであいつら気を使ってるんだろうな、物怪のくせに」
ミケーレは辺りを見回した。確かに円狐と一目の姿は見えない。
「俺はあんたと同じ『人』だ。円狐と一目は物怪だ、人じゃない」
一目が人ではないというのは分かる。円狐も物怪だろう、自分でそう言っていた。しかし――。
「でも平二サン…私は、あなたの眼が赤く光っているのを見まシタ。何故デスカ…?」
「平二でいいよ。さんなんてつけて呼ばないでくれ」
そう言って平二は右眼を隠している布をずり上げる。右眼が露わになると、それを指さして言った。
「これは円狐と一目たちの親分みたいなのにもらった。なんでもその親分は天狗なんだそうだ」
「ハァ?」
眼を貰うとはどういうことか、理解に苦しむ答えだ。そもそも天狗というのが何かもわからない。今はその眼も光ってはいない。
「女房が殺された時、俺も腹を割かれて中身を全部出されちまった。その上、眼玉も一つ喰われちまったんだ。だからその天狗が、俺に右眼をくれたのよ。これのおかげであっという間に傷が塞がって、今じゃこうしてぴんぴんしてる」
平二は自分の着物の胸元を軽く拡げて見せた。胸から腹の方に、痛々しい傷跡が残っている。確かにかなり深そうな傷で、あっという間というほど簡単に治りそうなものではない。
「でも、怒ったり泣いたりすると、眼が光って暴れ出すんだとさ」
ミケーレは山中で見た平二の姿を思い出した。激しく光る右眼に赤銅色の肌。顔に深く皺を寄せて歯を剥き出しにしていた。暗くて良くは見えなかったものの、あれは決して人の姿ではない。
彼らの話すことは、迷信的な妄想の産物だとしか思えなかったが、与えられた薬や、何日も休まず走れる驚異的な体力、一つ目の大男に平二の眼、どれにしても事実ではある。だが、ミケーレのキリスト者としての常識から言えば、はなはだ受け入れがたい事実だ。
「…モノノケというのは、悪いものでショウ? それを私たちはデモンとかデビルと呼びマス」
平二は「ふーん」と気のない返事を返す。
「人を騙したり、陥れたりして不幸にシマス。デモンは神から人を遠ざける。そしてあなたの命を奪いマス」
「確かに円狐には騙されたなぁ。あいつはむかつく奴だ。でも、物怪っていうのは人を殺して喰ってしまうものかと思ったが、そうでもないらしい。お前も聞いたろう、『人』なんぞ臭くて触りたくもない、喰ったりなんかするもんか、ってさ」
「そうは言ってましたが、でも……」
「あいつらは、俺やあんたみたいな『人』が大嫌いなんだそうだ。いまは、芭尾を追うのに仕方なく一緒にいるんだと」
ミケーレはこの国へ来て、初めて居留地の外へ出た。見るもの全てが物珍しかったが、この一行に出会ったことは、人生で最も鮮烈な出来事だ。妻を殺した仇を追う男と、それに連れ立つ人ならざる者たち。ミケーレは執筆していた旅行記のことを思い出した。日本の風俗や文化、見たものを記録するように書き付けてきたが、こんな体験を書いたとしても、誰も信じることはあるまい。
「ミケーレさんよ、あんたの目的はここへ戻ってくることだったな。約束通り、俺たちをあの居留地ってとこに入れてもらう」
横浜まで連れて来てもらった代わりに、居留地に彼らを入れてやらねばならない。さて、どうしたものか――。
「まさか、忘れてたわけじゃないだろうな」
「いえ、そんなことはないデス。でも…」
「でも?」
「あなたたちをあそこへ連れて行っていいのか、迷いマス」
それは、平二と円狐も予想していたことだった。自分たちの正体を知ったミケーレは、居留地へ平二たちを連れて行くことを拒むに違いない。だから、わざわざ『人』である平二がミケーレと二人で話すことになったのだ。
「安心しろ。言ったろ、円狐たちは人を殺さないって」
「…あなたは、どうなのデス?」
ミケーレはじっと平二の眼を見つめる。その真っ直ぐな視線に、思わず平二は視線を逸らした。萬澤宿で平二が役人を斬り殺しているところを、ミケーレは見ている。
平二はまさか自分が拒絶されるとは思ってはいなかった。
「なんだよ、人殺しは連れていけないとでも言うのか?――いいぜ、ならお前を脅してでも…」
そう言って平二は膝立ちになると、腰に差した太刀に手を掛けた。
「脅しても無駄デス。――それより私の話を聞いてくだサイ」
平二は太刀に手を掛けたままで、動きを止める。
「あなたと円狐サンの話は聞きまシタ。あなたは人を殺めたことを後悔しているのデショウ?」
黙ったまま返事をしない平二に構わず、ミケーレは言葉を続けた。
「人の命を奪うのは、決して許されないことデス。でも、あなたが自分のした行為を悔いているのなら、まだその罪を償う機会はありマス。あなたはまだ若い、そのための時間は十分にありマス」
平二は返答に迷った。円狐に指摘された通り、そしてミケーレの言う通り、宿場で殺した役人の顔が頭から離れない。
人を殺めたのは、これが初めてではない。賊であった時に何度か人を斬っている。だが今は何とも言えない、むしゃくしゃした気持ちを抱えている。後ろめたい気持ちが沸き起こるのだ。
きっと自分は、おゆうに出会ってから変わった。賊をやめ、おゆうと暮らすと決めた時から日和ってしまったに違いない。
「俺には、そういう難しいことは分からねえよ」
「いえ、あなたは分かっていマス。あなたの眼を見れば分かりマス。まだあなたの眼は、澄んだ水のように綺麗デス。罪を償うことを諦めた者の眼は、どの国の者でも濁った色をしているものデス」
「言ったろ、俺の右眼は天狗にもらった眼だ。あんたが見ているのは物怪の眼さ」
「でも、もう片方はあなたのものでショウ?」
平二は太刀に掛けた手を下ろして、また元のように座った。
「罪を償うために、善い行いによって神を喜ばせるのデス。善い行いの積み重ねによって、神は必ずあなたに報いてくれマス」
妙石庵の日嘉も、同じようなことを言っていた。使う言葉は違っても、どの神様でも言うことはさほど変わらないらしい。
「やっぱり、俺にはよく分からねえよ」
「簡単なことデス。もう誰も傷つけてはいけまセン」
「でもな、おゆうの仇は――芭尾は俺が殺さないといけない」
「おゆう…おゆうさんというのがあなたの奥さんでシタカ? あの、おふうという…」
言いかけたミケーレの言葉を遮るように平二が口を開いた。
「…あんたが見た女の見掛けだけだ。芭尾がおゆうの皮を被ってる。本当のおゆうは…あんなじゃない。あんな下種な笑い方をする女じゃないんだ」
平二は先ほど押し上げた右眼を隠す布を下に戻した。おゆうのことを思うと、どうしても気持ちが高ぶる。それだけに芭尾に対する怒りと憎しみが膨れ上がってくるのだ。
「すいまセン。そういうつもりでは…」
「いいんだ、別に。あんたの知ったことじゃないさ」
「…そうじゃないんデス。どうかもっと、自分の気持ちに素直になってくだサイ。あなたは言うほど悪い人ではないはずデス」
「短いつきあいで俺の何が分かる? 大体あんたとまともに話すのはこれが初めてだ」
「そこまで必死に奥さんの仇を討とうという人が、悪い人だとは思えマセン。それに…」
「…?」
「円狐サンも、言うほどあなたを嫌っているようには思えまセン。――一目サンに関してはわかりませんが…」
平二は呟くように「まさか」と言うと、ミケーレの方へ向き直った。
「とにかく、俺たちをあそこへ入れてくれ。――手荒な真似はしたくない。頼む」
「もう二度と人を傷つけないと約束してくだサイ。そうしたら連れて行きマス」
平二はしばし考え込んでから口を開いた。
「…分かった。でも芭尾は別だ」
「…許せないのデスカ? どうしても」
「元々、それが目的でここまで来た」
「例え復讐を遂げたとしても、悲しい気持ちは決して減りまセン。せめて捕まえて、罪を償わせることは出来ないでショウカ?」
「無理さ。あいつは大昔に捕らえられて、ずっと封印されていた。それに俺は、奴を許すつもりはない」
平二は語気を強めた。
この調子では、ミケーレの助けがなければ居留地へ押し入るだろう。復讐心で先の事を考えられなくなっている。
「……私は、あなたがしようとすることを受け入れることも、許すこともできまセン。でもあなたの気持ちは分かりマス」
「なら…」
「あなた方は、私と一緒に教会の手伝いということで居留地に入りマス。教会で働いているタケサンという女性がいマス。その人が働きたい人を教会に連れてきてくれるのデス。その人にお願いして、一緒に行ってもらいまショウ」
教会では、雇っている日本人に頼んで、週に何度か教会の掃除の手伝いとして、日雇い人を連れてきてもらっている。普段は入れない居留地に入れる上に、賃金まで貰えるということで都度大勢が集まってくる。そうやって少しずつではあるが、来た者たちに教えを説いているのだ。
その時、円狐が遠くから平二に声を掛けた。声の方へ振り向くと、円狐と一目が立って、こちらの方を見ている。二人の話を聞いていたのだろうか。それにしては気配がなかったが。
円狐はゆっくりと二人の方へ近づいてくる。それに続いて一目も、ざくざくと草を踏みしめる音をさせて歩いてきた。
ミケーレは、円狐と一目に対して不思議と恐怖を感じなかった。もう二日も一緒にいる。何かする気なら、とうの昔にされているはずだ。そもそも死にかけていたところを助けてくれたのは彼らだ。
それに、十字架を不思議そうに撫でる円狐の表情は、とても悪魔の類とは思えなかった。それだけ神秘的で美しかったのだ。
「話は済んだのかい?」
「白々しい。どうせそこで聞き耳立てていたんだろう?――済んだよ。連れて行ってくれる」
「そうかい」
円狐はそう言って、ミケーレに向き直った。
「そうと決まればすぐに行くよ。ミケーレ、ここからはお前さんが頼りだ」
その言葉に、ミケーレは力強く頷いた。
「――急ぐよ。芭尾はここにいる。間違いない」
円狐の言葉を聞いた平二がすかさず訊いた。
「臭いか?」
「『人』の臭いだけじゃない、獣を焼く臭い、油の臭いもする。そんなのが全部混じって腐ったような臭いになっているのさ。――その中にね、生臭い『人』の血の臭いが混じっているんだ。もう芭尾の臭いはない。でもこの血の臭いの量はね…」
皆まで言わず、円狐は着物の袂で鼻を抑える。途中で話をやめたのは、結論を言うのをためらったのだ。それを察した平二が言った。
「それは人が沢山死んでいるってことか?」
「多分。血を流して殺されてるんだ。――芭尾があそこの中で、人を喰っているのかも知れない」
ミケーレは思わず息を飲んだ。芭尾に連れて行かれたオールトや長次郎は、どうなったのであろう。急に不安に駆られたミケーレは、胸元から木枝で作った十字架を取り出すと、胸前にかざした。
「…神よ、どうか皆をお守りください……」
俯いて神に懇願するミケーレに、平二が話しかけた。
「お前の言っていたタケって人の家に案内してくれ。今晩の内に話をつけて、明日の朝一番であそこに入る。そんな念仏みたいなのをぶつぶつ唱えたって、芭尾は倒せないぜ。――ほら、立つんだ」
平二はミケーレの腋に腕を通すと、無理やり引き上げた。
平二が「さあ」と促すと、ミケーレは無言で頷いて丘を下りだす。円狐の言ったことが相当に堪えたのだろう。十字架を持つ腕は小刻みに震えている。
もうすっかり日が落ちて、街に明かりが灯り始めた。一際明るいのが遊郭街だ。平二たちが目指すのは、そこから離れた暗く明かりの少ない区画、日本人街だ。
この中に芭尾がいる。おゆうを殺し、おゆうの顔で人を喰っている。あいつだけは絶対に許さない。
平二は、眼下に広がる横浜居留地を睨みつけた。