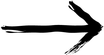※
横浜居留地には木造のカソリック教会がある。居留地に滞在する各国の代表団や、商業使節団からの寄進を元に作られた教会だ。
ヨーロッパで培われた石造りの意匠こそないものの、日本の大工が丹精こめて作った木造の建物は隅々まで丁寧に作りこまれており、質素ながら品格にあふれる外観となった。
そこにはフランス人であるロベール・デュボワ神父の他に、半年ほど前からミケーレ・ラブティ神父も滞在している。齢五十を超えるデュボワは、インドで宣教師として布教に努めていたが、一昨年、日本にやってきた。居留地の住民たちの寄進を元に日々の糧を得て、慎ましい信仰生活を送っている。
この遠い東の異国において、居留地に住む人々の心の拠り所であるこの教会には、日々大勢が祈りを捧げにやってくる。他にも、日本人でカソリックに改宗した者たちも来る。そのほとんどが居留地に住む外国人宅で、召使のような仕事についている者たちだが、中にはデュボワの説教に共感して、カソリック教徒となった神奈川藩の役人もいた。
オランダの商業使節団長であるヨハン・オールトは、かなりの金額をこの教会に寄進してくれている。建立時の寄進だけでなく、まとまった金額を定期的に提供してくれているのだ。しかも人格者で、金は出すが口は出さない。教会にとってはありがたい人物だった。
そのオールトが突如変節した。旅から戻ってからというもの、明らかに様子がおかしい。
旅先で病に倒れたラブティ神父を置き去りにしてしまうばかりか、助けたという女性を澳門に連れて行くので、口説くのを手伝えと言う。まさか神父である自分に、そのような下世話な頼みをしてくるとは思わなかった。しかも夜中に、顔を腫らした関兵衛を使いにやってまで頼んできたのだ。オールトは東洋人に対して侮蔑的な言動をするきらいはあったが、手を上げることはなかった。
関兵衛に顔の痣のことを問いただしても、ころんだと言うばかりで何も言わない。殴られた跡であるのは明白であるのに。そうした日本人の主人に対する忠誠心は敬服すべき点ではあるが、時には極端に習慣的であることは否めない。
今朝オールト邸を訪問し、おふうと言う女性に頼まれた通りの話はした。これまで世話になっている手前、無下には断れない。しかし帰り際に、おふうを教会へ連れてくるよう関兵衛に言い含めた。オールトの考えていることは、おおよそ想像がつく。おふうが訳のわからぬままに、澳門へ連れて行かれるようなことにはしたくない。
キャソックと呼ばれる黒い立襟の司祭服に身を包んだデュボワは、手にした懐中時計を見た。時計の針は午後一時を指している。関兵衛には、正午までに教会へおふうを連れてくるよう言ってある。
待ちくたびれたデュボワが、迎えに行くべきかと思い始めた時、教会の扉が開く音が聞こえた。細く開いた扉の隙間から、関兵衛が身を滑り込ませるように入ってくる。その後に続いて、小奇麗な青いドレスを身につけたおふうが入ってきた。
デュボワは西洋式のドレスを着る東洋人を初めて見た。一般人で西洋のドレスに袖を通せる者は、今の日本にはそう多くない。
入ってきた二人に向けて、デュボワは声を掛けた。
「やあ、よく来た。こちらに座りなさい」
関兵衛とおふうが、デュボワへと近づいて行く。
デュボワは、祭壇前にある長椅子におふうを座らせた。整然と並べられた椅子も、ヨーロッパにあった物に似せて、日本の大工に作らせた。随分長い椅子なので、初めは大工も当惑していたが、注文どおり、それなりの物を作ってくれた。
初めて来た教会の中を、おふうはきょろきょろと見回している。日本の大工が作ったものであるとはいえ、物珍しい作りである事には違いない。
デュボワは関兵衛に、おふうを連れてきたことに対して礼を言うと、話を始めた。
「来てもらった理由はもうお分かりかと思います。今朝オールトさんのところでお話したことです」
おふう=芭尾は小さく「はい」と答える。
「オールトさんの手前、行ってみては、と薦めましたが、それは私の本意ではないのです」
デュボワは、長椅子に座る芭尾の横に自分も座った。
「あの方は、奥方を亡くされてからずっと独身でいます。ですから、あの方があなたに特別な好意を抱くことは構わないでしょう。――私の言っていることがわかりますか?」
デュボワの問い掛けに芭尾は頷いた。
「ですがあなたは、オールトさんと出会ってから、まだ何日も経っていない。当然、彼の申し出を受け入れるだけの理解はないでしょう。オールトさんがあなたを澳門に連れていくというのは、あなたと特別な関係を持ちたいのだろうということです」
芭尾は黙ったままで聞いている。
「ですがオールトさんは、オランダ商業使節団長です。それは東洋人との婚姻を許される立場ではない。――見下すような物言いをして申し訳ない。ただ、あの方の周囲の者たちが、それを許さないということです」
デュボワが芭尾に対して向き直った。芭尾はまた、無言のまま頷く。
「それでも、と言うのであれば、私はオールトさんに快くあなたの意思を伝えようと思います」
デュボワはじっと芭尾の顔を覗きこんだ。
芭尾は特に考えるふうでもなく、デュボワに向かって口を開いた。
「その、いくつか聞きたいことがあります」
「何でしょう? 私の分かることであればお答えしますよ」
芭尾は祭壇に目を向けた。そこには今朝ほど見たロザリオより、大きな十字架が飾ってある。大人の腕ほどの大きさであろうか。それは、デュボワがフランスから持ってきた、銀製の十字架だ。それにもやはり、磔にされた男が象られている。大きいせいか、より細かい装飾がされていて、手と足に打たれた釘から血が流れている様子も分かる。処刑された死体の像に祈るなど、やはり悪趣味としか思えない。
「イエス・キリストは、本当にいたのでしょうか?」
意外な問いであった。
「もちろんです。主たる父が地上に遣わした神の子です。実際にいたからこそ、我々がこうして存在しているのです」
「イエスは『人』ですか、それとも神なのでしょうか?」
「神は唯一つの存在です。その神たる主が血と肉を持ってイエスを地上に遣わされた。血と肉を持つことが人であることならば、イエスは人でしょう。ですが…」
「細かいことは結構」
芭尾は強い口調で言い放った。急に雰囲気の変わった芭尾にデュボワはたじろぐが、そんなことはお構いなしに、芭尾は話を続ける。
「イエスが人ならば、その血を受けた杯、身を貫いた槍や釘も存在すると言うことなのでしょう?」
「…そうです。確かにそれは存在します。――急にどうしたのです? 一体…」
怪訝そうに訊くデュボワの言葉を遮って、芭尾は問いかけを続ける。
「イエスの血には、全ての罪から開放する力があるのでしょう? ならば、どうすればその力を使えるのです? 血はどうすればその力を発揮するのでしょう?」
デュボワは答えに窮した。まさか、おふうがこのようなことを言ってくるとは思わなかった。今朝の話をどう解釈したのだろうか。あまりに理詰めでイエスの力を解釈しようとする。
黙って考えこむデュボワを、芭尾はじっと見つめている。いつの間にかその視線が、とても冷たいものに変わっていることにデュボワは気付いた。下から睨め付けるように見るその双眸から、ねっとりと絡みつくような不快感が垂れ流される。デュボワは背筋に悪寒を感じて、思わず眼を逸らした。
「……私はそこまで明解な答えを知りません。ただ…」
「ただ…?」
「その様な聖遺物を所有することで、そうした力の恩恵に預かれると言われています」
デュボワの答えを訊いた芭尾は、露骨に大きなため息を漏らした。その変わり様に戸惑うデュボワをあざ笑うかのように、芭尾は口元を上げてにんまりと笑う。その様子に、デュボワは鳥肌が立つほどに寒気を覚えた。
「お前は奇跡があると言いながら、その奇跡の起し方は知らない。杯や槍が存在すると言いながら、それをどうしたらいいのかを知らない。曖昧なことしか知らないくせに、すべて本当だと断言する。肝心なことは漠然とした言葉ではぐらかす。結局、人に伝え聞いたと言って誤魔化しているだけだ」
困惑するデュボワは必死で言葉を返す。
「そ、それは違う! 神は…イエスは…」
思ったように言葉が口から出ていかない。まるで喉が内側から締められるような感覚に、思わず首元を押さえて立ち上がったデュボワは、祭壇の十字架の下へ駆け寄った。
芭尾は元の場所に座ったまま、相変わらず冷たい視線で、デュボワを見つめている。
デュボワはその瞳の奥に、微かに青い光を見た。恐怖で身がすくんだデュボワは、十字架に手を触れて祈りを唱え始める。上手く言葉に出来ないものの、懸命に祈りの言葉を吐き出していく
「貴様には少しは効いた。――ここへ来る前に、腹ごしらえをしたからねぇ」
芭尾が立ち上がると、傍らにいた関兵衛も一緒に立つ。その眼はうつろで、まるで何も見てないかのように宙を見つめたままだ。
「デュボワとか言ったか、試したいことがある」
芭尾の瞳に灯った光が徐々に収まっていく。それに連れて、デュボワは体の自由を取り戻していった。
デュボワは目の前にいる女が尋常でないことを悟った。オールトの変節も、この女のせいに違いない。
まさしくこれは、悪魔の所業だ。この女が悪魔に取り憑かれているか、あるいはこの女が悪魔か。手に触れた祭壇の十字架を両手で持ち上げると、デュボワはそれを芭尾の方へ向けた。
「悪魔め。神とイエス・キリストの前にひれ伏せっ! ――汝を滅ぼさん! いとも汚れし霊よ、すべての悪の力よ、地獄からの濫入者よ………!」
デュボワは祈りの言葉を芭尾にぶつけるように唱える。
「そうだ、それでいい。私に向けて、その十字架とやらを振り回せ」
芭尾は一歩ずつ、デュボワに近づいて行く。
足がすくんで動けないデュボワは、その場にへたり込んでしまった。それを見た芭尾は、関兵衛に何か言う。すると関兵衛が、デュボワの後ろに回りこんで羽交い締めにした。そのまま腰の抜けたデュボワを無理やり立たせる。
デュボワが持つ十字架に、芭尾はそうっと手を触れた。
触れた瞬間、びくっとして一旦手を引いたものの、また手を伸ばす。指先で、かたどられたキリストの頭から胸を撫でていく。
デュボワの十字架を持つ両手は、強く握り続けているせいで真っ白になっている。血の気が引いて蒼白になったデュボワに、芭尾はにんまりと笑った。
間違いない。確かにこの十字架やデュボワの力は自分には通じないのだ。触れば確かに不快な痺れはあるものの、決して耐えられぬほどではない。祈りの言葉は耳障りだが、我慢できぬほどには効かぬ。
「おい、デュボワ、その澳門とやらに、仏を拝む坊さんはいるか?」
祈りの言葉を唱え続けるデュボワは、芭尾の問を無視した。
「澳門には仏法僧はいるかと聞いている」
そう言うやいなや、芭尾は指先でデュボワの肩を突いた。すると、その爪が鋭く伸びて、背中の方まで突き抜ける。デュボワは痛みのあまり悲鳴を上げた。祈りの言葉はそこで止まった。
「答えろ、いるのか?」
「…いる…あそこには仏教の寺があった」
「お前の国はどうだ。ヨーロッパとか言うところにはいるか?」
「いない…私の国には…」
「なら、オールトの国はどうだ? お前のような神父ばかりか?」
「…そうだ」
苦々しい顔でデュボワが答えると、芭尾はゆっくりと肩に刺さった爪を引き抜いて行く。痛みに呻く声を聞きながら、答えに満足した芭尾がにんまりと笑う。
芭尾はデュボワの眉間に指を突き立てた。
「…神よ…」
そう囁いたデュボワは両目を閉じる。
一瞬の内に、芭尾の爪がデュボワを刺し貫いた。