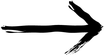※
萬澤宿を飛び出した平二たちは、また丸一日走り通した。今はもうすっかり日が落ちている。
一行は街道を逸れて、山の中を走った。異人であるミケーレ・ラブティが人目につかないようにするためだ。山中を走るなど、ミケーレにはとても無理なので、終始一目が抱えている。
萬澤宿から南へ向えば駿河に出る。そこから東海道を西に行けば大阪、東なら江戸へ辿り着く。平二たちが向かう横浜は、江戸のすぐ手前にある。東海道の神奈川宿を外れてすぐのところだ。
朝から飲まず喰わずで、ずっと走り続けている一行は、太陽の位置を頼りに南東へと進んだ。整備されている街道を行くわけでないので、走っていても思ったほどの距離は進んでいない。
宿場を飛び出して以来、平二たちはほとんど言葉を交わしていない。走っているから話さない訳ではない。一目は元々無口だが、円狐と平二は、お互い話すきっかけが無い。
日がすっかり落ちて暗くなった山中で、円狐は脚を止めた。それに倣って一目も立ち止まる。気付いた平二も、少し先で立ち止まった。
平二と円狐は、互いに視線は合うものの、やはり言葉はない。
「一目、ミケーレを下ろしておやり」
円狐に言われた一目は、両手に抱えていたミケーレを下ろした。萬澤宿で抱えられてから、ずっと同じ姿勢のままだったミケーレは、やっと足が伸ばせたことに安堵した。
横浜を出てからの道中は、籠と馬を乗り継いできた。籠は乗り心地がすこぶる悪く、随分腰を痛めたが、この大男に抱えられているよりはずっとましだった。それに籠であれば、休みたい時は止めればいい。しかしこの大男は、何を言っても返事がない。結局ずっと抱えられたまま、ここまで揺られ通しであった。おかげで、円狐から渡された着物にも着替えられていない。
円狐は袂から包みを取り出すと、平二の目の前に突きつけた。それは、宿場の茶屋で受け取った握り飯の包みだ。以前渡された時と同じく、包みの中身がある。
「喰いな。お前も腹が減っている頃だ」
「……」
平二は無言でそれを受け取った。
「半分はミケーレにおやり。ここには『人』が喰えるものはないから」
平二は、受け取った包みをミケーレに差し出した。
「おい、これ全部喰えよ」
「あなたの分は…?」
「俺はいらない。全部食ってくれ」
包みをミケーレに渡した平二に向かって、円狐が言った。
「……お前、あたしが言ったことを気にしてるのかい?」
「なにが?」
「一緒に行く理由がないって言ったことさ。忘れてないだろう?」
「そうだったな。で、どうする? ここらで別れるか?」
円狐は、ため息を吐いて言った。
「なんだい、ここまで素直に付いてきておいてさ。今更、別々に行ったって、着く場所は一緒じゃないか」
「それで、芭尾を見つけてどうするよ? 俺とあんた、どっちが殺るんだ?」
平二は円狐に向き直った。平二の言葉に、円狐は答えずに黙る。
「あんたも芭尾とは因縁があるんだろうが、これだけは絶対に譲れねえよ」
平二は円狐を睨みつけて言う。円狐も視線を逸らさずに動かない。
睨み合うように相対する平二と円狐の様子に、ミケーレは訳が分からないながらも、黙ってそのやり取りを聞いていた。
しばし押し黙ったままだった円狐が口を開いた。
「…無理さ。妖力の使い方も碌にわからないお前じゃ、返り討ちに合うに決まってる」
「やってみなけりゃ分からんだろ。いざとなったら…」
平二の言葉を遮る様に、円狐が鋭い語気で言った。
「調子に乗るんじゃないよ。仇が討ちたいなら、黙ってあたしらに付いて来るんだ」
「ふんっ、そうかい。――どうしてもあんたが殺ると言うなら、俺はここから一人で行く」
斜に構えた平二の右手が、腰に差した太刀の柄に触れた。
「…勝手にすればいい。別に止めやしない。――でもね、あたしらの邪魔はさせないよ」
そう言う円狐の手には、いつの間にか黙儒が握られている。
「やっぱり、こうなるよな」
円狐は後ろに飛び退いた。鬱蒼と茂る草木の中へ降り立ったはずなのに、物音一つさせない。
平二は、空いた左手で右眼を隠す布を押し上げる。暗い山中に、右眼の赤い光が浮かぶ。
「山ン本の眼で見たからって、あたしに勝てると思うな」
静かに言った円狐は、黙儒の突先を平二に向けた。
その様子を見ていたミケーレの体が宙に浮いた。一目に後ろから抱え上げられたのだ。そのままミケーレを持ち上げた一目は、ゆっくりと後ろへ下がる。
円狐がずいっと前に出ると、一気に間合いを詰めた。黙儒の突っ先が平二の喉元に切迫するも、鞘から抜いた太刀で、平二がそれを払う。そのまま横へ飛んだ平二は、太刀を円狐に向けて振り下ろした。それもまた黙儒の横一線で振り払われる。平二の太刀と黙儒が触れる度に、鈍い打撃音とともに、青白い火花が周りに飛び散った。
ミケーレは、平二と円狐が斬り合う様を離れたところから見ている。宿場で出会った時から普通ではないと思っていたが、今の様子はまったく尋常ではない。丸一日も走り続けた挙句、今度は斬り合いを始めたのだ。その上、平二と名乗った男の片眼は、暗闇の中で赤い光を放っている。
平二の刀を避ける円狐は、幾度か黙儒を振るっただけで、後は距離をとって平二を翻弄している。軽い身のこなしで避ける円狐相手に、空振りを繰り返す平二の太刀筋は、疲れのせいか乱れ始めている。木に囲まれた狭い空間では、太刀の刃が木の幹に当たってしまう。何度か木に当たる内に、食い込んだ刃が抜けなくなってしまった。
枝にぶら下がった太刀を抜こうとにするものの、押しても引いて動かない。
ふと気がつくと、真横に円狐が立っていた。黙儒の突っ先は、平二の喉元を捉えている。
「なんで掛かって来ない、手加減のつもりか?」
「黙儒が当たれば、只じゃ済まないことは知ってるだろう? それに、お前の剣さばきは雑すぎて、あたしに掠りもしない。でも…」
「…?」
「でも、ただの百姓にしては、達者だねぇ」
平二は眼を細めて押し黙った。
「お前、宿場で二人斬り殺したね。――ためらいがなかった」
「うるせえ、黙れよ!」
平二が声を荒げる。
「お前、わかりやすいよ。――殺したこと、悔やんでるんだろう?」
宿場で襲ってきた役人は、芭尾の手に掛かって死んだものと思っていた。しかし死に際のあの顔は、確かに正気だった。あれは、自分がなぜ殺されるのかをわかっていない表情だった。
「あそこで襲ってきた奴ら、蟲に喰われて、死んだも同然だったじゃないか。いや、そうでなくても、やらなきゃ俺が殺されていただろうが!」
「あたしに言い訳してどうする? 慰めて欲しいのかい?」
平二は腰に差した短い方の刀を抜くと円狐に迫った。鋭く突き出されたそれを、身を引いて避けた円狐は、そのまま大きく後ろへ下がった。平二は追わずに、仁王立ちになって円狐を睨みつける。
平二の右眼の光が徐々に増してくる。吹き上がるようにこみ上げてくる感情を抑え切れない。
小さく、低く、呟くように平二は言った。
「……何が言いたい?」
「何も」
怒りの形相を浮かべる平二を前に、円狐は涼やかな表情で静観している。動く様子のない円狐に、平二が少しずつにじり寄っていく。
すると、円狐が口を開いた。
「いや、やっぱり言うわ。お前も芭尾も、人殺しには変わりないね」
強烈な感情が平二の心中に湧き上る。
「……てめえっ!」
平二が円狐に向けて跳んだ。
間合いが詰まるのを嫌った円狐が後ろへ飛び退く。もう同じ轍は踏まない。太秦坊の屋敷では、あっという間に組み伏せられたが、距離を取れば、そう簡単には捕まることはないはずだ。獣の様な速さで襲いかかってくるが、動きが単純なので、避けるのは容易だ。
向かってくる平二に、円狐は一定の間隔を保ちながら下がっていく。
平二は止まらない。皮膚は赤銅色に染まり、右眼は煌々と赤く燃え盛っている。
平二の手が、円狐の喉元へ伸びた。
すれすれで交わした円狐が後ろへ飛び退くと、急に周りの木々が見えなくなった。全身が月明かりの下に出る。足が地に届かない。
崖だ。下の方から水の流れる音が聞こえてくる。
円狐の体が弧を描いて落ちていく。それを追って平二の体も飛んだ。宙で捉えられた円狐は、平二と共に真っ逆さまに沢へと落ちる。
沢の水に浸かった平二の体から、しゅうしゅうと白い水蒸気が立ち上った。右眼の力で、異常なほどに熱くなった平二の体が冷やされていく。赤銅色に染まった皮膚は、徐々に元の肌色に戻っていく。
直ぐに立ち上がった円狐が、ずぶ濡れの平二を見下ろしていた。
「あたしらに、人を喰ったことはあるかと訊いたね」
「……」
「喰ったことなんて無いさ。あたしは『人』が嫌いだと言った。だから、関わるのも嫌だ、見るのも嫌だ、臭くて汚い『人』なんて、喰ったりするものか」
円狐は声を荒げる。
「あたしは『人』を殺したことなんて無い。芭尾とは違うんだ。――なのに、芭尾が『人』を喰ったせいで、あいつがやったことで、あたしがどれだけ卑しまれたと思う? 同じ狐だからと、どれだけ爪弾きにされたか!」
鋭い眼つきで睨みつけたまま、円狐は平二に向かって言葉をぶつけていく。
「ずっと、ずっと、逃げたかった! 山を出ればつらい思いをしなくても済むのに。なのにお前らが、『人』がどんどん増えていくせいで、あたしの逃げる場所までなくなっちまったんだ! ――だから、だから、あたしが芭尾を殺る。誰がなんと言おうと、あたしがやらなきゃ駄目なんだ!」
円狐は叫ぶように言葉を吐き出すと、歯が食い込む程に下唇を噛んだ。何かこみ上げるものを、必死で抑えるように、じっとそのまま下を向いている。
平二の右眼はいつの間にか光を失っていた。もう睨むでなく、じっと円狐を見上げている。感情を剥き出しにした円狐に、すっかり気を削がれてしまった。
物怪はどれほど生きるのだろう。芭尾は五百年も封印されていた。ならば円狐は、あの山にどれだけ長い間縛られていたのだろう。
平二は、ずぶ濡れになった体を起こした。
「俺はどうなったって構わない。だけど、せめて仇討ちぐらいしてやらなきゃ…。そうでもなきゃ、おゆうに顔向けができないんだ」
しんと静まり返った山奥の中では、水が岩の上を流れる音しか聞こえない。しばらく静寂が続いて、円狐がつぶやくように言った。
「……お前も引けないんだよねぇ」
前髪の間から見える円狐の眼が、潤んでいるように見える。平二はそれを見ないように円狐から目を逸らした。なぜか、見てはいけないのだと思った。
ふと視線を上げた平二が円狐に言った。
「早い者勝ちでどうだ? どうせ、どっちも引けないんだ。ただし、お互い邪魔はなしだ」
ややあって、どしんどしん、と足を鳴らして一目が近づいてきた。その脇にはミケーレを抱えている。
「……一目?」
「一緒にやれよ。山ン本はそう言ったろ」
斬り合うのを止めるでもなく、ずっと見ていた一目が喋った。
「せえので合わせて、突き刺せってのか」
平二の言葉に、一目はまたちっと舌を鳴らす。すると、円狐が口を開いた。
「……山ン本は、お前と力を合わせろって言ったんだ。一緒にってのはそう言うことだよ。芭尾の妖力は、人を喰ってどんどん強くなる。あたしらだけじゃ無理だからってさ。お前の右眼は山ン本の眼だ。山ン本が言うには、お前はすこぶる強い妖力が使えるはずだって。――まあ、さっきの様子じゃ見当違いだろうけど」
円狐は、腕組みをして鼻をふんっと鳴らす。
「でも、さっきの早いもの勝ちってのはいいじゃないか」
「なら約束だ。言っておくが邪魔はするなよ」
「しつこいよ。脚を引っ張り合っても仕様が無いことぐらいわかっているさ。むしろ、お前が約束を守れるのかい?」
「破るつもりはねぇよ。あんたみたいに騙せるほど器用じゃない」
「なんだい、口移しの事をまだ根に持ってるのかい?」
そう言って円狐はけらけらと笑う。先ほどまで斬りかかってきたくせに、すっかり気安い口調で話す円狐に、平二は言い返す気まで削がれた。
「それに役人を殺っちまったんだ。あたしらもすぐに追われることになる。早く全部終わらせて、帰らなくちゃいけない。こんな押し問答している場合じゃないんだよ」
そうだ、芭尾を殺した後はどうする。円狐と一目は山へ戻るだろう。だが俺には戻る所がない。また賊になるつもりはない。だが、もうおゆうはいない。――ならば、どうするか。
思いあぐねる平二に構わず、円狐は平二に言った。
「この先から、山を越えた所に箱根の関所とやらがあるはずだ。そこは『人』が通せん坊しているんだろう?」
ぼうっと考え込んでいる平二は答えない。円狐が「おい」と言って気を引くと、平二が顔を向けた。
「平二、聞いてるのかい? 関所だよ。もうすぐのところにある」
円狐の言葉に気付いた平二は「ああ」と短く答えた。先の事を考えても埒があかない。向き直った平二は円狐に言った。
「関所って、箱根のか?」
「そう言ったじゃないか、呆けてるんじゃないよ」
それにしても、円狐は闇雲に走っているのかと思っていた。出発した頃は臭いを追っていたが、今は、もう居留地を目指してまっすぐに走っている。円狐は『人』の作った街道や関所のことなど知らない筈だ。なぜ関所が近いと分かるのだろう。
「どうして分かるんだ? ここいらは初めて来るんだろう?」
平二がそう言うと、円狐は袂からたたんだ紙を取り出した。
「そこの異人がいた部屋にあった物さ、見てごらんよ」
拡げたそれを、月明かりに照らして見る。線と文字がいくつも書き込んである。地図だ。
「学のないお前には無用の長物だろ。書いてある字は知らないが、理解するのは案外容易いもんさ」
見知っている地図とは随分違う。書いてある文字は異国のものだろうか。
平二はふと、暗闇でも存外ものが見えていることに気がついた。右眼は開いたままだ。試しに右眼を閉じてみると、なるほど左眼だけでは全く何も見えない。この眼は闇の中も見通すのか。
そうするとミケーレは、真っ暗闇の中で、何も見えずに怯えているに違いない。 平二は辺りを見回すと、細い体が座っているのを見付けた。平二はその影に向けて声をかける。
「おい、ミケーレさんよ、聞こえるか?」
「ハ、ハイッ!」
ミケーレが素っ頓狂な声を上げた。平二が近づいていくと後ずさるように足を動かすが、腰でも抜けたのか、その場から動けないでいる。胸のあたりに両手を置いて、指先には何かを握っている。それは、木枝らしきものを組み合わせて作った十字架だ。
「そんなに怯えるな。喧嘩は終わったし、話もまとまった。みんな仲良く行くことになった」
「……」
ミケーレは、平二と円狐の言い争う声は聞いていた。内容は理解できる。しかし訳がわからない。日本には食人の習慣は無いはずなのに、人を喰ったとかいう話をしていた。そして追っているはずのおふうの名前でなく、別の名前を連呼していた。
「…芭尾というのは、何デスカ?」
「話してわかることじゃない」
「でも、私も一緒に行くんでショウ? それなら、教えてくだサイ」
平二は円狐のほうを振り返った。話して良いものか、念押しぐらいはしておいたほうがいいだろう。すると円狐が近づいてきて、平二の後ろに立った。
「芭尾ってのは狐の物怪さ。そいつが平二の女房を喰って逃げた。お前が会ったおふうは、平二の女房の皮を被った芭尾なんだよ。そいつはお前も殺そうとしたんだ」
存外あっさりと話したことに驚いている平二を尻目に、円狐は話を続けた。
「芭尾なら瞳術であんたを操ることだってできたろうに、なんであんな回りくどいことをしたのかがわからない。なあお前、芭尾に何もされなかったのかい?」
「ドウジュツって…?」
「ああ、瞳術ってのは、眼を合わせただけで相手を暗示に掛ける術さ。妖力の強い芭尾なら、視線が合えば一瞬で相手を篭絡できるだろうさ。でもお前は暗示にかからず、蟲にも喰われなかった。なんか理由があるんだろう?」
「私は何も。ただ、おふう…芭尾と眼が合った時、とても嫌な気分になりまシタ」
「それだけかい?」
「…ハイ」
円狐は、「ふうん」と言うと、首をかしげて黙ってしまった。平二は待ちきれずに口を開く。
「なあ円狐、一体なんだよ」
「お前さん、宿場でのことを忘れたのかい? あれだけの大人数を、しかも死にかけの『人』を操った芭尾が、このミケーレには碌に手出しをしなかった」
「だから?」
「馬鹿だねぇ。このミケーレは、多分普通とは違うんだよ。瞳術が通じないんだって」
「どうして通じないんだ?」
「だから、さっきから言っているだろう、なんでだか分からないんだよ。――坊さんだとか、そういうのには通じないこともあるけどね」
宿場の茶屋で聞いた話では、異人は切支丹の先生だということだった。ミケーレが胸前で掲げていたのも、確か切支丹の印だ。
「なあミケーレ、あんたは切支丹の坊さんなのか?」
平二が訊くとミケーレは首を縦に振った。
「私は…仏教徒の僧職とは違います。カソリック教会の神父デス」
「なんでもいい。そういうのはよくわからんし。とにかく同じようなものだろう?」
「……違いマス。神の存在は唯一つ。似てもいないし、ましてや同じではナイ」
怯えていたミケーレの声に力が入る。そこへ円狐が口を挟んだ。
「多分ミケーレが、その神父だからなのかもしれない。いずれにしても、芭尾の瞳術が効かないことは確かなようだ。――平二、やっぱりこの異人は、おまえよりずっと役に立つよ」
円狐はそう言って笑った。その口調には、もう刺々しさがない。
「なあ、あんたもその瞳術ってのを使うだろ?」
「まあね。瞳術は妖狐の十八番だから」
「なら、あんたがミケーレに、その瞳術とやらを試したらどうだ?」
「……」
円狐は、平二の提案に黙った。
「どうした?」
「いや、やめておく。さっきお前とやり合って、もうずいぶん妖力を使ったからね、無駄に疲れるのはごめんだよ。大体、芭尾の瞳術が通じないなら、あたしのもまず無理さ」
「そういうもんなのか?」
「そういうもんさ。お前も早く妖力に慣れることだね。瞳術なら、お前の持ってる山ン本の眼だって出来るんだ。――上手く使えば、あたしだってどうにか出来るよ」
そう言って円狐は妖しく笑う。
「お前さ、茶屋で渡した銀貨があったろう?」
「…?」
「出して見てご覧よ」
平二は腰袋に入れた銀貨を探った。茶屋で円狐から受け取った残りをそのまま持っていたはずだ。しかし、取り出して見たそれは、大きさこそ銀貨に似てはいるものの、全て石ころだった。
唖然と石を見つめる平二に、円狐はけらけらと笑いながら言った。
「それが瞳術さ。騙されたくなけりゃ、次は山ン本の眼で確かめるんだね」
確かに、銀貨を受け取った時には右眼を隠していた。と言うことは左眼のほうが騙されていたということか。平二は手の上の石ころをその場に落とすと、円狐に言った。
「関所を通るのも、お前の瞳術でなんとかならんか? いや、この辺りの山ん中だって、役人が見張っているかもしれん」
「できなくないさ。でも、めっぽう疲れるんだ」
「箱根を過ぎてからは、人目を避けて行くのが難しくなる。横浜までの間、辛抱できないか?」
すると円狐は、着物の袂から数枚の紙片を取り出した。そこにはなにか文字が書いてある。
「……どのみち、そうするつもりでいたんだ。ほら」
そう言って、紙片の一枚を平二に手渡した。
「なんだ、こりゃ?」
「呪符さ。山ン本が持たしてくれた。これを使えば、あたしの妖力でもお前たちの姿が見えなくなる。あいにく三つしかないから、お前とミケーレ、それと一目に使ってもらう。――いいから、それをちょっとお貸し」
渡した呪符を平二の手から取り返すと、円狐はそれを、平二の額あたりに貼った。呪符が邪魔で前が見えない。だが外そうと引っ張っても、呪符は張り付いたままで取れなくなった。
「おい、これ取れないじゃないか」
「そうだよ、あたしの妖力が効いているうちは、その呪符は剥がれないんだ。その代わり、『人』がおまえらを見ても見えなくなる」
見ても見えないとはどういう事か? 平二は呪符を貼りつけたままで、ミケーレのほうへ向いた。
「ミケーレさん、あんた、俺が見えるかい?」
平二が訊くと、ミケーレは目を瞬かせながら答えた。
「いえ…あの、見えますけど、でも、よく見えナイデス」
ミケーレは平二の方を向いているが、眼の焦点が合っていないかのように、ぼんやり宙を眺めている。
「やっぱりこの異人には、妖力ですることが効きにくいみたいだね。普通なら、声を出したって、姿かたちは見えないはずさ」
「暗くて見えないだけじゃないのか? 大体、こんな紙切れ一枚で姿が見えなくなるなんて…」
円狐は鼻をふんっと鳴らすと、平二の額に貼った呪符を剥ぎとった。ついでに毛も数本引っこ抜く。
「痛ってぇ! 何すんだ」
「おや、ごめんよ」
額を押さえて痛がる平二を見て、円狐は声を出して笑った。
「この呪符はちゃあんと使えるから安心おしよ。それより疑うとご利益がなくなっちまうよ」
平二は、一目よろしく円狐に聞こえるように舌打ちをすると、なにか思いついたように顔を上げる。すると、呪符をひらひらさせている円狐に向けて言った。
「それならミケーレに貼って試してくれよ。俺の左眼で見えなければ使えるってことだろう?」
「なんだい、お前も疑い深いねぇ」
円狐はミケーレへ近づくと、呪符を持った手を伸ばす。するとミケーレは、勢いよく飛び退いた。
「ヤメテ! そのような邪教のものを差し向けないでくだサイ!」
「邪教って、おまえさん、大げさだねぇ」
「私は神の僕デス、邪教のまじないに身を委ねることなどできマセン!」
ミケーレは手に持った十字架を円狐の目の前にかざした。木の枝と布切れで作った十字架だ。
「なんだい、そりゃ?」
円狐は呪符を引っ込めると、空いた手で十字架に触れた。
すると何かを感じたのか、素早く手を引く。しかしまた手を伸ばして、今度は慎重に十字架に触れた。触るとほんの少し痺れるような痛みがあるものの、我慢出来ないほどではない。
「不思議だね、ただの棒っきれなのに。触ったらちょっとぴりぴりするよ。――一目も試してご覧よ」
言われた一目は動かない。また、ちっと舌打ちをしただけだ。
不思議そうに十字架を撫でている円狐の姿に、ミケーレは思わず見蕩れてしまった。月明かりでぼんやりと見える円狐の表情は凛としているが穏やかで、その美しい顔立ちは気品に溢れている。今まで出会った日本人の中には、これほど優美な女性はいなかった。
ぼうっと見つめているミケーレに、円狐が言った。
「お前、これは切支丹の法具みたいなものかい?」
「ホウグ…これは十字架デス」
「ふうん、あたしが触っても大丈夫ってことは、これは、物怪には効かないのかねぇ」
「モノノケ…」
「そう、さっき教えてやったろう? 芭尾は物怪、あたしと一目も物怪さ」
物怪というのが日本の民話に出てくる悪魔や魔物を指す言葉ということは知っている。日本の風俗や文化に関して知るために、教会で働く日本人たちから教えてもらったのだ。彼らが話す伝承や昔話は多岐に渡り、道徳的なものも多い。また話に出てくる悪魔や魔物など、畏怖する存在が多種多様であることも興味深かった。
芭尾という物怪を追っているという話も、文化水準の低い日本人が盲信したためかと思った。
しかし、目の前にいる女性は、自分がその物怪だと言っている。ミケーレは思わず「まさか」と言葉を漏らした。
「……お前が信じたくないなら、それでいいさ。でも、後で呪符は貼ってもらうからね」
確かに、丸一日山の中を走っていながら、涼しい顔をしているのは常識を逸している。日本には長距離を走って荷を運ぶ、ヒキャクという職業があるらしいが、それにしても一目という男は、大の大人である自分を抱えて、ここまで来たのだ。
その時、誰かがミケーレの肩を叩いた。振り向くと、一目が見下ろしている。全く疲れた様子のない一目の姿が、月明かりでぼんやりと見えている。
この男も非常識なほどの巨体だ。五・六フィート(約一七〇センチ)程のミケーレと比べると、頭三つ分は大きい。
一目はミケーレと眼があうと、太い芋虫のような指で自分の鼻の頭を指差した。ミケーレがその様子を凝視すると、一目は手の平を拡げて顔を隠す。
その手がゆっくりと下がると、一目の眼と鼻がなくなっていた。
衝撃的な光景に、ミケーレは絶句した。眼をそむけようとするものの、恐怖で身がすくんで瞼さえ閉じられない。
身動き一つしないミケーレをよそに、一目の口がにんまりと笑うと、顔の中心が横へ割けるように開く。眼玉一つと分厚い唇だけしかない奇異な顔が現れた。
その一つ目と視線が合った瞬間、ミケーレは意識を失った。