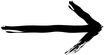四、妄執
横浜に辿り着いた芭尾は、オランダから来た商人であるヨハン・オールトの屋敷に居座った。齢五十程のオールトには妻がいない。長らく続いた外国での暮らしの間に、病で死んだらしい。子供もいないらしく、屋敷には日本人の召使が数人いるだけであった。
屋敷の中は見たことのない作りであった。板張りの床の上には、絨毯という厚く模様が縫い込まれた布が敷かれている。細かい細工がされた調度品が所狭しと家具の上に並び、油を塗ったように輝いていた。屋敷の中では下足のままで歩きまわり、床の上に座らなくていいように、椅子が屋敷のあちこちに置かれている。
その屋敷で芭尾は、オールトとテーブルを挟んで食事をしている。窓の外は、既に日が落ちて暗い。真っ白い皿の上には、黒く焼かれた肉が載っている。それは鹿の肉だというが、火を通してあるものを食べる気がしない。腹ごしらえなら、もう先の宿場町で済ませた。
料理に手を付けない芭尾にオールトが何か言うと、それを多少言葉がわかるらしい日本人の召使が日本語で伝えてくる。食事が気に入らないのなら、別のものを用意すると言っているらしい。
街道で自分を助けたのが異人であったことには面を喰らったが、思いのほか事は順調に進んだ。
宿場町で役人に引き渡される前に、相馬長次郎という男に瞳術をかけた。番所にいた役人も幻惑した。いずれも視線を合わせただけで、すぐに言いなりになった。
問題は二人の異人だった。言葉の通じない相手では、瞳術で幻惑しても、言うことを聞かせて従わせることができない。
瞳術は相手の心を覗き、見透かして、その者が持つ拠り所や執着などを別の何かに置き換える、あるいは別の方向へ向けさせることで相手の心を支配する。相手の持つ偏執が強ければ強いほどに、術は掛かりやすい。しかし言葉がわからないのでは、心の内が覗けても何が何やら理解ができぬ。それを弄ることができないのだ。 いっそ殺してしまう事も考えたが、こいつには性的な欲求、根源的な欲望を瞳術で刺激して、たらし込むことにした。
オールトはすぐに『人』の姿をした芭尾にのぼせ上がった。しかし、もう一人は全くなびかない。視線が合ってもその心が読めぬ。異人だからというわけでない。なにかの壁に阻まれるかのように、もう一人の男、ミケーレ・ラブティには芭尾の瞳術が効かなかったのだ。
先を急ぐ芭尾には、時間をかけてミケーレを篭絡している暇はなかった。なので、役人の一人を殺して肝を抜き、それを絞って作った巫蟲をミケーレの食事に盛った。
それでもミケーレは、気を失って寝込んだだけだった。巫蟲でさえも思ったように効かない。とはいえ動けなくするまでにはできたので、そのまま捨て置いて横浜まで来たのだった。
食の進まぬ芭尾を見て、心配そうにオールトが声を掛けた。その言葉を、いちいち召使が言葉を置き換えて伝えに来る。何か欲しいものはと訊いてくるが、別に何もない。年老いた男のオールトからなど、眼玉であっても欲しいと思わない。
そのうちオールトは、通訳をする召使に怒鳴り始めた。彼の伝え方が悪いと思っているのだろう。まあ八つ当たりだ。芭尾にたらしこまれたオールトは、決してまともな状態でない。芭尾と視線を合わせる度に、まるで阿片を吸ったかのような陶酔感と高揚感を味あわされているのだ。常に興奮状態にあるオールトは、帰ってきてからは、人が変わったかのようであろう。
身振りを付けて怒鳴り散らすオールトの様子を、芭尾は冷淡な視線で眺めている。この男の屋敷に匿われていれば当面は安心だ。
太秦坊はきっと追手を寄越しているはずだ。だが、太秦坊自身は追っては来ない、奴は、物怪の山を納める主だ。一歩でも山の外に出る事はない。ならば誰が来るか。いずれにしても、この『人』の皮を被った姿を知るのは太秦坊だけだ。他にこの姿を知る者はもういない。臭いもそろそろ消える。如何に鼻の利く物怪であろうと、もう臭いで追ってくることはできないだろう。しかも、ここは外国人の居留地だ。『人』が作った垣根と境界が、芭尾を追手から遠ざけてくれる。あと数日安泰なら、逃げ切ったも同然だ。
熱のこもった声で雄弁に召使を叱りつけるオールトをよそに、芭尾は席を立った。用意されている寝室へと向かう。それを見たオールトが声を掛けるが、当然返事など返さない。
芭尾が部屋から出ると、オールトの叫び声とともに、召使が何度も殴られる音が響きわたった。
※
次の日の朝、寝室にいた芭尾の元へ昨晩の召使がやってきた。
小奇麗ではあるが、粗末な仕事着に身を包んだ男の顔は腫れ上がっている。ここまでされて、逃げもせずにまだ甲斐甲斐しくオールトの屋敷にいるなど、全く理解ができない。この男こそ、なにか暗示にでもかけられているのでなかろうか。果たして狂ったオールトに対して、何か恩義でもあるのか。弱みでも握られているのか。
居間に通された芭尾を、オールトともう一人の男が迎えた。窮屈そうな黒い服に身を包んだ男が芭尾を見て近づいて来る。髪は薄く髭は濃い。オールトと同じくらいの年齢だろうか。
「あなたが、おふうさんですか?」
男は流暢な日本語で話しかけてきた。芭尾が「はい」と答えると、男は言葉を続ける。
「私はロベール・デュボワと言います。この居留地で教会の神父をしています」
たしか神父というのは、術の効かなかったミケーレ・ラブティとか言う男と同じ、切支丹の坊主のことだ。一体何の用なのか、正体が露呈したのでないだろうが、面倒には違いない。
「ここにいるオールトさんが、元気のないあなたを心配して私を呼んだのです」
色惚けじじいが気を回して呼んだのだ。余計なことをする。
「神父さまといえば、ミケーレ・ラブティ様と同じでしょう? あの方は、もうお戻りになったのでしょうか?」
芭尾は素知らぬふりで訊く。あの男が戻れるはずがない。もう死んでいるはずだ。
「ラブティ神父なら、昨日すぐお医者様とお役人が迎えに行きましたよ。無事だと良いのですが…」
そう言いながらデュボワは、芭尾に座るよう、手で促した。そこへ先ほどの召使が、カップに入った紅茶を持ってきた。この屋敷に着いてから、同じものを何度か出されている。芭尾はこの茶の臭いに不快感を覚えた。それは『人』にとっては香しいのであろうが、物怪の芭尾にとっては、腐った葉の煮汁としか思えない。
「オールトさんは、あなたが大変な苦労をされてここまで来たと言われていました。あなたがまだ、襲われた時の心の傷が癒えていないのではないかと心配しています。言葉が通じないので、是非にあなたと話して欲しいと。――どうでしょう、なにか心配事があれば、私に話してみませんか?」
デュボワはそう言って笑みを浮かべた。笑うと髭で隠れた顔に、強く皺が寄るのがわかる。
芭尾はデュボワの顔をまじまじと見る。珍しそうに、愛想よく微笑みながら。だが実際には、目の前の男の存在を苦々しく感じていた。心配事など、太秦坊の追手から逃げきれるかどうかだけだ。異国からきた坊さんに話すことなどない。
「いえ、心配事など…」
「そうですか。でも…」
何か言いにくそうにデュボワは咳払いをする。紅茶の入ったカップを口につけて、軽く一口啜ると、意を決したように口を開いた。
「…聞けば、衣服を全て奪われて道端に捨て置かれたとか。――それは女性にとって、大変残酷な仕打ちでしょう。もちろん言いたくないことは言わなくていいのです。ただ私は、あなたの力になれればと思っています」
デュボワは、着物を奪われてから起こったであろうことを暗に言っているのだ。
芭尾が黙っていると、デュボワは胸元から、銀色の飾りのついた首飾りを取り出して。テーブルに置いた。それの首紐は数珠のようになっていて、飾りの部分には、細かい装飾がされている。
「これはロザリオと言って、私たちカソリック信徒が神に祈りを捧げるために持つものです」
「…?」
数珠状の首飾りについた十字の装飾には、その形に沿って両腕を広げる男性の像が彫り刻まれている。十字は磔台だ。よく磨きこまれているのか、きらびやかに輝いている。磔にされた男の姿に祈るとは、なんと酔狂な風習であろうか。
デュボワはロザリオを持ち上げて、芭尾の手の平に置こうとする。しかし、芭尾が咄嗟に腕を引いた。
行き場を失くしたデュボワの手が宙で止まる。
「怖くないですから、手にとってよくご覧なさい。これがイエス・キリストです」
芭尾の手を取ったデュボワは、その手にロザリオを置こうとする。
芭尾は全身をこわばらせた。過去に追い込められた時のことを思い出したのだ。あの時、僧侶たちが持っていた法具に触れただけで、皮膚は弾けて焼けただれた。今、目の前にあるものが異国の法具なのであれば、自分の身に何かあるやも知れぬ。
身を固くして構える芭尾に、デュボワはにっこりと微笑んだ。
芭尾はどうするか迷った。今ここで、オールトやデュボワを殺すことは容易い。だがここに長居することができなくなる。
さあ、どうするか。
「そう緊張しないで、さあ」
デュボワの持ったロザリオが、芭尾の手の平に触れた。
――何もない。
手に乗ったロザリオから、痺れるような痛みを感じるものの、我慢が出来ないわけでない。デュボワが手を離すとその重みが感じられた。ずっしりとした存在感とともに、金属の冷たさが感じられる。手の平から落ちそうになるロザリオを、芭尾は慌てて握る。
思ったより張り合いのない結末にあっけにとられた。ミケーレ・ラブティに自分の瞳術が効かないのも、相手が異人とはいえ僧の類だからと思っていた。しかしどうもそうではないらしい。この異人の持つ法具もまた、自分には効かぬ。
「おふうさん、あなたはイエス・キリストの名を聞いたことは?」
呆けたようにロザリオに目を落とす芭尾に、デュボワが声を掛けた。自分が呼ばれたことにも気付かず、ぼうっとする芭尾に、デュボワは言葉を続ける。
「神である主がその御子を地上に遣わされた。それがイエス・キリストです」
の声に芭尾は顔を上げた。
「…神が御子を遣わされたのは、世を裁くためでなく、御子によって世が救われるためです。イエスはその生涯を通して数々の奇跡を起こし、人々に救いをもたらしました。――その救いの手は、今あなたにも差し伸べられているのです」
芭尾は口元に笑みを浮かべた。それを見たデュボワが頷いて応える。
なんと滑稽なことか。腹の底から笑いがこみ上げてくる。なにが「救い」だ。物怪が『人』の神なるものに救われる道理があるものか。
「私には…、よくわかりません。でも、ご心配には及びませんから」
芭尾は、ロザリオについた十字架を見ながら言う。なんとか、このくだらない話が早く終わらぬものか。そう芭尾が思うのとは裏腹に、デュボワの声色には熱が籠る。
「御覧なさい、その十字架にあるイエス・キリストの御姿を。――磔にされ、そして処刑されたイエスは、その血によって、この世のあらゆる罪に許しを与えたのです」
「あの、――わたしも伺って良いでしょうか?」
先ほど紅茶を持ってきてから、ずっと傍らで立っていた召使の男が声を上げた。
「ああ、関兵衛さん。もちろんですとも」
関兵衛と呼ばれた召使の男に、デュボワは快く答えた。それを見たオールトは露骨に渋い顔をする。皆が日本語で話している中で、自分だけが会話を理解していないことが気に入らないのだ。
「血で許すというのは、どういうことなのでしょうか?」
「イエスの処刑は、心ない人々の策略でした。しかしイエスは、その運命を甘んじて受け入れるのです。そして、世にある罪を自らが流す血潮で洗い流されました。――簡単に言えば、世にある全ての罪に対する罰を、その御身に受け入れることで、イエスは人々に許しと救いをお与えになられた」
関兵衛はどうにも理解し難いのか、眉をひそめつつ頷いている。
「無論、イエスの力を持ってすれば、やましい者たちの策略などは退けることができたのです。でもそれをしなかった。関兵衛さん、それが自己犠牲というものです」
「どうやら、私には難し過ぎるようです」
関兵衛が答えると、デュボワが立ち上がって大袈裟に言う。
「そんなことはない、あなたはまだ、洗礼を受けて間もない。信仰の道を踏み出したばかりではないですか。大切なのは、理解することでなく信じることです」
「信じる…ですか?」
「そう、全てはそこから始まるのですから」
関兵衛が「はい」と言いつつ、恭しく頭を下げると、デュボワはまた席に着いた。
芭尾は、デュボワの話に幾分か興味を持ち始めた。芭尾が知る神仏の類とは、少々有り様が違う。
「それは、本当なのですか…?」
ずっと黙っていた芭尾が口を開いたことで、デュボワは驚きながらも嬉しそうに答えた。
「そう、本当です。実際に、イエスの血を受けた聖杯も、イエスを刺し貫いたという聖槍も存在し、今もヨーロッパの教会で聖遺物として大切に保管されています。イエス・キリストが去った今でも、その奇跡はこの地上にあるのです」
デュボワの話が途切れたところで、オールトが声を掛けた。何かを訴えている。すると、デュボワが芭尾に向き直った。
「申し訳ない、つい話が逸れてしまった。――実はオールトさんから、あなたに伝えたいことがあるのです。彼は日本語がわかりませんから、私があなたにお話します」
芭尾は首を傾げて、デュボワの言葉に無言で応えた。オールトは、その様子をいささか上気した面持ちで見守っている。
「オールトさんは日本での仕事を終えて、近く澳門へ行く予定です。この横浜から船で一週間程度の所にある場所なのですが。――是非、あなたにも一緒に来て欲しいと、オールトさんは言っています」
突然の申し出に、芭尾は面喰らった。たぶらかしたはいいが、言葉がわからないせいで、オールトを操れてはいない。のぼせ上がっていても、自分の意思で行動している。しかしまさか、惚れた勢いで海の向こうまで連れ出そうとするとは思わなかった。
驚いている様子の芭尾に向けて、デュボワは言葉を続ける。
「オールトさんの商船団は、澳門を拠点に商売相手の国々と交易路を結んでいます。ですから、もちろん澳門からまた横浜へ戻ってくることはできます。あなたさえ良ければ、なのですが」
果たしてこれは好機なのか。異国の地まで逃げる必要があるか。
暫く考えあぐねた芭尾は口を開いた。
「いつ頃、横浜を発つのでしょう?」
「出発は二日後です。幕府の許しを得ている時間はないでしょう。でも、オールトさんといれば、行った先でも安心です。彼は澳門での仕事を終えたら、責任を持って日本へ返すと言っています」
オールトは、デュボワが話すことを雰囲気で察したのか、芭尾の顔を覗きこむようにして、笑顔で頷いた。
この色惚けは、自分を国外に連れ出すことで、情婦として囲い込むつもりなのだ。国を出れば頼る相手はオールト以外にいなくなる。そうすれば、必然的に深い関係を結べると踏んでいる。頭はいかれても、こういうことには知恵が回るらしい。どうせ日本へ返すつもりもないのだろう。
「あまり時間はありませんが、ゆっくりと考えてみてください。――そうだ、もしよかったら、後で私の教会に来なさい。そこで外国のお話を聞かせましょう。場所は、関兵衛さんが知っています」
後ろで立って話しを聞いていた関兵衛が、小さく「はい」と返事をする。デュボワは暫く、オールトと異国の言葉で会話をした。話した内容を聞かせているのだろうか、オールトは何度か頷くと、デュボワの手を両手で包むように握った。礼でも言っているのだろう。
「ところで関兵衛さん、その顔は一体どうしたのです?」
オールトと話を終えたデュボワは、顔を腫らせた関兵衛に向かって言った。先ほどまでの明るい口調とは違い、押さえた低い声色で話しかける。声を掛けられた関兵衛は、慌てたように「あのっ…」と短く言うと黙ってしまった。オールトの手前、口をつぐんだのだ。これでは誰に殴られたのか察しがついてしまう。
「言いたくなければいいのですが。何か変わったことがあるのなら、私に相談しなさい」
そう早口で言ったデュボワは、オールトに一礼すると部屋を出て行った。関兵衛も、デュボワを玄関先まで見送るために続いて部屋を出る。デュボワは、オールトの変質に気付いたのだろうか。
二人が出ていった部屋で、オールトは相変わらず、にやにやしながら、芭尾を見つめている。伝えるべきことが伝わった今、オールトは返事を待つだけだ。
芭尾は立ち上がって、テーブルの向こう側に座るオールトに近づいた。何を期待するのか、オールトは椅子を引いて、テーブルを回りこんでくる芭尾の方を向く。
芭尾はその場で立ち止まってオールトに相対すると、その場で着ている服を脱ぎ始めた。この屋敷で与えられた服は着物と違ってずっと軽く、頭から被るように着る。今着ているのは襦袢のようなものだろうか、薄手のそれは白くて透けている。
手早くそれを脱ぐと、一糸まとわぬ姿でオールトの前に立った。白く染み一つない肌に、オールトが見蕩れている。乳房は桜色の乳輪で飾られ、贅肉のない体はゆるやかな丸い曲線を描く。
オールトは目を丸くして、薄い陰毛に隠された局部を凝視している。だらしなく開かれた口元から、今にもよだれが垂れてきそうだ。
芭尾は自分の体をあちこち見回した。取って付けた『人』の皮だが、うまく馴染んできている。関節の辺りに幾分皺が寄ったものの、気になる程ではない。
芭尾の双眸に、青い光がぼうっと灯った。
裸の芭尾に手を伸ばそうとしていたオールトに、芭尾が「おい」と声をかけると、その顔が上がった。芭尾の双眸と視線が合うと、オールトの動きが止まる。前のめりに両手を伸ばしたオールトは動かないまま、芭尾の視線から目を離せない。
暫くそのままでいると、徐々にオールトの息が荒くなってきた。肩が上下するほどに息が荒くなった頃、オールトのズボンの前が、はちきれんばかりに大きくなった。その股間の物を何かに擦りつけるように、オールトは小刻みに腰を振り始める。前後に揺れる椅子が軋む。動きが大きくなって椅子から転げたオールトは、その場で俯せになった。それでも腰を振る動きは止まらない。床に激しく腰を擦り付けるオールトを、芭尾が冷めた眼で見下ろしている。
「オウッゥ」と呻くように叫ぶと、オールトは動きを止めた。切なそうな顔で体を痙攣させている。
芭尾はこの屋敷に来てから、こうして何度もオールトを骨抜きにした。手で触れずとも、勝手に腰を振らせて射精させる。この老体には少々堪えるだろうが、どうせ死んでも喰うわけでないから構わない。こうしてオールトは、射精する快感を重ねるごとに、芭尾への依存を深くしていく。
言葉さえわかれば、一緒にいた長次郎のように瞳術で幻惑し、言って聞かせて従わせることもできるのだが、この異人には、今はこんな方法しかない。いずれ言葉を多少なりとも覚えれば、意のままに操ることもできるだろう。
芭尾は、脱いだ服を取り上げて頭から被った。存外この服が気に入っている。着物に比べればずっと動きやすい。他にも与えられた服は、どれも着物よりずっと楽な代物だ。こうしたものに溢れる異国への興味はある。もともと狐の物怪、妖狐と呼ばれるものは、海の向こうから日本に渡ってきたのだという。ならばこの自分が、また更に遠くへ行くのも、なんら不可思議なことはない。
芭尾が思案を巡らせる間も、オールトはまだ股間のものを床に擦り付けている。芭尾はそれを一瞥することもなく、居間を後にした。