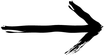※
平二が目を覚ました時、最初に視界に飛び込んできたのは大きな木製の扉だった。
平二をおぶった一目が、閉じられた居留地の門扉に向かって体当たりをしたところだ。すさまじい衝撃と音で目を覚ました平二は、思わず「うおっ」と声を上げて体を起こす。一目の背中に乗っているので目線が高い。周囲を見回すと、家屋の屋根越しに火の手が上がっているのが見える。しかも一カ所だけでない。あちらこちらに火勢がある。見下ろすと、周りは大勢の人に取り囲まれていた。
「イチさん、もう一丁! あと少しで門が倒れるぞ!」
仁八の声だ。それに気づいた平二が振り向くと、仁八とタケが、大きな荷物を抱えて立っている。
「おお、目が覚めたかい。良かったねぇ」
タケが、胸をなで下ろすようなしぐさを見せた。
まだ状況がわからないが、火事から逃げているのだというはわかった。しかし、なぜこうも一カ所に人が集まっているのだろう。平二は一目の背を叩いて言った
「一目、下ろしてくれよ」
すると、尻の辺りを支えていた太い腕がなくなって、平二は一目の背からずり落ちた。地面に降り立った平二は、自分が着物を着ていないことに気づいた。上半身には袈裟懸けにさらしが巻かれており、下は褌しか着ていない。寒空で裸同然の平二に、一目が長いものを差し出した。太秦坊がくれた太刀だ。よほど持っているのが嫌だったのか、一目はそれを摘むようにしている。
平二は太刀を一目から受け取ると、仁八に声をかけた。
「一体何で、みんな逃げないんだ? こんなに集まったら逃げられないだろ」
「それが逃げようにも、あちこちから火が上がってて逃げ場がねえんだ。みんなここに集まって来ちまった。――それにしてもお前さん、あれだけ斬られて、なんでそんなにぴんぴんしてるんだ?」
「俺のことはいい。――それで、どうするんだよ?」
「居留地には、まだ火の手がないんだ。だからそっちへ逃げるのに、イチさんが門を倒しているとこさ」
どしーんと大きな音がする。一目が門に体当たりしているのだ。平二たちが長次郎に出くわした門だ。そこを開いて居留地へ逃げようと、大勢の人間が一カ所に集まってきている。一目の体当たりで、それを支える柱ごと門が揺れると、周囲から大きな歓声が沸いた。
両手が空いた一目は、既に大きく傾いている門を目一杯に押す。めりめりと音を立てて柱が折れていく。そのまま倒れかけた門を太い足で押さえつけると、一気に押し倒した。
門の片側が倒れて向こう側が見えた。さほど広くない運河に橋が架かっている。橋の向こうが居留地だ。幾人かの男が、倒れた門の上を脱兎のごとく駆け上がると、協力してもう片方を開く。開け放たれた門に人々が殺到した。
「ひゃあっ」とタケが悲鳴を上げた。出遅れた仁八とタケは、なだれ込む人の波で端へ追いやられてしまう。すると二人の体がすうっと持ち上がった。一目が二人を抱え上げたのだ。
「おお、イチさん、助かったよ」
右手に抱えられた仁八が言うと、一目はにんまりと笑顔を見せた。
「一目」と平二が声をかけた。押し寄せた人を避けて、いつの間にか門の脇にあった家の庇の上に立っている。
「すまんが、仁八とタケを頼む。――俺は相手をしなきゃならない奴がいる」
平二は倒れた門の先にある、橋のたもとを見ている。逃げる人々を避けるように立っている男が一人。役人の風体だが、上半身裸で腹にはさらしを巻いている。その男もまた、じっと平二の方を見ている。平二を斬った、相馬長次郎がそこにいる。
一目は平二が見ている方へ顔を向けた。庇の上で屈んでいる平二と目線の高さが大して変わらない。
「先に行ってくれ。俺があの役人を引き受ける」
長次郎は、タケや平二の顔を知っている。そして今、既に平二は見つかった。ここで平二たちが来るのを待ち受けていたのだろう。このまますんなりと、橋の向こうへ行かせてくれるとは思えない。
立ち上がると、平二は屋根伝いに長次郎のいる方へ走り出した。平二に合わせて、長次郎も移動する。平二が人々の方から離れるように横へ移動していくと、長次郎も付いてくる。
平二は軽々と屋根から屋根へと飛び移っていく。足取りは軽いが、斬られた背中の傷が、突っ張るようでまだ動きにくい。
斬られた時のことは覚えている。体の中を刃が通り抜けて行くのを感じたほどだ。相当に深く斬られたはずである。今こうして動けるのは、芭尾に裂かれた腹の時のように、傷を塞いでもらったからだろう。はっきりとは覚えていない。しかしまどろむ意識の中で、暖かい手の温もりを感じた。その感触は、まだ傷の上に残っている。
平二は、長次郎へ近づいていくにつれて、速度をぐんぐんと上げていく。平二の耳に、風を切る音と逃げ惑う人々の怒号が混じって聞こえてくる。
ついに長次郎の目の前まで迫ると、屋根の縁を蹴って下方に飛んだ。すでに抜いている太刀の突先を真下に向ける。太刀がまっすぐ長次郎に向けて落ちていくと、長次郎はすんでの所で身を引いた。地面に降り立った平二も、その場に止まらずに、すぐ飛び退く。
長次郎の抜刀術は見ている。距離、威力、速さ、どれも群を抜いている。長い間に積み重ねた訓練の賜であろう。
平二は右眼を覆っていた布を押し上げて、長次郎を両目で見据えた。平二には、もう油断はない。円狐の言った通り、峰打ちでやり過ごせる相手ではないのだ。
「あんた、長次郎っていうんだろう?」
長次郎は刀の柄に手をかけたまま、じっと動かない。平二の右眼には、長次郎の瞳の奥にある、青い光が見えている。芭尾の瞳術で操られているのだ。
「芭尾はどこにいる?」
平二の言葉に答えない長次郎は、足をすうっと前に出す。袴で足下は見えないが、その足さばきは素早い。
あっという間に自分の間合いまで詰めてくると、長次郎が刀を抜いた。その突先が、ほんの一瞬で平二の喉元あたりへ届くと、すぐさまその軌跡を反転させる。長次郎の初撃に反応した平二は、もう元の場所にはいない。ゆるりと刀を鞘に収めた長次郎は、また構えの姿勢に戻る。
無闇に出ても避けられることを悟ったか、長次郎は、そのままじっと相手が動くのを待つ。橋はまだ人でごった返し、皆、我先にと橋へ殺到していく。
平二は右眼で長次郎を見た。その双眸の光を見て平二は気付く。先に見たときより、眼の光が暗く濁り、明滅を繰り返している。そして刀を構えた姿勢も、心なしかぎこちない。
「俺の言うことはわかるだろう? あんた、操られているんだ」
問いかけに、長次郎が眉を動かす。それを平二は見逃さなかった。
「化け狐に付き合って、俺たちが殺し合いをする必要はないだろ」
長次郎は、構えた姿勢のままで言った。
「……わかっている。しかし、自分ではどうにもならない」
長次郎の声は、嗄れていて聞き取りにくい。まるで独り言のように呟いている。
脇腹を抉られてから、漫然としながらも、自我を取り戻していた。だが巫蟲を体内に入れられたことで、長次郎は完全に芭尾の支配下に落ちた。はらわたを喰われ、中身が巫蟲に入れ替わっていくにつれて、痛みは消え、体の自由が奪われていく。まるで、自分の中に芭尾がいるようだ。自我があるにも関わらず、自分の意思とは裏腹に、芭尾の命令を死守しようとしている。
己を取り戻してからは地獄だった。心血注いで磨いた剣術で、罪のない人を斬り殺してしまった。怒りと後悔で気が狂いそうになる。
長次郎は人を斬ったことはない。戦のない世にあって、人を斬る機会は滅多にない。それが気づいてみれば、一晩で三人も斬っていた。挙げ句に言われるがまま、街へ火を放った。いくら操られていたとはいえ、自分が罪を犯したことには変わりない。
「貴様、名は?」
長次郎が訊いた。構えの姿勢は崩さない。
「平二だ。名字はねぇよ」
「そうか――平二よ、私の近くに来るな」
「…?」
「来れば斬る。そのまま後ろを向いて逃げろ」
そう言いつつも、構えた姿勢のまま、長次郎はじりじりと平二に詰め寄ってくる。
「俺が逃げたらどうする?」
「追う。追って殺す。中年の女も、ミケーレも殺す」
「ならここで、あんたの相手をしなきゃならんな」
動きを止めない長次郎に合わせて、平二はゆっくりと後ろに下がる。平二が下げた足に、転がっていた桶が当たった。こんっと軽い音が足元から響く。
瞬間、長次郎が一気に間合いを詰めた。繰り出された刀が、平二に向かってまっすぐに伸びてくる。間に合わないと悟った平二は、上体を反らし、思い切って後ろへ倒れた。仰向けになった平二に向けて、長次郎が刀を振り下ろす。平二は太刀の腹でそれを受けた。
鋭い一撃が、甲高い金属音を立てて、平二の太刀を打ち付ける。
平二は衝撃で腕が痺れるのに耐えながら、上から刀を押し込んでくる長次郎を押し返す。しかし、全体重を乗せている長次郎はびくとも動かない。むしろ刀はじりじりと近づいてくる。
「…平二よ、頼まれてくれ」
見下ろす様に覆い被さった長次郎が、絞り出すような声で言った。
「俺を――俺を殺せ」
そう言いながらも、長次郎の力は緩むことがない。
なんと因果なものか。もう殺生はしたくないとなると、殺してくれと懇願される。
しかし請われたからといって、はいそうですかと簡単に応じてやれる状況ではない。長次郎は言葉とは裏腹に、平二を斬り殺そうと、持てる力を全部込めて襲い掛かってくる。
必死の形相で見下ろす長次郎の眼の奥には、青い光が揺らめいている。それは芭尾の眼が湛えていたのと同じ光だ。畏怖さえ感じさせるその冷酷な光を、今の平二は冷静に見ることができた。ゆらゆらと瞳の奥で閃く光は、時折、明滅したように輝きを失う。光の消えた長次郎の眼は、まるで死人のようにどんよりと濁っている。
長次郎の脇腹から、滴るように血が流れ落ちる。平二の右眼には、その血に混じって落ちていく黒い蚯蚓のようなものが見える。芭尾の巫蟲だ。巻かれたさらし布の間から、ぼとり、ぼとり、と地面へこぼれ落ちていく。
生きながらに喰われるのは、死んだも同然であろうか。ミケーレの時とは様子が違う。おとなしく薬を与えてやれる状況でもない。ならば望み通り、死なせてやるのが情けなのか。
平二は右眼に意識を集中させる。今の平二に頼れるものは他にない。平二の右眼は、徐々に赤い炎のごとき光を帯び始める。光に伴って、右眼から全身へと熱い血潮が巡っていく。
平二は円狐に言われたことを、意識の中で繰り返した。
――心を乱すな。
溶けた鉄のようにたぎる血が全身を駆け巡り、体中に力がみなぎってくる。
平二の鼻先すれすれまで迫っていた刃が、徐々に離れていく。平二が勢いをつけて刀を押し戻すと、長次郎の体が持ち上がった。宙に浮いた長次郎を、平二が下から蹴り上げる。長次郎の体が後ろへ投げ飛ばされると、すかさず平二は立ち上がった。
赤く色付いた平二の肌から、上気した汗が立ち上っていく。しかし肌はかつてのように、濃い赤銅色にはなっていかない。心の均衡を保ちながら、平二は妖力を練り上げていく。
長次郎もすぐさま立ち上がった。蹴られた拍子か、腹のさらしがほどけている。長次郎は、用をなさなくなったさらしを解いて地面に放った。
露わになった長次郎の腹は、右半分がなかった。大きな穴の空いた脇腹はあばら骨が露出し、桃色をした臓物が垂れている。その臓物の隙間を縫うように、血に濡れた巫蟲が這いずり回る。垂れ下がった腸を手で中に押し戻した長次郎は、再び刀を鞘に収めた。
長次郎の動きがぎこちなかったのは、この傷のせいか。しかし、これだけの怪我でここまで動けるのは、芭尾の暗示や巫蟲のせいばかりではあるまい。
長次郎が腰を低くして、右手を刀の柄に掛ける。それに応じるように、平二も太刀を正面に構えた。二人は向かい合ったまま、しばらく互いの気配に集中している。平二の右眼は光を失わずに、長次郎を正視している。
迫ってくる火勢によらず、見える光景は赤い。長次郎の脇腹から垂れ下がった黒い蟲は、流れ出す血とともに地面に落ちては消えていく。平二はその光景に吐き気を覚えた。右眼を閉じれば見なくてすむだろうが、そうすれば、すぐさま長次郎の刀が飛んでくるだろう。
すでに火の手はすぐそこまで来ている。平二の背中を、じりじりと熱風が炙る。熱さで痛みを感じ始めた時、長次郎の背後に人影が現れた。ミケーレが、慣れない着物をはだけて走ってくる。
「平二サンッ!」
遠巻きに二人を見定めたミケーレが、平二の名を呼んだ。
声が聞こえた刹那、長次郎の体が前に出た。平二の胴に狙いを定めて抜刀する。体の部位で、最も遅く動くのが胴体だからだ。
一瞬で長次郎の刀が平二に届くが、平二は後ろへ下がらずに、持っている太刀の腹で、真横から迫ってくる刃を受けた。がちんという音が鳴ると、すぐさま長次郎が刀を引く。平二の太刀と長次郎の刀が擦れ合って、不快な金属音が鳴り響く。
引いた勢いで半身を後ろへ反らした長次郎は、反動をつけて体を回転させると、平二の胸元に向けて、一気に刀を突き出した。
抜いた刀で切る抜刀術の軌道とは違う。突き出された刀は最短距離で平二に襲い掛かった。
避けきれない平二は、太刀の腹を長次郎に向けた。
平二が見切ったか、長次郎の刀が太刀の腹に突き立った。押し出された刀の勢いで、太刀の刀身は大きくしなる。平二は、負けじと突きを押し返すが、長次郎も全体重を掛けて押す。二人の拮抗する力に太刀がしなりきれず、砕けるように折れた。
長次郎の刀は頬を掠めるように、平二の背後へと逸れた。
長次郎の渾身の一撃だった。伸びきった長次郎の腕を沿うように平二が前に出ると、折れた太刀を長次郎の首に向けて振るう。
半分に折れた太刀の刃が、長次郎の首を深く切りつけた。勢いよく血しぶきが上がる。
長次郎は手から刀を落とすと、そのまま地面に倒れ伏した。
「へ、平二サン!」
ミケーレが声を上げた時から、瞬きする程の間しか経っていない。
呼びかけにも振り返ることのない平二は、長次郎の返り血を浴びて、半身が真っ赤に染まっている。
倒れた長次郎の傍らに腰を下ろした平二は、動かなくなった体を仰向けに起こすと、取れ掛けた頭を支えながら、そっと地面に横たわらせた。見開かれたままの眼を、血だらけの手で閉じてやると、死体に向けて両手を合わせた。
我に返ったミケーレは、長次郎を挟んで平二の反対側に膝を付くと、懐から十字架を取り出して、死者を送る祈りを唱える。
ミケーレの祈りが終わるのを待って、平二は口を開いた。
「…お前との約束を守れなかったな」
「私は見ていまシタ。長次郎サンはあなたを殺すつもりデシタ。仕方なかったんデス」
「理由はどうあれ、殺したのは俺だ」
「神様はあなたの行いを見ていマス。きっとあなたをお許しに…」
「いいよ。誰かに許してもらおうなんて思ってない。俺の地獄行きは決まっている」
そう言うと平二は立ち上がって、折れた太刀の先を拾った。腕の先程度の長さのそれに、長次郎の着けていたさらしを巻きつけて握りを作る。すると、少し長めの小刀ができた。
「円狐はどうした?」
平二が訊いた。ミケーレは俯いたままで、その言葉に答えない。
ミケーレは黙ったまま、抱えていた服を地面に下ろして広げると、中から血だらけの黙儒が転がり出てきた。
「…円狐サンは、芭尾に殺されてしまいまシタ。私も芭尾に殺されかけましたが、円狐サンが助けてくれたのデス」
ミケーレの眼から涙がこぼれ落ちる。
「平二サンの傷を治した円狐サンは、力が足りなかったんデス。それで逃げようとしたけれど、駄目でシタ…」
「そうか」
涙を流しながら話すミケーレに、憮然とした表情で答えた平二は、そのまま黙ってしまった。
ミケーレには、何も言わない平二がもどかしかった。人と物怪との違いはあっても、互いに共感しているのだと思っていた。それだけに、平二の素っ気ない態度が非道く冷たく感じられた。
「平二サンは、円弧サンが死んだことが悲しくないのデスカ?」
ミケーレの口調には、少なからず腹立たしさが込められている。
「さあな」
相変わらず平二の言葉は少ない。
期待した答えを諦めたミケーレは、転がった黙儒を指差した。
「…平二サンに、これを渡すように言われました」
円狐には絶対に触るなと言われた。ここまで持ってくるのに、ずっと服に包んで持ってきたのだった。
平二は黙儒に手を伸ばすが、すんでのところで触れるのに躊躇する。
「円狐サンが言っていまシタ。平二サンは触っても大丈夫だそうデス」
平二はもう一度、手を伸ばした。かすかに触れた感触を確かめると、手を広げて黙儒の柄を握りしめる。何もない。
「ミケーレ、円狐は何か言ってたか?」
「自分の分も頼む、そう平二サンに伝えてくれと…」
「そうか」
先ほどのように、素っ気ない答えが返ってくる。
しかし、平二が手にした黙儒は、ミケーレの言葉を聞いたと同時に、激しく火花を散らし始めた。それは、円狐が手にしていた時とは比べものにならない程、猛烈な勢いで周りを青く照らす。
平二の眼が、真っ赤な光を放っている。その姿に、ミケーレは平二が言ったことを思い出した。天狗にもらった右眼は、感情が高ぶると激しく光るのだと。
平二は頭に巻いた布を下げて、右眼を覆い隠す。すると、黙儒が放つ火花も徐々に治まり、ついには何も発しなくなった。
振り返った平二は、無表情なままでミケーレに訊いた。
「芭尾は、どこにいる?」
「…海の向こうへ行くと言っていまシタ。船で日本から出て行くつもりデス」
それならば、きっと港に向かったはずだ。外国へ出る船は、目の前の港に沢山停泊している。
即席の小刀をミケーレに押し付けるように渡すと、平二は折れた太刀と黙儒を両手に、橋の方へと歩き出した。
「平二サン、私は武器など…」
「持っとけ。芭尾の術が効かなくても、お前のまじないだって芭尾には効かないんだろ?」
「まじないじゃありまセン! イエス・キリストは…」
ミケーレの言葉を聞かず、平二は走り出した。
もう橋の上には人がいない。街から逃げてきた人々は、すでに居留地の中へと逃げたのだろう。その居留地の奥、横浜港に芭尾がいる。
平二に芭尾を倒せるだろうか。弱っていたとはいえ、円狐は全く敵わなかった。平二が敵う道理はない。呪われた右眼を持つ男の勝利を神に祈るしかあるまい。
平二に追いつこうと小走りに急ぎながら、ミケーレは胸前で十字を切った。