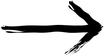「さあ、いくよ」
円狐は黙儒を構えた。ミケーレも十字架を持った手を胸前に掲げる。瓦礫の向こうで、芭尾が無表情のまま立ち尽くしている。何か仕掛けてくるつもりなのか、あるいは力の差が知れたので油断しているのか。円狐は後者を期待していた。まだ円狐は黙儒を本気で振るっていない。芭尾は、黙儒がどういう武器かをよくわかっていないはずだ。もし芭尾が油断しているのなら、勝機はある。
円狐は芭尾に向かって言った。
「どうせ逃げられないなら、ここで相手をしてやるよ」
「でかいのを逃がしておいてよく言う。――まあどのみち、お前たちは全員殺すけど」
いつの間にか芭尾は、瓦礫の山を回り込んで、円狐たちが見える所まで来ている。そのままゆっくりと移動しながら、円狐たちの逃げ道を狭めていく。
「ラブティ、どういうつもりで残った? 私の蟲を滅した程度で、どうにかできると思ったか?」
ミケーレは息を呑んだ。芭尾の両眼が青い光を放っている。その眼に睨まれたミケーレは、体の力が抜け落ちていくのを感じた。萬澤宿で、初めて芭尾と眼があった時と一緒だ。徐々に腰が重くなって、地面に尻を押しつけたい衝動に駆られる。
「お前は私の言葉がわかるだろう? なあ、ミケーレ・ラブティ」
芭尾の声は頭の中で反響して、まるで四方から聞こえてくるようだ。芭尾の力が強まっているのか、以前のように抗えない。まぶたが落ちてきて、今にも眼をつむってしまいそうになる。
その様子を察したか、円狐がミケーレの肩を握った。
肩に触れた手は、幻惑に取り込まれそうになったミケーレにとって、唯一確かな現実だ。その込められた力で意識が呼び戻される。
「円狐サン…」
「しっかりおしよ。ちゃんとさっきみたいにやるんだ、いいね?」
円狐の言葉に我を取り戻したミケーレは、十字架を芭尾に向けた。先ほどと同じように、覚えている限りの悪魔払いの祈りを唱える。しかし芭尾は、全くひるむ様子はない。
円狐が飛びかかった。黙儒を袈裟懸けに振るうが、あっさりと避けられて宙を斬る。身軽な円狐に比べても、芭尾の動きは速い。円狐の黙儒をすんでのところでかわしていく。
「なぜ太秦坊はお前みたいな弱いのをよこした? それとも――」
黙儒が芭尾の左肩にまっすぐ振り下ろされていく。しかし、あと少しで当たりそうになるところで、黙儒がぴたりと止まった。芭尾がその刀身を、片手で捕らえたのだ。
「これで、長次郎の腹を抉ったか」
黙儒の刀身が芭尾の手の中で激しく火花を散らすが、握った手はそのままで離そうともしない。
「見た目に派手だが、存外大したことはない。――妖力を吐き出す剣か。これじゃあ『人』はたまったものじゃないな。でも私を殺すには、少々足りない」
まるで握られているのを嫌うように、黙儒はばちばち音を立てる。それを芭尾がぐいっと引いた。円狐はそれに抗うが、体ごと引かれてしまう。
「だが中々おもしろい。この剣を私によこせ。同じ狐のよしみだ。これを置いていけば、殺さないでおいてやる」
芭尾の言葉に、円狐が眉を動かした。
「そうかい。ならミケーレはどうなる?」
芭尾がにやりと笑って答えた。
「そいつは駄目さ。なぶり殺しだ。――なんなら殺した後に、こいつをお前が喰ってもいい」
芭尾は、円狐が妖力を失っているのを見抜いている。剣から漏れるように伝わる妖力は、弱々しく覇気がない。
『人』の街中で物怪が妖力を取り戻すには、『人』を喰うしかない。
「お前は喰わないのか?」
円狐が芭尾に言った
芭尾と言葉を交わす円狐を、ミケーレが心配そうに見ている。芭尾はその姿を見て、笑いがこみ上げてきた。『人』が不安を抱き始めた瞬間が、この上なく楽しい。ミケーレは、なびき始めた円狐に対して不安を感じている。
「大人の男の肉は好みじゃない。全部お前にやるよ」
芭尾はそう言って黙儒を引くが、円狐は手を離そうとはしない。妖力の尽きかけた円狐にとって、芭尾に対抗し得る唯一の手段だ。そう簡単には手放さない。
「おまえ、私と来ないか? 船で海の向こうへ行くんだ。外国には、そこの異人のようなひ弱な坊主しかいない。――わかるだろう? 飽きるほど『人』を喰っても、誰も私たちを退治ができないんだ」
芭尾は円狐を見据えて言った。円狐にとっては悪い選択肢ではないはずだ。ここで死ぬか、一緒に来て生きるか、簡単な話だ。
「それは――悪くない話だね」
「そうさ、この男と一緒にいたヨハン・オールトの船で、私たちは海の向こうに行ける。さあ…」
芭尾が発した言葉を遮るように、ミケーレが叫んだ。
「円狐サンっ、駄目デス、芭尾の言うことを聞いてはいけナイ!」
声を上げたミケーレに、芭尾がうんざりとした眼を向けた。
ミケーレに気を逸らした芭尾は、円狐の変化に気付かなかった。
円狐は総毛立ったように震えると、その体から目に見えるほどの気迫を吐き出す。円狐が残った妖力を一気に黙儒に込めたのだ。ミケーレに気を取られていた芭尾は、すぐに応じることができなかった。とっさに黙儒から手を離そうとしたが、遅かった。
込められた円狐の妖力が、凄まじい勢いで黙儒の刀身を駆け抜けると、爆発したかのように噴き出した。それはもう火花でない。風に煽られた炎のごとく噴き上がり、黙儒を握った芭尾の手を弾き飛ばす。それ自身が意思を持つ黙儒は、使い手の妖力を何倍にもして、攻撃する力に替える。円狐は尽きかけた妖力を全部込めて、芭尾が触れた刀身から一気に吐き出させた。
勢いで後ろへ飛ばされた芭尾は、背後の瓦礫にしたたかに打ち付けられた。染み一つなかった外套とドレスは、焦げた木片のすすで黒く汚れる。片腕は手首から先がなくなっている。どす黒い血が滴り落ちる腕を見た芭尾の表情が、みるみるうちに歪んでいった。顔中に刻まれた皺が、芭尾の顔を醜く変化させている。芭尾はゆっくりと立ち上がると、円狐を睨み付けた。
「貴様ぁっ!」
芭尾の来ているドレスの裾がふわりと持ち上がると、中から鋭い槍が、稲光のごとき速さで円狐に伸びた。肩で息する円狐は、その場に立ち尽くしたままで避けられない。
槍は円狐の腹を貫いてもなお止まらず、後ろで燃えている家屋をも突き崩した。
槍は芭尾の尾だ。尾を紙縒のようにすぼめて鋭くしたものだ。尾が円狐の体から、ゆっくりと引き抜かれる。少しでも痛みを味合わせるように、ずるずると音を立てるようにこすって引き抜いていく。円狐が苦痛に呻くと、芭尾は口端を持ち上げて笑った。
引き抜かれる寸前で、芭尾の尾が膨れ上がった。急激に質量を増した尾が、円狐の体を上下に引き裂くと、腹から上が宙を舞った。
ミケーレの目の前には、円狐の下半身だけが残っていた。まだ立ち尽くしている円狐の腰から下が、ばたりと地面に崩れ落ちる。裂かれた胴から流れ出す血が、足下に大きな溜まりを作っていく。円狐の血が足先に触れた時、ミケーレは頭を抱えて絶叫した。
膝を落として泣き叫ぶミケーレを見下ろしながら、芭尾は血だらけになった尾を大きく広げた。渦を巻いて鋭くなっていた尾がほどけると、波打つ毛が放射状に広がる。芭尾の背後で、大きく太い芭蕉の葉が現れた。芭尾が芭尾と呼ばれる所以だ。
「よくも、やってくれた」
血溜まりの真中にある円狐の上半身は、仰向けになって転がっている。躊躇なく円狐の体に近づいた芭尾は、その顔を思い切り踏みつけた。動けなくなった円狐の顔を何度も強く踏みつけると、芭尾は円狐に唾を吐きかける。
「やめてくだサイ!」
走り寄ったミケーレが、円狐の体を庇うように覆い被さった。
「もう十分デス、もう円狐サンは死んでるんデス。お願いですからやめてくだサイ!」
「物怪が、そんな簡単に死ぬもんか」
芭尾の言葉に、円狐の体を抱きしめていたミケーレが顔を上げる。
「どのみち、このままなら死ぬだろうがな。そいつを助けたければ、お前が喰われてやればいい。――ミケーレ・ラブティ、物怪は人を喰うと力が出るって知っていたか?」
ミケーレはごくりと生唾を飲み込むと、ゆっくりと、腕の中にいる円狐に目をやった。その顔は、芭尾に踏みつけられたせいで、あちこち皮膚が破れて血だらけになっている。ミケーレはそっと自分の耳を円狐の口元に近づけた。
ミケーレは両目を見開いた。微かにだが、円狐の吐息が聞こえる。
その時、どんっと背後から鈍い音が聞こえてくるのと同時に、焼けるような激しい痛みが、背筋から脳天へと走り抜けた。叫び声を上げるミケーレの背中には、鋭い芭尾の尾が突き立っている。その尾は背中を貫いて、腹の方まで突き出ていた。
芭尾が笑って見下ろしている。
「物怪と『人』がじゃれ合って、――胸糞悪い」
芭尾はそう言うと、ミケーレの背中に突き立てた尾をずるりと引き抜いた。ミケーレが抱えていた円狐の体が転がり落ちる。それを見て笑った芭尾が、ミケーレの肩を蹴り飛ばした。腹を貫かれたミケーレは、円狐と自分が流した血の溜まりに没した。
「ここで焼け死ね」
そう言い放った芭尾は、近くに転がっていた黙儒に近づいた。それを拾い上げようと、腰をかがめて右腕を伸ばす。しかし腕の先に手がない。芭尾は一瞬顔を歪ませると、黙儒を強く蹴り飛ばした。転がった黙儒は、円狐たちの流した血に浸る。
日本人街を取り囲む火事は、どんどん勢いを増していく。芭尾はその火勢から逃れるように姿を消した。
虫の息の円狐とミケーレは、燃えさかる炎のまっただ中にいる。
上半身だけになった円狐は、仰向けのまま血だらけで横たわっている。その傍らには、腹に穴を開けられたミケーレが倒れている。
ミケーレは呻き声も上げられず、ただひたすらに心の中で祈りの言葉を繰り返していた。もう痛みはない。感じないのだ。寧ろ血が大量に流れ出したせいで寒い。炎に囲まれて、皮膚がじりじりと焼かれているはずなのに。
自分は一体、日本まで来て何ができたのだろう。イタリアでの満たされていた毎日にわだかまりを感じて、この国に来た。たどり着いた日本では、居留地の中に閉じ込められて、布教もままならず、何も結果を残していない。
平二や円狐、彼らのことは、物怪の存在すら碌に知らなかった自分には、何者であるのか理解できなかった。
でも、共感はしたのだ。平二の自責の念に、円狐のやり場のない怒りに、そしてそれぞれの無念の思いに。それだけに何もできなかったことが悔しい。
ミケーレは涙を流していた。痛みや訪れる死への恐怖からでなく、ただ悔しさで泣いた。歯軋りを立てて、息も尽きかけた喉の奥から、嗚咽を漏らして泣いた。
「……み、ミケーレ、……生きてるかい?」
円狐が微かな声で囁いた。声にならない声を上げて泣いていたミケーレは、その声に目を開いた。そうだ、まだ円狐は生きているのだ。
「…まだ、生きているなら、…よくお聞き」
ミケーレは声のする方に顔を向ける。そこには円狐の上半身だけが仰向けになっている。泣くのを堪えるミケーレは、円狐に言った。
「円狐サン…聞こえマス。まだ、生きていマス」
「いいかい…ここに落ちている剣…黙儒を、平二に届けておくれ」
ミケーレのところからは黙儒が見えない。見ようにも、胸から下はまるで自分のものでないように動かない。
「で、でも…もう、私は動けまセン」
「大丈夫…お前は死なないよ」
円狐は痙攣する腕を、ミケーレの方へ伸ばした。
「…手をお出し。あたしの手を握るんだ」
「……それより、円狐サン――私を…食べてくだサイ」
その言葉に円狐は黙った。驚いたのか、あるいは怒ったのか、いずれにしても、その表情を見ることはできない。
「私は…もう死にマス。…せめてあなたの役に立って…死にタイ」
円狐は黙ったままだ。円狐の手がミケーレの方を探る。
だらりと伸びたミケーレの左手が、まさぐっていた円狐の手と重なった。
「あたしは…『人』を喰わない。芭尾とは…違う。…誰かに言われたから…じゃない。私がそう…決めたんだ」
円狐の手から、暖かな心地が伝わってくる。その暖かみはミケーレの手を伝って、肩から心臓へ、血の流れに乗って全身へと伝わっていく。もう感覚がなくなった体でも、その暖かみを感じることができた。体の感覚が戻ってきても、貫かれたはずの傷は痛くない。
ミケーレが見ている円狐の姿が、どんどん霞んで見えなくなっていくと、目の前に青々と茂った木々の立ち並ぶ光景が見えた。その木々の間を勢いよくすり抜けていく。森の中にいるようだ。緑と土の匂いが、鼻の中に充満していく。
今は火事のまっ只中にいるはずなのに、燃える煤の臭いも血の臭いもない。森を抜けると、目の前に小さな滝が見えた。清涼な水がざぶざぶと音を立てて流れていく。水同士がぶつかって、清々しい匂いが立ちこめている。
ミケーレは、その光景と匂いに激しい郷愁を感じた。一度も見たことのない景色に、胸が詰まるほどの懐かしさを覚える。知らない場所なのに、そこへ帰りたい思いが沸き上がる。
この景色はきっと、円狐の故郷なのだろう。感じている思いは、きっと円狐のものだ。円狐の手から伝わる暖かさと共に、いろいろなものが自分に流れ込んでくるのがわかる。
すると、遠くから自分を呼ぶ声が聞こえた。円狐の声だ。
「……ここに落ちている黙儒を平二に届けてやってほしい。でも、お前はこれに触っちゃいけないよ。何かに包んで持って行くんだ」
「でも、私は…」
聞こえてくる声にミケーレは答える。声を口から出している訳でない。自分が思った言葉が、水の流れる音に混じって聞こえてくる。
「大丈夫、お前はここで死なないよ。いいね、お前は剣に触っちゃいけない。嫌われると痛くされるから。それと平二に伝えておくれ。――あたしの分も頼むって」
最後の言葉の意味を悟ったミケーレは、胸が締め付けられるような思いに包まれた。
ミケーレは声を上げて嗚咽した。
「ミケーレ、泣いてばかりじゃないか。怖いことなんてないよ」
「…そうじゃナイ、あなたが泣かないから、私が泣いているんデス。つらくて苦しいはずのあなたたちに、私は何もしてあげられナイ。だから、泣くんデス」
「そうかい。最後まで面倒かけるねぇ…」
ミケーレが見ていた光景が、また徐々に霞んで見えなくなっていくと、途端に現実の景色が目の前に拡がった。火で燃える街並が眼に飛び込んでくる。
体中が熱い。先ほどまでは血が流れて、寒いほどであったはずなのに。感覚を取り戻した体は、炎に焼かれる痛みから逃げる様に訴えている。体に力を入れると難なく動く
ミケーレは、体を起こしてあたりを見回した。円狐の体はもうそこにはない。芭尾に貫かれた腹をまさぐった。そこにはでこぼことした傷跡があるものの、もう穴は開いていない。
ミケーレは血と涙で濡れた顔を袖で拭うと、着ていた綿入りの胴服を脱いだ。血でべっとりと濡れたそれを裏返すと、地面に落ちている黙儒を包んで持ち上げる。
真っ白い刀身は、円狐の血で赤黒く汚れている。それを抱えたミケーレの両目から、また涙が溢れてきた。
自分を食べてくれと言ったのに、逆に円狐に助けられた。きっと平二の傷を塞いだように、自分の傷を癒やしてくれたのだろう。ミケーレの命を取り込んで、生き永らえることもできたのに。円狐は自分を犠牲にして、ミケーレを救ったのだ。
死の間際にいても『人』を食べぬと言った円狐は、最後まで気高かった。彼女は化け物などではない。きっと円狐は、精霊や天使のような存在だ。遠い世界の東の果てで、ミケーレは奇跡と出会ったのだ。
ならば今、自分がするべきは何か。この黙儒を平二のもとに届けることだ。そのために円狐が自分を生かしてくれた。 芭尾を逃がしてはいけない。逃がせば、もっと悲しいことが起こる。
歩き出そうとしたミケーレの足に、竹の皮でできた包みが当たった。ミケーレがそれを取り上げると、中身が入っている。前と同じように握り飯が二つ入っている。
包みを懐にしまうと、ミケーレは燃えさかる街の中へと飛び込んでいった。