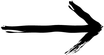七、岐路
日本人街で起こった火事で、居留地にいる外国人たちも混乱に陥っていた。封鎖されていたはずの門が壊され、日本人街から逃げてくる者たちがなだれ込んできた。居留している各国の軍人たちも、武装して集結した。しかし、家財道具を抱えて逃げてきた者たちを、火事の中に追い返すわけにもいかず、居留地の中は、逃げてきた日本人で溢れかえっていた。
既に居留地の一部に延焼し始めた火事を見て、各国の代表団たちは、真っ先に船の待避を指示した。西欧各国から集まった蒸気船や大型帆船は最新鋭ではあるものの、いずれも材質のほとんどが木製だ。ひとたび火が付けば、あっという間に燃えてしまう。
ヨハン・オールトが指揮する商船団は、船体横に水を掻く外輪が付いている蒸気船エンホーン号と、大型の帆船フローニゲン号の二艘で構成されている。既に出港準備が整いつつあった二艘は、すぐに港の沖合に逃げることができる。船員たちは、蒸気船であるエンホーン号でフローニゲン号を牽引して、沖まで出る準備を進めていた。
芭尾にとって、火事による船の待避は予想外の幸運であった。日本人街から戻った芭尾は、港に向かうオールトに合流し、すぐにフローニゲン号に乗り込んだ。
甲板上から見える横浜港は、火事の炎で明るく照らされている。燃えさかる炎は、すでに外国人居留地の一部にまで浸食を始めていた。
船の甲板上に立つ芭尾は、先ほど円狐と相対した辺りを見やった。炎が舞い上がり、もう建物は崩れ落ちている。そこにいるはずのミケーレ・ラブティも、黒焦げになった頃であろう。
芭尾は手首から先がなくなった腕を見て、苦々しい表情を浮かべた。
狐の物怪と、ミケーレ・ラブティは返り討ちにできた。存外楽に撃退できたものの、右手を丸ごと失ってしまった。さして痛みもないが、失った体の一部を元に戻すには、時間と妖力が必要になる。
右手のことばかりではない。逃がした大男と、長次郎が斬ったという男のことも気掛かりだ。だがそれも夜の海へ出てしまえば、もう懸念することもない。手首のほうも、いずれ幾人かを喰えば済むことだ。むしろそれらの中で、大きさの合う手首を継いでも良かろう。
船縁にもたれて燃える街を眺めている芭尾の元に、ヨハン・オールトがやってきた。傍らには関兵衛が立っている。言葉のわからない芭尾のために、オールトは関兵衛も連れて行くつもりだ。日本語のわかる関兵衛は、既に芭尾の術中にあるが、オールトはたらし込んだだけで、未だにうまく操ることができない。言葉がわからないおかげで操り様がないのだ。
この男は、ことあるごとに芭尾に色目を使ってすり寄ってくる。求愛の言葉を関兵衛に通訳させて、自分といれば、如何に幸せな一生が送れるかということを言ってくる。しかし関兵衛のオランダ語も怪しいもので、言っていることの半分も通訳できていないだろう。
芭尾は、手のない右腕を外套の合わせで隠した。話しかけるオールトに振り向くこともなく、燃える街を見る。芭尾の素っ気ない態度にも関わらず、オールトは芭尾の腰に手を回して、自分の方へ引き寄せた。大勢の船員たちが、船を出すために甲板を走り回っているが、人目を構おうともしない。
腰を押しつけるように抱き寄せてくるオールトに、芭尾は抵抗するでもなく、したいようにさせる。用が済めば、この男も何かの術の材料にでもするつもりだ。日本から出るまでは、せいぜい好きにすればいい。
船さえ出てしまえば、もう誰も追っては来られない。あと少しだ。
※
平二とミケーレは、火を消すために奮闘する人々の間を縫うようにして走った。
居留地の外国人たちは延焼してきた火の手を恐れて、必死に屋敷からものを運び出している。それを眺めていた日本人も、一人二人と外国人らを手伝う者が出てきた。その内に、延焼してきた炎を消し止めようと、協力して運河から水を汲み出し始める。
居留する外国人全員が船で沖へ逃げられる訳ではない。それにどの船も、すぐに岸壁から離れられる状態ではない。この居留地まで炎に包まれれば、大多数の人々は逃げ場がなくなるのだ。
門を封鎖していた役人たちは、皆惚けて道ばたに座り込んでいる。そんな役人たちをよそに、居留地の外国人と逃げてきた日本人たちは、助け合い始めたのだった。
平二たちが走っていくと、燃え始めた屋敷の前で一斗樽を両脇に抱えた大男が見えた。一目だ。
「一目!」
平二が叫ぶと、体の割に小さい頭が振り向いた。走ってきた二人を見定めた一目は、持っていた樽の水を燃えている炎に向けて撒き散らす。圧倒的な水量で火が押し流されると、周りから歓声が上がった。それをよそに、一目は平二たちのほうへ走り寄った。
「仁八とタケは無事か?」
平二の問いかけに、一目は深く頷いた。
黙儒に気付いたのか、一目は視線を平二の手元に向けている。それを見たミケーレが口を開いた。
「円狐サンはあの後、芭尾と戦って…」
ミケーレの声色で悟ったのか、一目は皆まで聞かずに一際強く舌打ちをする。
「芭尾は船で外国へ逃げる気だ。沖に出られたらもう追う手立てがない。――お前も来るか?」
一目は平二の問いかけに頷くと、ミケーレの体を抱え上げた。
「ミケーレ、ここからはあんたが道案内をしてくれ」
言われたミケーレが、港の方を指差して言った。
「あっちが港デス。港で待ち伏せすれば、芭尾はきっと現れるはずデス」
横浜まで来たときと同じように、ミケーレの体を抱きかかえた一目が走り出した。巨体に似合わぬ軽快な動きで、人混みの中を走り抜けていく。平二もそれに続いた。
外国人居留地の中は、平二たちにとって見慣れない風景だった。道は神社の参道のごとく舗装されている。立ち並ぶ屋敷は大きな二階建てで、障子でなく硝子の窓がはまっている。
しばらく走ったところで、ミケーレが声をあげた。眼の前には一際変わった形の建物が見える。
「こ、ここで止まってくだサイ! 少し、少しだけ待ってくだサイ」
立ち止まった一目から飛び降りたミケーレは、その変わった形の建物の正面にある、大きな両開きの扉を開けて中に入っていった。高くとがった屋根を持つ建物の外壁は白く塗られている。平二は、その屋根の先端に見たことのあるもの見つけた。暗い空に浮かぶ白い十字の飾り。ミケーレが何かと掲げていた、あの木枝を組み合わせた物と一緒だ。
ミケーレの後に続いて、平二も建物の中へと入っていく。扉の中は、柱の他に仕切りもなく、襖も障子戸ない。大きな部屋になっていて、横に長い椅子が等間隔で並べられている。扉からまっすぐ続く通路の奥、小ぶりな祭壇の下でミケーレは膝を着いている。
飾ってあった十字架が、床に落ちたまま転がっている。デュボワ神父が、日本へ来る折に持ってきた銀製の十字架だ。ミケーレはそれを拾いあげて祭壇に戻すと、再び片膝をついて、十字架に向かって手を組んだ。
「ここが、あんたの言っていた教会ってところか?」
「そう、神の住まわれる場所デス」
「…急ぐぞ」
「もう少しだけ待ってくだサイ。祈りを終えたら、すぐに行きマス」
ミケーレはそう言って、首をうなだれる。しばらくして顔を上げたミケーレは、祭壇の上の十字架を手に取った。
ミケーレはこの十字架を持っていくことにした。いずれにしても、ここにあっては火事で教会とともに焼けてしまうかもしれない。
大きな十字架を重そうに持ってくるミケーレに、平二が言った。
「まさか、それを持っていくわけじゃあるまいな?」
ミケーレは首を縦に振ると、一目に向かって言った。
「一目サン、この十字架の下に付いている台を外してもらえまセンカ? 一目サンの力なら、簡単に外せると思いマス」
言われた一目は十字架を差し出されるが、手を出そうとはしない。円狐は触っても平気だと言っていたが、やはり少しはためらいがあるのだろう。
「一目サンなら大丈夫デス。先ほど神は、あなたを助けマシタ」
一目は軽く舌打ちをすると、十字架をむんずと握りしめる。それをミケーレの手から持ち上げると、十字架の下についている台を持って引っ張った。何度か傾けたりするうちに、繋げていた溶接が外れたのか、十字架はきれいに台から離れた。
一目に礼を言ったミケーレは、十字架を受け取ると外へと出る。
すると、汽笛の音が聞こえてきた。しかし様子がおかしい。汽笛の音が繰り返し、幾つも鳴っている。
「…ミケーレ、この音はなんだ?」
「わかりまセン、でも船の汽笛をこんなに鳴らすなんて…」
「とにかく、急ぐぞ」
走り出した平二に従って、一目もミケーレを抱えて走り出す。
港は教会からは、さほど遠くない。走り出した平二たちは、すぐに海が見えるところまで来た。港には物資を保管する木造の倉庫が、間断なく立ち並んでいる。それらから、樽やら木箱やらを乗せた荷車が頻繁に出入りしている。火の手が迫る前に貴重な品々を持ち出すつもりなのだろう。港のあちこちから、異人たちが怒号を上げる声が聞こえる。
建物の間にある暗がりに平二たちを残して、一人で港の岸壁に出たミケーレは、木箱に縄をかけていた若い男に声を掛けた。
「すいまセン」と思わず日本語で言ったミケーレは、相手がきょとんとしているのに気づいた。ここは居留地だ。ほとんどの者は日本語がわからない。
ミケーレがイタリア語で聞くと、相手は英語で返してきた。
「すいません、ちょっと」
「……あんた、神父さんだろ? いったい、その恰好はどうしたんだ?」
ミケーレは改めて自分の身なりを思い出した。着物はぼろぼろのままで着替えてはいない。それに暗くてわかりにくいが、血だらけになっているはずだ。手に持った大きな十字架以外には、自分が神父であることを示すものは何一つない。きっと相手が教会に来たことがあって、ミケーレの顔を覚えていたのだろう。
ならば話は早い。ミケーレは慌てて英語で返答した。
「少々込み入った事情があって、ある人を探しています。日本人の女性です。知りませんか?」
「いや、俺も今来たばかりで知らないな。大体こんな状況じゃ、誰が何人かなんてわからないよ」
「どういう状況なんです? なんでこんなに沢山の人が…」
「火事から船を遠ざけるために、急いで沖に出す準備をし…」
その時、近くの船が汽笛を鳴らした。甲高い機械仕掛けの笛の音で、男の声がかき消させる。
「…だ。夜で見えないから、ああやって音を出して、お互いに自分の船の居場所を教えてるのさ」
再びどこかで汽笛が鳴ると、それに応えるように、また音が鳴る。
「神父さん、もういいかい? 俺、もう行かないと」
「あ、あと一つ、教えてください。オランダの…ヨハン・オールトさんの船はどこにいますか?」
「ああ、オランダ商船団なら、もうとっくに沖に出てるよ。昨日から出港準備をしてたからね。出るのが早かった」
「エエッ」と声を上げて、がっくりと肩を落としたミケーレをよそに、若い男は踵を返して行ってしまった。ミケーレは、力なさげに平二たちの元に戻る。
「おい、どうしたんだよ、ミケーレ?」
「……オールトサンの船は、もう海へ出てしまったそうデス」
「…何?」
俯いて話すミケーレに、仏頂面の平二が聞き返した。
「芭尾は、オールトサンの船で外国へ行くのだと言っていマシタ。だとすれば、もう追うのは無理…」
ミケーレは途中まで言いかけて唇を噛んだ。夜の海に出て行った大型船を追えるような手立てはない。仮に船で海へ出たとしても、相手の船がどこにいるかもわからないのでは、どうしようもない。
「…私が教会に寄ったりしなければ、間に合ったかもしれナイ」
「そんなことあるかよ」
懺悔の言葉を漏らすミケーレに、平二が言った。
「芭尾はまだすぐそこにいるんだ。どこかで船を…」
「無理デス! こんなに暗いのに、どうやって芭尾のいる船を見つけるんデスカ? それに沖に出た船は一艘だけじゃないんデス!」
「だったら、片っ端から乗り込んでいけばいいじゃねえか」
「正気デスカ? 日本人が船に乗り込んだりすれば、捕まる前に銃で撃たれマス。いくら私が一緒でも、あなたを庇いきれマセン」
もうあきらめた様子でうなだれているミケーレをよそに、平二は岸壁へと歩き出した。
港に突然現れた褌姿の平二に気づいた者たちの動きが止まる。平二が両手に持った太刀と黙儒に気付いて、逃げ出す者までいた。暗がりとはいえ、平二の姿は外国人だらけの港ではよく目立つ。
居留地にいる者達は、一部の日本人が外国人に対して激しい憎悪を持っていることをよく知っている。特に支配階級で軍人である侍の多くは、外国人が日本にいることに我慢ができないらしい。護衛を付けずに居留地の外へ出た者たちが、難癖を付けられて侍に斬られそうになるのは、よくあることだ。場合によっては、そのまま帰ってこないこともある。都度、斬った侍は殺人犯として捕えられて処刑されるが、同じようなことが後を絶たない。
居留地の港で太刀を持った平二を見れば、皆が危機感を抱くのは当たり前であった。しかも今の平二は、体中が返り血で汚れている。混乱に乗じて、日本人が襲いに来たと思われても致し方ない。
逃げて行く外国人たちをよそに、平二は港の船着き場に走った。沖に向かって伸びている船着き場には、船に詰め込むために倉庫から引き出された荷物が乱暴に積み上げられている。荷物を乗り越えて、船着き場の先端にたどり着くと、平二は海を見渡した。
そこからは、真っ暗な海が一望できた。火事のせいか、ほんのり明るいが、かえって遠くが見え難い。海上にいるはずの船の影さえ碌に判別できない。
しばらく目が慣れるまでじっと暗闇を見つめていると、不鮮明ながら、遠くにいくつかの船影が見えた。その数八つ。どれに芭尾が乗っているかはわからない。いや、芭尾はそれのいずれにも乗っていないのかもしれない。
ミケーレの言う通り、ここでまた芭尾の行方が分からなくなった。平二はその場に腰を下ろすと、じっと海上を見つめた。
――さあ、どうする。
平二は唇を噛んだ。八方ふさがりだ。何も思いつかない。
こんな状況で、いい手立てが思いつくような頭はない。円狐に言われた通り、俺には学がないのだ。そう、こんな時に円狐がいればなんと言うだろうか。
平二は右手を上げると、眼を覆っていた布を押し上げた。あいつは「右眼で見ろ」と言った。何度も、そう円狐から言われた。
あらわになった右眼は、徐々に赤く光りだす。光はどんどん強くなって、体に熱い血潮が巡り出す。夜の海は赤黒く、曇り空は赤い闇となって平二の右眼に映る。しかし、左眼で見たのと同じように、船影は相変わらず不鮮明で、その外観さえはっきりしない。それでも平二は、必死に右眼を凝らした。もうこれしか頼れるものがない。
「平二サン!」
背後からミケーレの呼ぶ声が聞こえた。平二を追ってきたミケーレは、荷物をよじ登ってきたらしく、ぜいぜいと息を切らしている。
「大変デス、平二サンを捕まえようと人が集まってきていマス! 早く逃げないと…」
ミケーレが言いかけた時、平二がつぶやいた。
「…見つけた」
「えっ?」
「ミケーレ、芭尾を見つけたぞ!」
平二の眼は光を放ちながら夜の海を見つめている。その視線の方向に顔を向けるが、ミケーレには真っ暗な海しか見えない。
だが平二の右眼には、はっきりと見えていた。芭尾の双眸が青く光る二つの点になって、赤黒い世界に煌々と輝いている。あの光は芭尾の眼だ。あの冷たい光、間違いない。
すると平二の横に、すうっと一目の顔が寄ってきた。ぎょっとして平二が仰け反る。初めて一目を右眼で見た。顔の真ん中に大きな目が一つ。口元はいつものように、にんまりと笑っている。一目は、小さな船の上に乗っていた。二本の櫂を両手で漕ぐ西洋式のものだ。どこから持ってきたのか、船には荷まで載っている。
背後から、積みあがった荷を乗り越えてやってくる者たちが怒声を上げた。振り向いてそちらを見ると、手には何やら長いものを持っている。小銃だ。
平二とミケーレは、一目が拝借してきた船に飛び乗った。二人が飛び乗ると同時に、一目が手に持った櫂で水を漕ぐ。しかし、西洋式の船の漕ぎ方がわからないのか、一本の櫂を両手で持って漕いでいるせいで、まっすぐに進まない。
「一目サン、それ、貸してクダサイ!」
見かねたミケーレが、もう一本の櫂を持って言った。やおら後ろ向きになって、船の中央に座ったミケーレは、側面にある穴に櫂を嵌めると、両手で二つの櫂を引くようにして水を掻く。すると船は、どんどん船着き場から離れていく。
「おお、こうやって漕ぐのか?」
平二が感心しているうちに、幾人かが船着き場の先端にたどり着いた。平二たちの乗った船に銃を向けている。周辺で銃弾が水を弾く、ぽしゃんという音がいくつも聞こえてきた。
ミケーレに相対するように座っていた一目が、船を漕ぐミケーレの手をむんずと包み込むように握ると、押す様にして船を漕ぎ出した。一目の力で、船はぐんぐん速度を上げていく。
「一目サン、い、痛いデス。場所を変わってクダサイ」
ミケーレが懇願すると、一目が手を放した。もう岸から離れているので弾は届いてこない。
ミケーレに代わって、船の中央に腰かけた一目が漕ぎ出すと、先ほどまでとは桁違いの速度で船が進み出す。
平二は、体に巻かれたさらし布に手をかけた。斬られた傷を押さえておくために巻かれたものだが、幾分緩んでしまっている。手早くさらしを解くと、背中の傷が露わになった。ミケーレが縫った傷は、痛々しく盛り上がって血が滲んでいる。
「平二サン、まだ包帯を取ってはだめデス!」
「動きにくいんだよ。もう傷も塞がっているし、いいんだ」
そう言った平二は、解いたさらし布を丸めて放った。
手を背中に回して、傷の具合を確かめる。痛みはあるものの、体の深いところから傷が塞がってきているようだ。
平二は、背中に触れていた手の感触を思い返した。まどろみの中で感じたあれは、傷を癒してくれた円狐のものだったのだろう。
おゆうが介抱してくれたときも背中をさすってくれた。斬られて苦しむ平二の背中を、ずっとさすってくれた。あの時のおゆうの手、そして円狐の手のぬくもりは、二本の傷と共に残っている。ぬくもりをくれた手の主たちは、いずれも芭尾に殺された。自分の命が継がれたのは、その仇を討つためだ。それ以外に、この命の使い道はない。
平二たちの船は、沖に避難した船の間を通り過ぎて、まっすぐ一番沖合にいる二艘を目指す。
「あのでかい船には、どうやって乗る?」
ミケーレにも船の輪郭がわかるほど近付いた頃、平二が言った。
「よじ登るしかないでショウ。誰かが引っ張り上げてくれるとは思えマセン」
「一目、俺を船の上に投げられるか?」
平二に背中を向けている一目は、振り向きもせずに首を縦に振る。
「できるだけ遠くから、あの船に向けて俺を放り投げてくれ。――あとは自分でなんとかする」
平二がそう言うと、一目は櫂を漕ぐ手を止めた。船は惰性で水上を滑るように進んでいく。櫂を降ろした一目は船が傾かないように、ゆっくりと立ち上がった。
「おう、ここからでも届くかよ?」
平二の問いに、一目はにんまりと口角を上げた。平二は頷いて応えると、ミケーレに振り返った。
「ミケーレ、世話になった。ここでお別れだ」
突然の申し出に、ミケーレは眼を丸くした。
ここまで来たのだ、当然自分も付いていくつもりでいる。
「何を言い出すんデスカ? わたしは一緒に行きマス。神の力は、芭尾にも通用するんデス!」
「芭尾だけを殺すってわけにはいかないだろ。――あの船に乗っている奴らも、芭尾に操られているなら殺すことになる。そうしたら、お前まで人殺しだぜ」
「平二サンはどうするのデスカ?! あなただって、これ以上は…」
「……俺はいいんだ。もうさんざん手を汚した。今更何人殺しても変わらん。さっきだって、お前の知り合いを殺しただろ? いずれ俺は、役人殺しでお尋ね者になる。捕まれば死罪だ。だから、悪いことは全部俺がやっておくんだ」
「何を言ってるんデス? あなたはまだ若い、まだ時間はたくさんありマス! 罪を償う機会はいくらでもあるンデス! ――そうだ、全部終わったら、あなたもキリストの下に学びましショウ。修道僧になれば、残りの人生を償いに費やせますカラ!」
それを聞いて平二は、少し嬉しそうに、だが、寂しそうに微笑んだ。
「坊主になるなんてな、俺の柄じゃねえよ」
きっと平二は死ぬ気だ。敵わないのを承知で芭尾と戦った円狐と同じだ。円狐を救えなかった。その上、平二までこのまま行かせてはいけない。
ミケーレは必死に食い下がった
「私も行きマス! 私が行けば、あなたを救えるはずデス。もう人殺しなんてさせまセン!」
ミケーレの言葉をよそに、平二は一目に声をかける。すると一目は、舌打ちしながらも平二の褌を掴んだ。
「一目、ミケーレのことは頼んだ」
平二の体が高く持ち上げられる。両手で平二を頭上に構えた一目は、上体を反らして振り被ると、思い切り放り投げた。両手に太刀と黙儒を持った平二は、体を丸めて夜空に飛んでいく。
それは届かぬどころか、下手をすれば目的の船を飛び越えてしまいそうな勢いだ。
ミケーレは、その様子を口を開けて眺めているしかなかった。
――これでは、平二に付いて行くのはとても無理だ。
懐を探ったミケーレは、平二に渡された小刀を取り出した。物怪を殺せる太刀の半分だ。
「わ、私はあんな風にできませんから、どうか、平二サンのところまで連れてってくだサイ!」
そう言うとミケーレは、手に持った小刀を自分の首に当てた。
「どうか、お願いデス。一目サン、行ってくだサイ!」
一目の手がミケーレの肩に伸びた。小刀を持った腕に触れないよう、そっとミケーレの肩を触る。
ミケーレは一目の顔を見た。その顔は、あの夜に見た一つ目の顔だ。だがもう驚きはない。一目が物怪だとしても、人ならざる者であっても、自分を害さないのはわかっている。
一つ目の一目が分厚い唇を開いた
「平二も助けてやってくれ」
その言葉を聞いたミケーレは、そっと小刀を持った腕を降ろすと、膝をついて泣き崩れた。
「平二も」と言ったのは、円狐を救おうとした自分を、そして今、なそうとしていることを、一目も分かってくれているということなのだろうか。自分が平二や円狐に共感したように、一目もまた、自分の思いを理解してくれているのかもしれない。
嗚咽の止まらないミケーレを尻目に、一目は再び船を漕ぎ始めた。