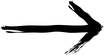※
しばらく身延山の参道を登った平二は、道を外れて走り出した。
きっと役人たちは、またすぐに追ってくるだろう。先程は思いがけず、右眼のお陰で相手が逃げ出してくれた。しかし、一体どうしたのかはよくわからない。自分が怒っていたことはわかっている。だが、またあれをできるかはわからない。
とにかく今は、少しでも遠くへ逃げるしかない。平二は人が入り難そうな方を選んで行く。
山狩から逃げた時と同じだ。結局こうやって逃げまわるのが性に合っているのだろう。こんな俺と夫婦にならなければ、おゆうも死なずに済んだだろうに。
またあてどなく、どこまで逃げればいいのか。いや、今度は違う。逃げるのでは無い。おゆうの仇――芭尾を追って捜し出し、この手で殺すのだ。
平二は進むに連れて、自分の走る疾さがどんどん上がっているのを感じていた。山の中を獣の様に走っている。膝まで生えた草も、枯れ草の積もったぬかるみも、苦もなく滑る様に走り抜ける。小川や大きな窪みも難なく飛び越える。しかもまったく息切れしない。
轟々と風を斬る音を聞きながら、ひとしきり走った。目の前が急に開けると、沢に突き当たる。生い茂った草木を押しのけるように並ぶ岩の間をすり抜けて、大量の水が流れ落ちていく。
いつの間にか、日が落ちて暗くなり始めている。沢を覆い隠す木々のせいで辺りは一層暗い。
平二は苔の生えていない岩を選んで、その上に座った。片手で沢の水を汲み上げると口元へ運ぶ。ふと鼻血のことを思い出して、救った水で顔を拭った。何度かそれを繰り返して、今度こそ両手で水を飲む。日嘉が言っていたとおりなら、平二にとってそれは三日ぶりに飲む水である。
一口飲み込んだ水は喉を通り越すと、すぐに体中に染みこむように吸い込まれていく。冷たい沢の水が、火照った体内を冷やしていく。
「気が済んだか?」
また水を飲もうと手を伸ばした平二の背後で、聞き覚えのある男の声がした。
平二は振り返らずに沈黙する。
「平二よ、聞こえておるだろう? 答えろ」
声の主は、黙ったままの平二にまた声を掛ける。
「………いや、まだ飲み足りない」
平二はそう言って、また両手で掬った水を飲んだ。
「山ン本が言っているのはそういう事じゃあない。逃げても無駄なことが、わかっただろうってことさ」
いつの間にか平二の正面、水の流れの向こう側に円狐が立っている。山の中だというのに、泥の跡一つない白木の下駄を履いて、苔むした岩の上に立っている。
平二は、円狐の方を見ずに答えた。
「太秦坊さん。この女狐は、俺の女房を殺した奴とは違うんだろ?」
「お前の目の前にいるのは円狐だ。芭尾ではない」
「そうか」
平二は、濡れた両手を払うと顔を上げた。
円狐が苦々しい表情を隠そうともせずに、平二を睨みつけて言う。
「坊さんに助けてもらおうかと思ったか? それとも死んだ女房が恋しくなったのかい? どっちにしても情けないねぇ…」
円狐の言葉を遮るようにして平二が言った
「あんたらはなんで、その芭尾という奴を追うんだ? 仲間のうちの一匹が逃げただけだろうに。それともなにか恨みでも…」
平二の言葉に、円狐が声を荒げた。
「あいつはね、人を喰う、外法を使う、物怪だってなぶり殺す。あんな下種とあたしらを一緒にするんじゃないよ!」
すると今度は太秦坊が話しだした。
「ここの山を開くと言ってやって来た坊主と約束した。儂らは山を出る、『人』は儂らの住む場所に入らない、儂らは『人』に関わらない、『人』は儂らに構わない。それは儂らにとって掟であり、『人』を儂らから遠ざける手段だ。芭尾は幾度となくその掟を破った。だから封印した。しかしあれは、その封印を自力で破って逃げ出した」
平二が声の方へ振り向くと、太秦坊が岩の上で胡坐を掻いて座っている。
「あれはお前の女房を喰って皮を剥ぎ、それを被って逃げた。…否、被ったのでない。自分の皮と取り替えた。外法の術だ」
「……?」
平二は訳がわからないというふうに、首を傾げる。
「そこにいる円狐は化けて人の姿をしている。儂もそうじゃ。本当の姿は右眼で見ただろう」
平二は無言で頷く。
「だがな、芭尾は化けずに自分の毛皮を剥いで、『人』のものと付け替えた。『人』を殺して、その皮を被り、その者に成り代わる、まさに外道のやりようじゃ。そうすると、誰が見ても人の姿にしか見えん。それは儂や円狐が見ても同じ。しかも臭いまで変わる」
「ようするにあんたらは、俺の女房の顔を知らない。だから俺に捜せということか?」
「そうだ。まだ奴が獣であった時の残り香を追うことができる。だがそれも、すぐになくなってしまうだろう。だから、奴の臭いがある今のうちに追わねばならぬ」
平二は岩の上に立ち上がって、太秦坊に向き直った。
「探すだけってのは嫌だ。奴は俺が殺す。あんたは俺に殺させてやると言ったはずだ」
そう言った刹那、平二の首元に白い剣が突き付けられた。知らぬ間に、円狐が真横に立っている。
「芭尾はね、お前が差しているような、ちんけで粗末な一物じゃあ殺せないよ」
円狐は、平二が腰に差している短めの刀を一瞥した。先刻役人たちが落としていった中の一振だ。一時期は山賊であった平二は、いくらか武器の扱いを知っている。平二は見た目に立派な長物よりも、扱いやすくて小回りの利く短い刀を好む。
「こいつはね、黙儒という象牙で作られた霊刀さ。持つ者の妖力を吸って相手を斬る。妖力が強ければ強いほど切れ味鋭く、当たれば骨まで弾け飛ぶ。――私が山ン本からもらったんだ。芭尾にはね、こういう得物じゃないと敵わないんだよ」
「なら、それを俺にくれ」
「馬鹿言ってんじゃないよ。これはね、持ち主を選ぶんだ。黙儒は気に入らない奴に触られると、怒って火花を散らすんだよ」
円狐は黙儒の突先を平二に向けて、ぐいっと突き出した。
平二は足を滑らせて、岩から転げ落ちた。それを見た円狐が声を上げて笑う。
「くだらんことはするな。おい一目、平二を起こしてやれ」
太秦坊が言うと、岩陰から大きな影が現れた。そこから太い丸太のような腕が伸びて、沢に落ちた平二を掴み上げる。
岩の上に戻された平二は、その大きな影の方を見るが、暗がりでその姿は良くは見えない。
「これは一目という。お前と円狐、そしてこの一目とで行ってもらう」
一目と呼ばれた大きな影の上に、小さな頭らしきものが乗っている。そこから、ちっと舌打ちする音が聞こえた。
「山にいるもので『人』の姿になれるのは、儂と円狐、あとはこの一目ぐらいしかおらぬ」
太秦坊は、手に持った白い布を平二に差し出した。それは太秦坊の屋敷で、平二の右眼を隠していたものだ。布には、眼に当たる部分に何か描いてある。
「これを付けておけ。その右眼の妖力を抑える。必要なときに外せばいい」
平二はそれを受け取った。
「芭尾の本当の姿が見えないなら、この眼は必要あるのか?」
「その眼が無ければ、芭尾と眼があっただけで睨み殺される。人外の者でなければ、奴を討ち取ることなどできん」
「…俺は、もう人外なのか?」
平二の言葉を聞いて、円狐が鼻を鳴らして笑った。
「フンッ、半分だけさ。山ン本の眼をもらったとはいえ、まだ半分は臭くて汚い『人』だ。あたしらの仲間になったようなこと言うんじゃない。――行くよ、一目」
円狐はそう言うと、山の方へ上り始めた。もう日が落ちて、月明かりしか頼りがないにも拘らず、軽々と岩から岩へ飛ぶように乗り移っていく。
それに続いて、大きな影が動いた。一目の見上げるような巨躯が、月明かりで露わになる。
平二は、一目の姿を間近で見た。見上げるほど大きな巨体に、丸太のような腕が生えており、これまた石臼のように大きな足がそれらを支えている。体の割に小さな顔は、目鼻立ちがはっきりとしないが、唇は突き出しているかのように分厚い。
一目の小さな二つの目が平二を見下ろしている。眼が合うと、また舌打ちする音が聞こえた。そのままそっぽを向くと、流れる水を堰き止めるがごとく、沢の中を進んで行く。
「来るか?」
太秦坊が平二に向かって聞いた。
おゆうの仇を討つのなら一緒に行くしかあるまい。元よりそのつもりだ。
月明かりを背にして立つ太秦坊に無言で頷くと、平二は手にした布を頭に巻いた。
太秦坊は、宙を歩くように岩から岩へと飛び移っていく。それに追いつこうと、平二も沢に連なる岩の間を駆け登る。
三つと一人の影は。山中の暗闇へと消えていった。
※
慶応ニ年(西暦一八六六年)十月
おゆう殺しの下手人である平二を追って、門前町と近隣の村の男衆によって山狩が行われた。しかし平二の逃げた痕跡はなく、消息は分からず終いであった。
日嘉は役人らに問い詰められたものの、頑なに平二と話したことを言わず、平二の無実を訴えた。
甲斐国八代郡杉原村の外れで起こった此度の一件は、結局平二を逃したことで責めを負わされるのを恐れた御番所の役人が、平二とおゆう共々、熊に襲われて死んだことにしてしまった。平二を捕らえようと妙石庵へ詰めかけた者たちも、以降この件には触れようとはしなかった。
平二が去ってから数日後、日嘉は、平二とおゆう、二人が暮らした小屋に火をつけて燃やした。中にあった家財道具も何もかも、全てそのまま小屋と一緒に燃やしてしまった。 平二はきっと戻らない。ならば、自分たちの思い出の品が、人手に渡ることを望まないだろうと思ったからだ。
平二から受け取った髷は、おゆうの墓に埋めた。小ぶりな土饅頭に石を置いただけの簡素な墓だが、日嘉が自ら葬ったものだ。その土饅頭を掘り返し、おゆうの亡骸に重ねるようにして、髷を一緒に埋めてやった。
それから日嘉が他界するまでの四十年間、平二はおゆうの墓のある身延山に戻っては来なかった。