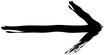天狗の眼(上) 二、逃避行 1幕 2幕
二、逃避行
芭尾は昼夜を通して山中を走った。追手に気づかれぬよう、自分の気配を消し、臭いを残さぬよう、途中とちゅうで何度も体を洗った。数百年かけて封印を解いたのだ。簡単に捕まるわけにはいかない。
芭尾が封印されたのは、人肉を喰ったことが理由であった。
妖狐・芭尾は、五百年前にこの世へ現出した。何かから生まれたのでなく、気づいた時には存在していた。
ある日、山に迷い込んで死んだ『人』を見つけた。以前に、『人』の肉を喰ったものから、その味のことを聞かされていた。獣や魚の肉とは違う香ばしい芳香を漂わせ、その血のしたたるや、まるで熟したざくろを頬張ったかのようであるらしい。またその滋味は、体の内から全身に染み渡るようで、一口食べる毎に妖力まで増してくる。特に眼玉はとびきりの甘露なのだという。
人を喰うことは、太秦坊の山では法度とされていた。古い昔、近くに霊山を開いた坊主と約束をしたのだという。物怪は『人』に近づかぬ、だから『人』も物怪の住む山には入って来ない。
だが、死ねばただの肉塊だ。芭尾はそう自分に言い訳をして、その『人』であった肉の塊を喰らった。無地のみすぼらしい野良着姿の男だった。死んでいくらか日が経っているのか、所々に蛆が湧いている。だが、食えぬわけでもない。
その肉は多少筋張っていたが、確かに、噂に違わぬ美味であった。
集っている蛆を払って腹の皮を割くと、中から薄紅色の臓物が出てきた。それを引っ張りだし、ずるずると音を立てて咀嚼する。またそれは甘みと苦味の混じった、なんとも言えぬ味がする。ひと際赤い色をした心臓は、こりこりとした歯ごたえで、噛む度に血が口中に溢れていく。芭尾は、見られることに用心もせず、夢中になって、その男の死体を貪り食った。
そしていよいよ、眼玉に手を伸ばした。やはり眼玉は腐りやすいのか、死体の目元に蛆がのたうち回っている。芭尾はそれを丁寧に払い除けた。鋭い爪先でつぷりとその表面を割って、眼玉に爪を潜り込ませていく。ゆっくりと眼玉を引き出すと、ぶちぶちっと筋やらがちぎれる音がする。
眼玉を一つ、口の中に放り込んだ。何度も舌で転がしてから歯で潰すと、水飴のように甘くねっとりとした旨みのある液体が、口の中で広がった。それは清水のような清涼さを伴って、喉から胃袋まで流れていくのがわかる。芭尾は一つを食べ終わると、すぐにもう一つを抉り出した。やはり美味い。『人』とはここまで美味いものか。そして何より、妖力が増してくるのがわかる。
芭尾が『人』の肉を喰ったことが、他のものに気付かれることはなかった。しかし芭尾は、あの味が忘れられぬ、またあれを喰うにはどうすればいいかと、始終思案するようになった。
明けても暮れても『人』を喰うことばかり考えていた芭尾は、太秦坊を嫌う物怪を訪れた。
物怪にも、馴れ合うもの、従順なもの、気易いものと様々なものがいる。だがわずかに他を寄せ付けず、太秦坊に従わない物怪がいる。芭尾が訪れたのは、かつて山神として『人』に祀られ、人身御供を得ていた物怪だ。理由は知れないが、行き場がなくなって、太秦坊の山に流れてきた。
狭く暗い湿った洞にいるそれは、決して他のものに姿を見せない。かつて自分が奉られていた様を大袈裟に語るので、住んでいる洞にかけて『法螺神様』と呼ばれていた。芭尾に『人』の味を説いて聞かせたのもこの物怪だ。
芭尾が男の死体を喰ったことを言うと、法螺神はひいひいと喉を鳴らして笑った。法螺神曰く、死体など『人』を喰ったうちに入らないという。『人』で美味いのは女だ、男など筋張っていて噛んでもちっとも味がない。子供は、味はいいが量が少ない。若い女は、脂がのっていて味もいいし量もある。何より『人』は生きているうちに喰らうのが良い。そう言って芭尾の食い気を誘った。
法螺神は、太秦坊も知らぬ外法の術を芭尾に教えた。妖狐の芭尾は、『人』を化かすための瞳術ぐらいは知っている。しかし法螺神のいう外法の術は、まるで聞いたことのないものばかりであった。
物怪は妖力を持つ。『人』でいう気力や精力のようなものだ。しかし物怪は、妖力を使って、『人』にはできないことをする。
幻を見せるには、空間を自分の妖力で満たして、相手の思考を支配する。見かけを変化するのなら、自身に妖力を込めて体の形を変える。心を操るには、妖力で心の内に入り込んで、意思や思惑を変えてしまう。
しかし、法螺神の教える外法の術は、獣や『人』を使って為すものばかりであった。使うとは、まさしくその生命を利用することだ。それらの持つ気力も精力も利用して、己の妖力と練り混ぜる。すると、より強い力を得ることができる。『人』を喰らって妖力が増すのも外法の内なのだという。
『人』を道具のように使い、『人』を材料にして術を為す。『人』の血で臭いを消し、『人』の皮で面を作って、『人』の中に紛れた。そうして人里に下りて、美味そうな『人』を物色し、山の奥へと攫って行った。
法螺神の言う通り、『人』は生きたまま喰うのが美味かった。
『人』を食わぬ物怪は妖力も弱い。外法の術で欺かれた芭尾の行いを見咎めるものなど現れるはずもない。稀に芭尾を不審に思うものがいても、確信を得る前に芭尾に殺されてしまった。
芭尾は外法の術を使うことに躊躇がなかった。自分が知らなかった術は、望んだ全てを可能にする。自分よりずっと年齢を経た物怪を欺くことができる。太秦坊でさえ、その例外ではない。
現に何人もの『人』を攫って喰ったが、一向に芭尾の悪事が知れることはなかった。男も喰った。女も喰った。子供も喰った。いろいろと食べ比べた。食べる度に妖力が増し、使う術の効きも強くなっていく。芭尾はもう、到底気取られることなどないと確信していた。
確かに物怪で気付くものはなかった。しかし芭尾は、『人』に報復されることを考えてはいなかった。
ある夜、人里に降りた芭尾は、待ち構えていた僧侶の一団に折伏(退治)されかけた。
僧侶たちの唱える経文の声は、耳を貫かんばかりの轟音に聞こえた。打ち付けられた錫杖は、熱した鉄棒の如く芭尾の皮膚を焦がし、肉を抉っていく。命からがら逃げる芭尾を追って、僧侶たちは太秦坊の山まで押し入ってきた。
芭尾を見失った僧侶たちは山を立ち去ったものの、芭尾の行いは、太秦坊をはじめとする物怪らに露呈する羽目になった。傷つき弱った芭尾はその夜のうちに追い詰められ、太秦坊の術で山頂近くにある大岩の隙間に押し込められた。その細い隙間に閉じ込められた芭尾は身動きが取れず、体中に激痛を覚えながらもがき苦しんだ。岩は硬く、弱った芭尾にはどうやっても砕ける代物ではない。
太秦坊は、芭尾を押し込んだ大岩の隙間を塞ぐように呪符を貼りこんでいった。いずれ芭尾が力を取り戻しても、呪符があれば出て来れぬ。こうして芭尾は封印されたのだった。
芭尾はこの封印を五百年かけて自力で解いた。伸ばした爪で、貼られた札と岩の隙間をかりかりと引っ掻いた。妖狐の芭尾にとって鋼のように硬い呪符も、長い年月をかければ少しずつ剥がすことができる。時々は太秦坊が見に来るので、悟られぬよう、呪符を剥がしきらぬよう、慎重に裏側から掻いた。そうすれば、表からの見た目は同じままだ。
数百年経って、呪符の隙間から覗く景色の中に人里が見えるようになった。その数はどんどん増えていき、かつては森であった場所が大きな集落となっていく。まるで水に垂らした油のようにそれが広がっていく様を、芭尾は毎日眺め続けた。
こうも簡単に増える『人』を喰ってはいけない道理とは何だ。許されぬと太秦坊は言った。すれば『人』は、物怪を折伏しに押しかける。互いに関わらないという決め事が無くなってしまうのだという。
そうしてもう随分経つが、物怪の住む山も森も、どんどん『人』が侵食していくではないか。あれは喰って減らすのが道理なのだ。喰って美味いのは、あれが物怪に喰われるべき生き物だからに相違ない。なのに、なぜ許されぬ。
いや、そもそも太秦坊が許せば良いのか? 『人』を喰らえば物怪は折伏されるのに、『人』が獣を喰っても咎めがないのはなぜだ? なぜ『人』だけが許される?
芭尾の封印が後少しで解けようという時、芭尾の視界に一軒の小屋が目に入るようになった。
小さい娘とその親が住んでいた。娘が幼いうちに、母親の姿を見なくなった。娘は日に日に成長し、父親と助け合って暮らしている。
芭尾は封印が解けたあかつきには、まずこの娘を喰らうと決めた。そのうちに父親の姿がなくなり、しばらくして娘の小屋に若い男がいるようになった。男は筋張っているが、妖力を取り戻すには少しでも食べておいたほうが良いだろう。
そうして芭尾は、封印が解けると真っ先に、平二とおゆうの住む小屋へと向かったのだった。
※
自分の皮と『人』の皮を付け替えた。見た目も臭いも『人』そのものになった。こうなると物怪の眼にも簡単には見抜けぬ。付け替えた後は、皮と肉が張り付くまで動かないのが良いのだが、そうもいかなかった。皮を付け替えた直後に、封印から芭尾が逃げたことを察した太秦坊が追ってきたのだ。
皮が肉になじまぬうちに暴れたせいで、体のいたるところに皺が寄ってしまった。その上、着るものもなく、ずっと裸のまま逃げ続けている。夜半に移動し、昼間は隠れてじっと待つ。気配を消して闇に紛れる。それでも幾度か、太秦坊の手のものに追いつかれた。とはいえ、所詮は人を喰わぬ、碌に力のないものばかりだ。都度、返り討ちにしてやった。
太秦坊の山から離れ、あてどなく彷徨った芭尾は、整地された細い道へ出た。周りは竹やぶに囲まれていて暗いが、昼間はまばらに旅装束の者が通る。どうやら、ただの山道ではないらしい。
『人』の気配がある所まで来ると、さすがに追ってくる物怪はいなくなった。
だが、まだ安心は出来まい。力のない物怪は、化けることさえできないものがほとんどだ。だが中には、『人』の姿になれるものがいるはずだ。きっとそれが追ってくる。とにかく、できるだけ遠くへ、太秦坊の手の届かぬところへ逃げ延びなくては。
芭尾は夜が更ける頃に、道の脇に裸のままで倒れこんだ。暫くそのままでいると、足音が聞こえてきた。芭尾はそのまま目を瞑って耳を澄ます。女の身である以上、さして警戒されまい。うまくすれば誰かが助け上げる筈だ。そうすれば着るものぐらいは手に入るだろうか。
足音が近くなると、一旦止まった後で慌てたように駆け足になった。複数の足音が重なって聞こえる。数は三人程か。
声はするが、それは芭尾が聞いたことのない言葉であった。徐々に近づく足音と声は男のものであろう。その内の一人が芭尾の体を抱き起こす。
目を開けた芭尾が見たものは、驚くほど大きな鼻を持つ顔だった。一瞬、天狗かと身構えた芭尾に、後ろにいた別の男が声を掛けた
「おい女よ、いったい何があった?」
その聞き様は『人』に違いないが、自分の体を抱き起こした面妖な者は一体何だ?
芭尾は様子を見ようと黙っていると、鼻の大きな男が聞いたことのない言葉で何かを言う。すると別の男が、また訳のわからない言葉で答えた。
「女、口が聞けぬか?」
これは『人』であろうか。いずれにせよ答えるしかあるまい。
「……追い剥ぎに襲われました。追って来れぬようにと身ぐるみを剥がされ、この場に捨て置かれたのです。どうか…どうか、助けてくださいまし」
芭尾に話かけた男は「なっ!」と一声上げて驚くと、腰に差している刀に手を掛けた。どうやら男は侍らしい。
「それは、今しがたかのことか?」
「……はい」
「ならば、この近くに――」
男は辺りを見回すが、既に真っ暗で、提灯の光が届くところまでしか見えない。
「いえ、追い剥ぎはお侍様の姿を見て、どこか逃げてしまいました」
「そうか、――女、名前は?」
名前も予め考えておいた。
「……おふう、と申します」
男は芭尾=おふうの名前を聞くと、鼻の大きな男と会話を始めた。やはり聞いても理解はできない。すると鼻の大きい男は、後ろで見守っていたもう一人の男に声を掛けた。提灯の灯に照らされたその顔は、やはり見たこともない彫の深い顔立ちだ。その男は着ていた外套を脱ぐと、芭尾の体を覆うようにそれを掛けた。
「ここにいるのは、イタリア人のラブティ神父と、オランダ人のオールト氏だ」
聞いたことない言葉の羅列に混乱している。五百年前に封印されてから、外界との接点がなかった芭尾には全く理解できない。
芭尾が呆けた顔をしていると、男が言葉を続けた。
「お二人とも異国から来たと言えばわかるか? 私は相馬長次郎、神奈川奉行の御使番をしておる。――おふうよ、立てるか?」
芭尾は、「はい」と答えて立ち上がる。
「ともかく、このすぐ先の宿場町まで一緒に参ろう。そこで番所にでも届けるといい」
うまくいった。少々思い描いたこととは違うが問題はない。何より『人』と一緒ならば、もう太秦坊は簡単に手を出せぬ。
芭尾のにやりと笑った顔は、暗闇を行く三人には見えなかった。
※
円狐と一目、そして平二は、芭尾を追って山中を走った。
出発したのは、太秦坊のもとに戻ってすぐだった。平二には、熊の毛皮でできた胴服と、錆びついた太刀が渡された。毛皮は寒さをしのぐために、そして太刀は芭尾を殺すためだ。錆びた太刀は、一見して古いものだとわかる。鞘はところどころ塗が剥げ落ち、深く反り返った刀身は、錆びている上に刃まで欠けている。
自分の拾った刀のほうがましだと言う平二に対して、太秦坊は、「この太刀なら芭尾を殺せる」としか答えなかった。仕方なく太刀を受け取った平二は、追い立てられるようにして出発したのだった。
円狐曰く、芭尾の通ったところには、まだ臭いが残っているらしい。だが、おゆうの皮を被った芭尾の臭いは徐々に薄れていく。もうすぐ、その臭いもなくなってしまうというのだ。
『人』である平二に構わず、円狐と一目は昼夜を通して走り続けた。太秦坊からもらった右眼のお陰か、置いてきぼりにはならないものの、平二にとっては付いて行くのがやっとである。
そうやって走り続けて丸一日、平二たちは山中の街道へ出た。それは東海道がある駿河国から、甲斐国をつなぐ駿州往還という街道で、別名「身延道」とも呼ばれている。身延道と呼ばれるのは、この道が駿河から身延山へ参る人々が往来するからである。街道は大部分が山中を通るので、険しい道のりになる。
円狐は街道に降りると立ち止まった。自分の立った場所から、何度も前後に振り返る。臭いの濃い方向を確かめているのか。
その傍らで、平二は両手を膝について息を切らせている。それを見た円狐が平二に言った。
「…ったく、この程度でへばっちまうのかい? これでもお前に合わせて、のんびりと来てるってのに、ほんとに厄介だね」
息が荒い平二は、前かがみになりながらも顔を上げた。
「仕様がないだろ…、それより芭尾はここにいたのか?」
「……」
「おい、どうなんだ?」
「さあね、いたのかもしれないし、そうでないかもしれない。――それより、もう少し他人行儀に話しな。そんな風に気安くされると、嫌気がするよ」
一目はともかく、円狐はどう見ても人にしか見えない。まとめあげた黒髪に、鼻筋の通った面立ちをしており、肌は透き通ったように白い。無地袖の着物は首元を大きく開いている。まるで浮世絵の美人画のようだ。右眼で見た狐の姿が、一体どうすればこれになるのか想像もつかない。
「そう言われても、こういう風にしか話せねぇよ。行儀のいい話し方なんて知らない」
円狐は平二に聞こえるように「ふんっ」と鼻を鳴らすと、街道の端の地面を指差した。
「ここに…この辺りに、芭尾の臭いが残ってる。それに合わせて、嗅いだ事のない臭いもする。『人』が幾人か、ここで立ち止まったね」
平二は街道の一端に目をやった。
「確か、この先に宿場町がある。ここを行ったんなら、その宿場町に出ているはずだ」
円狐は平二を見ずに答える。
「そんなこと言われなくてもわかる。こっちの方向に臭いが残っているからね。――で、お前はその宿場町に行ったことあるのかい?」
「いや、ない」
「なら、余計なことは言うんじゃないよ。さも知ったような口を利かれても、糞の役にも立たない」
円狐の辛辣な言葉に閉口した平二は、言った方向に向けて歩き出した。その背中に円狐がまた声をかける。
「勝手にどこへ行くんだい? お前はあたしらに付いてくるんだ、先に行くんじゃないよ」
その言葉に平二は振り向いた。
「ここは『人』が作った街道だぜ。あんたのその格好じゃ、走るわけにはいかない。それに誰が先に行こうと、行き先が一緒なんだから関係無いだろう。――それとこの先、道中は長くなりそうなんだ。俺が嫌いだからと、いちいち突っ掛るのはやめてくれ」
「生意気言うなよ、餓鬼が…」
円狐が鋭い目付きで睨めつける。
「それだ、そうやって悪態つくのが余計だって言っているんだ。お互い必要だから一緒に来たんだろう? ちゃんとやらなきゃ太秦坊に怒られるぜ」
「……」
平二の言う通り、あまりに円狐が平二に突っ掛るので、太秦坊は一目に目付け役として一緒に行くよう命じたのだった。一目にしてみればいい迷惑である。
「…あたしが嫌いなのはお前じゃない、『人』が嫌いなんだ」
「なら、帰るか? 幾ら嫌いだと言われても、俺は『人』をやめられないぜ。――そもそもあんたには、奴を殺す理由はないだろ」
「あたしだって、あれに借りがある。やらなきゃならない理由はあるんだ。――それにあたしがいなきゃ、あいつの臭いは追えないだろうに」
円狐は平二をあざ笑うように鼻を鳴らした。
「そうでもないさ。ここまで来れば奴の行き先はおおよそ分かるぜ」
「…どういう事だい?」
円狐が訝しい顔で訊いた。所詮は百姓の平二なんぞに、女房の仇を討とうなんて気概があるなどとは思わなかった。そもそも芭尾の姿を見分ける以外に、大して役に立つとは思っていない。それが今、芭尾の行き先がわかると言っている。
「約束しろ。いちいち突っ掛るな。一応は、同じ旅往く仲間だろ。――約束できるなら、教えてやるよ」
円狐は、平二を睨んだまま口を尖らせた。そのままじっと黙ったままでいる。
暫く返答を待った平二が痺れを切らせて歩き出そうとした時、頭ひとつ上の方から声が聞こえた。
「いいぜ」
驚いて平二が振り向くと、声がしたあたりには一目の頭があった。初めて聞いた一目の声は低く嗄れていたが、はっきりと聞き取れた。円狐も両目を見開いて、驚いた顔で一目を見上げている。平二はその様子に思わず失笑した。
笑う平二に、円狐が顔を真っ赤にして言う。
「糞っ、なんだってんだい。腹が立つ!――わかったよ、ただし芭尾を殺すまでだからね」
「それでいい」
平二は答えると、こっちへ来いと手招きする。先を歩く平二に円狐が追いつくと、その後から一目が付いて来る。
「この街道は、まっすぐ行くと甲斐を出て駿河に辿り着く。駿河は知ってるか?」
円狐は黙ったままで答えない。物怪にとって、国をまたいだ外の事など伝聞以外に知る由もない。当然『人』が作った街道のことなど、碌に知るはずもない。
「このずっと先にある駿河は、東海道っていう街道の大きな宿場町だ。そこまで行けば、東は江戸、西は大阪まで続いている。芭尾が行く先はそのどちらかで間違いないだろう。この時期は旅人も少ない。この先どこかで、芭尾を見た奴がいる筈だ。そいつらに聞けば、おおよそ行き先の見当はつく」
「なんでお前にそんな事がわかる? 元は百姓だろう?」
山賊であった頃に、旅人の通る街道のことを、詳しい仲間から聞いていた。その街道を歩いたことはないが、そこを歩いてくる旅人がどんなかはよく知っている。
「…まあ、それより次の宿場町まで急ごうか。ここいらで芭尾が拾われたなら、その宿場には行ってるだろう。臭いはこっちか?」
「少し薄いが、こっちに続いてる」
平二は自分の知らぬことを知っている。一緒に同道すれば、多少は役に立つかもしれぬ。
円狐は道を行く平二の後ろを歩きつつ、その横顔を見やった。まだ幼ささえ見て取れるほどに若い。歳は十八、九であろうか。髪は後ろにかき集めて短く縛っている。何のことはない平凡な男だが、なぜ太秦坊は助けたのか。やはり不憫に思って同情したか、あるいは芭尾を追わせるためか。いずれにせよ、この男は太秦坊から眼をもらった。半分は物怪ということか。
その半分だけなら受け入れてやってもいいだろう、そう自分に言い聞かせながら、円狐は平二の後へと続いた。
天狗の眼(上) 二、逃避行 1幕 2幕