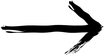※
身延山には参道が二つある。一つは日蓮宗総本山久遠寺を通る本道、そしてもう一つは、山の開祖である日蓮ゆかりの地をたどる裏参道である。山の麓にある門前町から、その裏参道を入ってしばらくのところに、妙石庵と呼ばれる寺がある。その昔、日蓮が近隣の村の者を集めて説法を行った場所だ。日蓮がその上に乗って説法したという大きな岩があり、元は天狗であったと言われる妙法大善神が寺社に祀られている。
妙石庵の住職である日嘉上人は、裏参道を下っている。禿げた頭は丁寧に剃られており、無精な様子は一切ない。もう五十を過ぎた年齢だが、人と会う機会が多いので、身嗜みには気を使っている。向かっているのは、平二とその妻おゆうが暮らしていた小屋だ。
そこは元々、おゆうが父親と住んでいた小屋だった。耕す土地を持たない父親は、強力として近隣の村々で手に入る食物を、山の中腹にある久遠寺へ運ぶことを生業としていた。父親が体を壊してからは、おゆうが妙石庵のまかないとして働いた。
身延山は元々が女人禁制であったが、徳川家康の側室、お萬の方の熱心な願いによって、その禁制が解かれたという。その縁もあってか、徳川十五代目の時代になっても、いまだ妙石庵には徳川家の信徒が参る。
身延山の名所であり、訪れる信徒も多い妙石庵にとって、おゆうは欠かせない働き手であった。
父親が死んでから、おゆうはいつの間にか平二と暮らすようになった。大怪我をして倒れていた流れ者の平二を、おゆうが助けて介抱したところ、そのまま居付いてしまったのだ。素性の知れぬ者に関わることを日嘉は反対した。だがおゆうは「これも縁だから」と、平二とともに暮らすようになったのだった。
きっと、父親がいなくなった寂しさも手伝ったのであろう。それから一年の間、傷が癒えた平二は、強力の真似事をするようになり、おゆうの元を離れずにいたのだった。
そのおゆうが、突然来なくなったのが三日前である。何の知らせもなく、おゆうが妙石庵に来ない。以前に体の調子を崩した時は、その日のうちに平二がそれを言いに来た。しかし今回は、丸一日たっても何の知らせも無い。不審に思った日嘉が、平二たちのもとへ使いの小坊主をやると、泣きながら腰を抜かして帰ってきた。小屋には誰もおらず、開け放たれた戸から見える土間は血だらけで、異臭さえするという。
慌てて駆けつけた日嘉が見た光景は凄惨であった。小屋の中は、床、壁のみならず天井にまで血しぶきが散っていて、転がる肉塊が腐れた臭気を放っている。
更に異様なのは、辺り一面を覆うように、おびただしい量の獣毛が散らばっていたことだ。
あまりの光景に、日嘉は胃の中の物をすべて吐いた。とても正視できるものではない。
すぐに役人が呼ばれて、検分が行われた。はじめは熊に襲われたのだと言っていた役人らも、散らばった毛だけでなく、剥がれた毛皮を見て考えを改めた。皆、気味悪がって検分は遅々として進まず、ついには僧侶である日嘉までも手伝う羽目になった。
小屋の中から見つかったのは、大量の毛と毛皮、腐りかけた肉塊と、人一人分の骨だった。一人分と分かったのは、髑髏が一つだけ見つかったからだ。
日嘉は、肉や毛のついた皮をその場で燃やして、骨だけを妙石庵へ持ち帰った。骨はきっと平二かおゆうのものに違いない。獣にでも襲われたのか。それにしても、もう一人はどうしたのか。
その内、検分した役人が話したことに尾ひれがついて、噂が広まった。天狗やら物怪に襲われたのだと。あるいは神隠しにあって、山の神に食われてしまったとも言われた。
近隣の者たちが、小屋を燃やしてしまおうと言い出した。天狗の仕業であろうと何であろうと、皆は気味悪い噂の元を根絶やしてしまいたいのだ。そこで日嘉が、小屋にある二人の物を持ち出すことになった。万が一、いずれか一人が戻ってきた時のためだ。
参道を外れて山道を行くと、程なく小屋が見えてきた。日嘉の足取りは重い。一昨日の検分以来、一度もここに戻って来ていない。小屋の中の惨たらしい光景を思い出して、引き受けたことを後悔した。如何に僧侶とはいえ、怖いものは怖い。
小屋の前まで来て、日嘉は戸が空いている事に気がついた。検分をした時、確かに戸を閉めていったはずだ。それにも関わらず、入り口の戸は半開きだ。
土間や板間に広がっていた血溜まりは、もう乾いて真っ黒な染みになっている。その染みに黄色い毛が絡められて、一緒にこびり付いている。
部屋の奥の方に、黒い達磨のような影があった。人がいる。
影はじっとそこから動かない。時折、頭が動く。間違いない、誰か小屋の中にいるのだ。山賊やら流れてきた者が隠れているのかもしれぬ。しばらく小屋の中の様子を見て、影が複数でないことを確かめる。日嘉は意を決すると、声を上げた。
「そこにいるのは…誰か?」
返事は無く、影も動かない。
「聞こえるか? 儂は妙石庵の坊主で、日嘉という者だ」
日嘉が言うと影が動く。暗がりの中にいる影が、ゆっくりと振り向いた。手で顔半分を隠すようにしている。日嘉は一歩前に出る。身を前に乗り出して影の正体を見た。真っ裸で座っている平二が、こちらを見ている。
「へ、平二か? なんと、無事だったのか!」
声をかけるが返事はない。じっと日嘉を見ているだけだ。しかも不自然に、右眼を手で隠している。
その尋常でない様子に、日嘉は近づくのをためらった。
「平二、何か言わんか? 一体今までどこにいた?」
平二は黙ったままだ。しかし、見開いている左側の目で、じっと日嘉を見つめている。日嘉は小屋の中へ足を踏み入れた。血の跡を避けるように進むと、平二の前に立った。
「儂がわかるか。日嘉だ。覚えておろうが?」
「……日…嘉…上人」
平二が口を開いた。
「どうしたんだ、何があった?」
「…おゆうは? ここに…おゆうの亡骸があったはずだ」
日嘉は持ち帰った骨のことを思い出した。あれはおゆうだったか。
「…亡骸は、三日前に私が供養して埋葬した」
「三日って、――あれからもう三日も経ったのか」
平二は興奮気味に言った。
「あれからとは、どういうことだ? 一体、おゆうに何があった?」
「……」
また黙り込んだ平二に、日嘉は質問を続けた。
「まさか、お前が手に掛けた訳ではあるまいな?」
「俺じゃない。俺がおゆうを殺すなんて…」
「わかっている、だから事情を話せ。何も言わぬのでは、力になってやることもできん」
「……」
平二はまた黙ってしまった。右眼を手で抑えたままで俯いている。
「とにかくここを出て妙石庵まで来い。その顔も、怪我でもしておるのなら治療しないと…」
「いや、これは…いいんだ。怪我じゃない」
「なら、服を着てここを出るんだ。ここは臭いがひどくて、とてもいられん」
小屋の中は、血と獣の臭いで充満しており、いるだけで吐き気を催させる。先程から日嘉は、袖を鼻に当てて臭いに耐えている。
日嘉に促されて、平二は部屋の隅に置いた小さなつづらを開けると、中から野良着とふんどし、そして手ぬぐいを取り出した。
日嘉に背を向けて、手ぬぐいで右眼を隠すと、着替えを始めた。野良着はあちこち擦り切れているものの、丁寧に折りたたまれている。生前におゆうが洗っておいたものだ。
着替え終わった平二は、裸足のままで土間に下りた。僧侶である日嘉とは違って、平二は普段から裸足で、草履は持っていない。
日嘉は平二を連れ立って、来た道を戻っていく。短い道中とはいえ、二人は殆ど会話をしない。よそ者の平二は、元々近隣の者たちと話すことが少なかった。
身延山の近隣に住む者は、大抵が日蓮宗の信徒だ。おゆうも父親と共に熱心な信徒であり、日嘉がいる妙石庵にも足繁く通っていた。しかし、平二は寺に来ても、手を合わせることがなかった。何度かおゆうに連れられて来たものの、傍にいて見ているだけであった。
「仏様に手を合わせてみては」と勧められても、気恥ずかしいだのと言って、はぐらかしてきた。平二と日嘉はそれほど親しくもない。所詮、おゆうを通じてお互いを知っているという程度の仲だ。
黙々と山道を歩く二人が妙石庵にたどり着くと、若い僧侶が出迎えた。日嘉の寺の者であろうが、平二は名前を知らない。若い僧侶は、平二の顔を見て「あっ」と声を上げる。
「すまぬが、何か飲むものを。それと…腹は空いているか?」
日嘉が振り返って訊くと、平二は首を横に振った。
「茶を二人分でいい。――さあ、こっちだ」
日嘉は平二に座るよう促した。指差した先には参道に面した平屋建ての休憩所がある。
妙石庵は、日蓮が説法をする時に使った道端の大石と、寺社がある他に、参道を登る者のための休憩所も設けている。休憩所とはいっても、そこには日嘉の他に幾人かの僧侶も暮らしており、信徒を泊めることもある。参拝者たちが座れるように広く作られた縁側は、所々が朽ちていた。
縁側のささくれたところを避けて、隅の方に平二は腰掛けた。少し空けて、日嘉も腰を下ろす。
「何があったのか、話してくれんのか?」
日嘉が話しかけるも、平二は黙ったままだ。
「いずれは話さなければならないことだ。そう黙ったままでは…」
「…おゆうの墓は?」
日嘉の言葉が終わるのを待たずに、平二が言った。
「ん…ああ、妙石庵の墓所に葬った。この参道を下っていった脇にある」
「……」
また俯いて黙ったしまった平二を、日嘉は待った。問い詰めても、きっと答えない。相当に堪える出来事であったのだろう。時間をかけて聞き出すしかあるまい。
「おゆうの父親もそこに入っている。きっと寂しくはあるまい」
そこへ先ほどの若い僧侶が、茶碗を二つ置いていく。日嘉はそれを手に取ると一口啜った。
「そこの岩の話を、平二にしたことはあったか?」
日嘉が参道を挟んで向こうにある、大きな岩を見ながら言った。岩は苔むしていて、太い綱が一周巻きつけてある。
「あれは高座石といって、あの上に日蓮聖人が立って説法をした大岩だ。近隣の村の者がここに沢山集まったそうだ。山に住む龍が、若い女の姿で説法を聞きに来たという言い伝えもある」
平二は項垂れたまま頷きもしない。日嘉は構わずに話を続けた。
「おゆうは毎朝ここで題目を唱えた後、その岩にも手を合わせておったな。幼い頃から父親と、それは熱心に信仰していた。母親を早くに亡くしたから、その供養でもあったのだろう。――あれは控えめであったが、とても信心深く、思いやりのある子だった」
「…何が言いたい?」
平二は、日嘉をじろりと睨みつけた。
「その言い様は、まるでおゆうを殺したことを後悔しろと言っているようじゃないか。いいか、俺は…俺は殺していない!」
平二は、自分の家に逃げ帰ったことを悔やんだ。日嘉は平二を疑っているのだ。自分とおゆうの身に起こったことを話しても信じてもらえるはずがない。元々よそ者であった平二の言うことに耳を貸す者などいるはずがない。いらぬ詮索をされて、山賊であった過去も露呈してしまう。そうすれば自分は死罪にされる。
「そうは言ってない。私はただ…」
「俺におゆうを殺す理由なんてあるか?」
「なら、なぜ何も話してくれないのだ? ――私にとっても、おゆうは娘同然だった。どんな事でもいい、話してくれ」
「……」
平二は、自分を見つめる日嘉の視線を避けるように項垂れた。
「何も言わぬ、でもやってはいない、それでは筋は通らん。お前がおゆうと仲睦まじくしていたことは良くわかっている。儂はお前を助けたいのだ、平二よ」
日嘉は、相変わらず黙ったままの平二を見据えたまま待った。平二が本当に話す気がないのであれば、とっくに日嘉の前から逃げ出しているはずだ。そうせずに黙って座っているのは、行き場がないだけなのか、あるいは話すきっかけを待っているのか。いずれにしても困ったことに巻き込まれているのは間違いないのだろう。
平二は長い沈黙の後、口を開いた。
「……あの晩、日が暮れた頃に帰ってきたんだ。そうしたら、家の中は真っ暗で…」
日嘉は、ゆっくりとした口調で話す平二の言葉に相槌もせず、じっとして聞いた。
「…狐の化け物が、おゆうのはらわたを食っていた。そしたら化け物は、おゆうの皮を、獣の毛皮を剥ぐみたいにして…。それで自分の皮を剥いて、おゆうの皮を…」
そこまで話した平二は右眼を押さえた。あの時のことを思い出すと、右眼が熱くなり始める。
「どうした」と案じる日嘉に向き直った平二は、右眼を押さえながら言葉を続ける。
「…そいつはおゆうの皮を、自分に貼りつけたんだ。そしたら化け物はおゆうの姿になった。そいつは、おゆうの姿で俺の腹を割いて、俺の目玉を食ったんだ!」
そこまで言って、平二は耐え切れなくなったのか、またうずくまってしまった。
体を丸めて唸る平二を、日嘉は黙って見下ろしている。思いもよらない話に、どう答えていいのかわからない。部屋に転がっていた肉塊、散乱した獣毛と毛皮。平二の言う通りなら、あの小屋の惨状もわからないではない。だが、にわかに信じられる話ではない。
「あんたは、信じない…だろうな。俺だって信じられないんだ」
平二はうずくまったままで言った。
「いや、しかし腹を割かれたはずのお前が、なんで、今こうしていられるんだ?」
平二は顔をゆっくり上げると、空いている左手で胸をはだけた。そこには痛々しい傷跡が縦に盛り上がっている。
「その狐の化け物を逃した天狗とやらが、俺を助けてくれた。――昨日、そいつの屋敷から逃げてきたんだ。化け物がうじゃうじゃといるおかしな屋敷から」
時折平二は呻いて、右眼をかばうように押さえる。言葉のない日嘉は、苦しむ平二に声を掛けられずに見つめている。
「あんたは俺の気が触れたとでも思っているんだろう あれほど話せと言っていたくせに、今度はだんまりかよ。――あんただって、今さっき坊さんの説教を聞きに、化け物がここまで来たって言っていたじゃないか? なんで俺の化け物の話は信じない?」
平二は見開いた左眼を血走らせながら、日嘉に食って掛かる。
「そうではない、そうではないのだ、平二よ。ただあまりに突飛な話で面食らっただけだ」
「おゆうは毎日、そこのホトケさんに手を合わせていたんだろう? 俺は一度だって手も合わせてないし、あんたの説教だって真面目に聞いたことはない。なのに、おゆうは殺されて、俺は生きてる。あんたのホトケさんは、おゆうに何もしてくれなかった」
「平二、それは…」
「一体何のために、おゆうはホトケさんを拝んだんだ? ご利益も何もない、貧乏暮しでいいことなんて一つもない、挙句に化け物に殺された。あいつは全然辛いばっかりじゃないか?」
平二は興奮するに従って、右眼がどんどん熱くなっていくのを感じていた。右眼を中心に顔がどんどん火照っていくのがわかる。
鼻の奥から何か垂れてきた。血だ。ずっと熱くなる右眼を閉じたままで我慢していた平二は鼻血を垂らし始めた。
「平二、お前、鼻血が出て…」
日嘉が心配そうに言うものの、平二は意に介さず言葉を続けた。
「それとも、俺が拝まないから罰でも当てられたのか? ならなんで拝まなかった俺が殺されない? 俺は、俺は…」
鼻血を手で拭うと、平二は両手で顔を強く押さえた。
血を滴らせながら喋る平二の剣幕に、日嘉は気を殺がれてしまった。初めは平二を疑った。おゆうを手に掛けた平二が、持ち物を取りに帰ってきたのかと思っていたのだ。化け物の話を始めた平二は、作り話でこの場を取り繕うつもりなのかもと思った。いずれ自分の目を盗んで逃げる気なのだろうと。
しかし先程から様子がおかしい。食われたと言った右眼の辺りを押さえて、鼻血を垂らして必死に訴えている。もしも平二の言っていることが本当だとすれば、なんとむごい話であろう。
「平二よ、おゆうはいつも、お前のためにお題目を上げて手を合わせておったよ。――お前と良く暮らせますように、お前が元気でありますようにとな」
日嘉はうずくまる平二に向かって言葉を掛けた。
「拝んだからと言って、必ず報われるわけではない。かといって、おゆうが毎日お題目を上げて手を合わせてきたことも無駄でない。ましてや神仏は、滅多なことで罰を当てたりはせん」
日嘉は、うずくまったままでいる平二の背中に、そっと手を置いた。
「神仏に手を合わせるというのは、教えを請い、よりよい生き方を学ぶことだ。人は生きているだけで罪を重ねていく。肉を食う、魚を食う、畑を耕せば虫だって殺す。他者と交わればちょっとした事で争いになるし、お互いを傷つける。だから神仏に学んで、良い生き方とは何かを知らねばならない」
日嘉は、ゆっくりと平二に言い聞かせるように話す。
「そうやって学ぶうちに、他者の幸せを願えるようになる。共に生き、共に栄える。皆で互いの幸せを願いあってこそ、真に幸福になれるはずだ。神仏に拝むというのは、そういう生き方をすることだ」
いつの間にか顔を上げていた平二が、怒気を含んだ調子で言った。
「なら、俺がおゆうのために拝まなかったからか…? そのせいであいつは死んだか?」
「そうではないよ、平二。決してそうではない。おゆうが、お前を生かしたのだ」
「…?」
「あれは、いつも人の事を気にかける優しい娘だった。平二、おゆうはお前のこともよく気にかけておったよ」
「……」
「おゆうが怪我したお前を連れ帰って介抱しているのを知ったときは、随分と心配した。怪我人とはいえ得体の知れぬ男だ、私は役人に知らせるべきだと言ったがね、おゆうは聞こうともしなかった。――あの時、お前を助けたのが、おゆうでよかっただろう?」
平二は、無言で小さく頷いた。
「でもそれは、おゆうにとっても同じだ。父親を亡くしたばかりだったおゆうは、お前が元気になるにつれて、自身も笑顔を取り戻していった。傷の癒えたお前がここに残る事になった時、おゆうは本当に嬉しそうだったよ。だから私は、お前たちが夫婦になることに反対しなかった。――あれはな、平二よ。お前を救って、自分のことも救ったのだ」
右眼を押さえたままの平二を見据えると、日嘉は静かに言った
「――だから、今度もお前が救われたのならば、おゆうもそれを喜んでいると思ってやりなさい」
平二は、自分がおゆうと一緒にいることを、日嘉が疎ましく感じているのだろうと思っていた。よそ者である自分が、村役人に突き出されることもなく、おゆうと暮らしていけたのは、そういう訳があったのかと初めて知った。
「……おゆうはいつも人の世話ばかりでさ。お人好しで、いいように利用されてばかりで、頼まれたら嫌だと言わない。だから、人より多く働くくせに、いつまでたっても貧乏なままだった。――だから俺が、あいつのために何かしてやれたらって思った。なのに、おゆうが……、おゆうが殺されるのに、俺は何も出来なかった。化け物の眼に睨まれたら、ちっとも体が動かなかった」
平二の左眼から、一筋の涙が頬を伝って落ちていく。
「おゆうは言ったんだ、自分が食われているのに、――俺に逃げろと言ったんだ。助けて欲しかったろうに。なのに俺は…俺は…あぁ…」
平二は縁側から崩れ落ちて、地面に膝をついて嗚咽を漏らす。
抑え切れない感情とともに、また右眼は熱さを取り戻していく。
感情の高ぶりとともに、右眼が熱くなることを既に平二は理解していた。怒り、恐怖、悲しみ、抑え切れない感情に合わせて、右眼は熱を帯び、体中の血潮が燃える濁流のように駆け巡っていく。
とにかく、日嘉に右眼のことを悟られてはいけない。知られれば、役人に捕まるどころではない。平二は必死に自分の着物の袖を咥えて、嗚咽する声を飲み込もうとする。
平二がまだ落ち着きを取り戻せないうちに、参道の遠くから人の声が聞こえてきた。
「そこにいるのは、平二か?」
声のした方向に平二は顔を向けた。参道の麓側から、七、八人程度の人影が登ってきている。手には柄の長い刺又を持つものや、刀を持つものまでいる。一群の先頭には、先程平二たちに茶を出した若い僧侶がいた。門前町のご番所から、役人を連れてきたのだ。いや、役人だけでない、あの小屋の様子を知っていた役人は、用心のために、腕の立つものを数人引き連れてきたようだ。
ようやく落ち着き始めていた胸の鼓動が、また激しく打ち始める。先ほどの悲しい感情よりも、今は怒りのほうが大きい。日嘉は自分をここに留め置いて、使いに役人を呼びに行かせたのか。さっきの話は全て嘘か。そう思うと、怒りの感情は右眼を焦がすほどに燃え上がらせる。
「あんた、騙したな!」
平二が言うのと同時に、日嘉が立ち上がって叫んだ。
「一体如何なる沙汰で、そのような物を持ってここへ来た?」
「日嘉上人、その男から離れてください!」
若い僧侶が日嘉に向かって言う。
「刀など持ってくるとは。お主らは霊山である身延山で人斬りをするつもりか? ――平二には、私が話を聞いておる。だから……」
話す日嘉の言葉を遮るように、一群の先頭にいた男が声を上げた。
「そうはいかんよ、上人様。こいつがここにいるってことは、あの家にあった亡骸は、おゆうって女のものってことだ。しかも三日も行方を眩ましていたのは、どういう了見か。どうあっても、ここは引けねえよ。番所へ連れてって、俺たちが詮議する」
男は前に出て、持っていた刺又を平二に向けた。
「平二よう、おとなしく一緒に来い」
平二は、男を何度か見たことがある。村役人の一人だ。この男は、平二がおゆうを殺したと思い込んでいる。門前町の番所へ連れて行かれたら、尋問と称した拷問を受けて、そのままなぶり殺しにされるだろう。代官所の目の届かない田舎町の番所なら、そのくらいは日常茶飯事だ。
「待て! 待ってくれ」
日嘉は、役人の男を止めようと、平二との間に割って入った。
今はもう、とても平二がおゆうを殺したとは思えない。平二の話を全て鵜呑みにできる訳ではないが、何か深い事情があることには違いない。
間を詰めてくる役人たちを前にして、平二を庇うようにして立った日嘉は、背後から平二の呻く声を聞いた。その声の出処を中心に、周囲の雰囲気がどんよりと重くなっていく。平二から漂ってくる只ならぬ気に、日嘉も思わず振り向いた。
平二は頭に巻いていた手拭いを、いつの間にか手に持っている。平二の殺気が、渦を巻くように押し寄せてくる。
尋常でない様子の平二に、役人たちも足を止めた。
「俺じゃない、俺が…」と平二が呟く言葉は、誰の耳にも届いていなかった。
裏切られたことへの怒りが、感情を極限まで高ぶらせる。天狗の眼が放つ妖力のせいか、平二の怒りは殺気の塊となって、周囲の者を圧倒する。
平二は顔を上げて右眼を開いた。赤い色の世界が広がっていく。日嘉も、役人たちも、平二の視界の中で真っ赤に染まっていく。先頭で平二に刺又を向けていた役人の男が、その場にへたり込んで失禁した。それに続いて、他の者たちもその場に倒れていくと、呆けたように口を空けて固まってしまう。
日嘉は辛うじて立っている。平二が右眼を見開いた瞬間、その殺気に飲み込まれるように、身動きができなくなった。息を吸い込むこともできない。背筋に冷水を浴びせかけられたかのような衝撃と、手足をがんじがらめに縛られている圧迫感、そして口の中に泥を流し込まれたかのように息ができない。日嘉は焦りを覚えながらも、必死に頭の中で題目を唱え続ける。
平二は太秦坊の屋敷の時のように、体が燃えるように熱くなっていくのを感じていた。鼓動はどんどん早くなり、体中から汗が吹き出していく。異様な様子を見られてはいけないと思いながらも、自分ではもう、どうにも抑え切れない。
日嘉は、平二の体が徐々に赤銅色になっていくのを見た。身動きが取れぬままに、目に映る怪異な光景を眺めている。尻餅をついたままの役人は呆けたようであっても、顔は真っ赤だ。息を吸えぬままなのだろうか、目は既に白目を向いている。
日嘉は、腹の底から渾身の力を振り絞った。たった一度、平二に届く声を出せればいい。もうそれぐらいしか、出来そうにないのだ。
「キイエェェェ――ッ!」
振り絞るように吐き出した気合で、日嘉が一気に体の自由を取り戻した。絡みつく平二の殺気を押し返すように、両手を向けて振り出すと、両こぶしに乗せる様に再び気合の叫びを発した。
「イエェヤ――ッ!」
その貫禄にたじろいだのか、平二が尻餅をついたように倒れる。
すると役人たちの呪縛が解けて、次々と息を吹き返す。なかにはその場で吐瀉する者もいた。
先頭にいた役人が「ひぃーっ」と絶叫しながら逃げ出すと、皆、我先にとそれに続く。
日嘉は、仰向けに倒れた平二に、両手のこぶしを向けたままじっと動かない。そのままでいると、平二の肌がゆっくりと元の色に戻っていく。
平二が、仰向けのままで口を開いた。
「――騙した…のか?」
「平二、その眼は……」
平二は仰向いたままで動かずにいる。両眼を開いて空を見る。左眼と右眼に映る空の色が違う。右眼で見る空はやはり赤い。夕焼け色ではない、血の赤色だ。
日嘉は、両腕を平二に向けたままで話しかけた。
「平二、聞いておるか?」
「騙したのか……?」
掠れた小さな声で、平二が言う。
「平二よ。あれらは私が呼んだのでない。そうではないのだ」
「……」
日嘉は、自分と役人の間に割って入ってきた。平二を連れて行くなと言っていた。なら、日嘉が役人を呼ばせたのではないのだろう。
いずれにせよ、もう、ここにはいられない。おゆうと暮らした家に戻ることも、元の暮らしに戻ることもできない。何より、おゆうはもういない。
平二は呼吸を整えるよう軽く深呼吸をすると、右眼を閉じて体を起こした。突然動き出した平二に、日嘉は姿勢をくずさぬまま後ずさりする。
平二は、ゆっくりと役人たちが落としていった刀のある方へ歩いて行くと、何本かを品定めするように鞘から抜いていき、その中で一番軽く小ぶりな一振を選んで腰帯に差した。
「俺はここに来る前、ずうっと遠くで山賊をしていたんだ。山狩でお侍に追い立てられてさ、ここまで逃げてきた。そこをおゆうに助けられたというわけだ。――あいつには最後までそのことは話せなかった。それでも俺と夫婦にまでなっちまうんだからさぁ、あいつは本当にお人好しだ」
そう言って平二は、腰に差した刀を抜いて、刀身に自分が映るよう目の前にかざす。
「あいつは、お人好しっていうのはいいことなんだって言ってた。人に優しくできるのはいいことだって。そんなのは、字も禄に読めない俺にはわかんねえよ。――でもさ…、」
平二は刀を自分の頭にやると、後ろから首筋に近づけた。
「へ、平二っ!」
日嘉が叫んだにも関わらず、平二は手を止めない。
空いている手で自分の髷を握ると、平二はそれを根本から刀で切り落とす。髷を落とした平二の髪はざんばらになって、その毛先が肩に落ちた。
「俺はまだおゆうに何もしてやれていない。だからせめて、あいつの仇を取らないとな」
切り落とした髷を日嘉に差し出すと、平二は深く頭を下げた。
「これを、おゆうの亡骸と一緒にしておいてくれないか? あいつが寂しくないように」
日嘉が、差し出された髷を受け取る。
「お前はどうする? 仇を討つと言っても…」
「化け物に食われた右眼の代わりに、天狗が目玉をくれた」
平二は閉じたままの右眼を指さして言った。
「この眼で見ると…化け物の姿が見えるんだ。これで、仇の――狐の化け物が倒せるらしい」
日嘉は平二の話に戸惑った。天狗に助けられたと言うのを、話半分で聞いていた。この妙石庵に祀られている妙法大善神も、元は天狗であったという。平二を助けたという天狗も、果たして身延に連なる山の神であろうか。如何にも平二の赤く光る眼と尋常ならざる殺気は、およそ人のものとは思えない。
平二が手に持った刀を上げると、「ごめん」と言って、日嘉に刃を向けた。
ぎょっとする日嘉に、平二が言った。
「また役人たちが来ると厄介だから、着物だけ、だましで切っておく」
そう言うと、日嘉の膨らんだ袈裟の袖に刃をあてて、長い切れ込みを入れる。
「その着物は、俺に逃げられた時に切られたことにしてくれ」
刀を鞘に収めると、振り返った平二は、ゆっくりと参道を登りはじめた。日嘉はその様子をじっと見つめている。
何か言わねばと、日嘉は平二の名を呼んだ。平二は、その場で立ち止まるが振り向かない。
「平二よ! その…、いつかまたここに帰って、おゆうの墓を見舞ってやれ」
平二は応えず、また歩き始める。
日嘉は、去って行く平二の姿をずっと見つめていた。