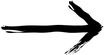天狗の眼(上) 二、逃避行 1幕 2幕
※
萬澤宿は比較的大きな宿場町だ。身延山へ続く街道のなかでも、萬澤宿からの道のりは次の宿場までは三里半もあり、しかも険しい山中を行く。そのため駿州往還を行く旅人は、大抵この宿場に泊まる。宿場には、旅籠と呼ばれる旅人向けの宿や茶屋、土産物を売る商店の他に、武家や公家が泊まるために作られた専用の宿泊施設もある。
街道から宿場町に入るところには、大きな門戸が設けられており、夜間には防犯目的で閉められる。平二たちが萬澤宿に入ったのは、この門戸が閉められる、ぎりぎりの時間であった。
門戸をくぐって、まず困ったのが一目の事だった。あまりに人離れしたその体格に、行き交う人が皆振り向いてまで注目する。平二に比べたら頭三つ分は高く、胴の太さは平二の二人分以上ある。振り返ってまで眺める人々の目に耐え切れなくなったのか、円狐は、門戸を入ってすぐの茶屋に入ろうと言い出した。
「入るのはいいが、金はあるのか?」
平二は毛皮の胴服と、錆びた太刀以外は何も持たされていない。太秦坊の元を離れてから気にはなっていたのだが、路銀は円狐が持っているのだろうか。
「まあ、その事は心配しなくていいさ。―とにかく一目をどこかに座らせるんだ。『人』にじろじろ見られるのは寒気がするよ」
そう言って、円狐が茶屋の暖簾をくぐると、一目も入っていった。渋々、平二も後に続く。
茶屋の中には男二人の客が一組と店主がいるだけだが、よほど平二たちが奇異なのか、皆呆けた顔で眺めている。涼やかな顔をした美人に、天井に届く程の大男、そして片目を隠して太刀を差した男が連れ立って入ってきたのだ、驚くのも当たりまえである。
円狐が空いた座敷に腰掛けると、相対する様に平二も腰を下ろす。すると一目の尻が収まるほどの余地が残っていない。仕方なしに一目は、そのまま地べたに座り込む。
その様子を心配そうに見守っていた店主が、座布団を一枚持って来た。差し出された座布団に、一目は首を横に振って拒んだ。
「あの、皆さん身延からのお帰りで?」
店主が誰とでなく声を掛けた。ここの宿場町を通る旅客のほとんどは、身延山参拝が目的なのだ。その問いに円狐が口を開いた。
「いや…まあ、そんなところかねぇ」
「違うので?」
しつこく問いただす店主に、平二が言った。
「この先のさ、温泉で湯治をした帰りだ。俺たち二人は姉御のお目付け役というか、まあ用心棒みたいなもんだ」
「はあ…」
「うちの親分が嫉妬深いもんだから、見栄えの悪いのをお供にってことさ。これなんか、でかいから驚いただろ?」
平二の言葉に合わせて、一目が店主に向けてにんまりと笑顔を作る。それを見た店主は、「ひっ」と声を上げて一歩退いた。
「とりあえず酒を三つくれ。あと何か食い物はあるかい?」
「ええ、今からだと蕎麦ぐらいしか…」
平二が円狐と一目の顔を交互に見ると、いずれも首を横に振った。
「なら、俺だけでいいや。それを一つくれ」
店主はあいよと言い残すと、奥の厨(厨房)へと消えていった。茶屋にいたもう一組の客も、店主がおとなしく引き下がったのを見て安心したのか、また会話を始めた。
「一体、今のは何だい?」
円狐が平二に小声で訊いた。
「ああ、あんたがやくざの親分の妾で、俺と一目がその用心棒ってことだよ」
「なんで、あの男はそんな事まで訊くんだい?」
「俺らが怪しい風体だからだろ。あの店主も、おかしな奴が来たら役人に届けなきゃならんから。まあ、ちゃんと理屈が合えば、あの店主もうるさく言わんよ」
「そんなもんかい?」
「そんなもんだ。それより、少しばかり細かい金をくれ」
「……?」
「ここの主人に心付けをする。いろいろ訊くのと、口止め分と」
それを聞くと、円狐は袂に手を入れて、いくらかの銀貨を取り出した。それを見た平二が「おおっ」と声を上げる。結構な大金だ。それに構わずに、円狐は差し出された平二の手に銀貨を落とす。
「それにしても、あたしが妾っていうのは気に喰わないよ」
「そう言ったら、あの主人はすぐに納得しただろ。あんたの見掛けはそういう風なのさ」
円狐は、鼻をふんっと鳴らしてそっぽを向いた。
すると早速、店主が酒を持って来た。小ぶりな湯のみ茶碗に入った酒を一人に一つずつ置いていく。店主が全部置いたところで、平二が声を掛けた。
「ご主人、蕎麦はひとついくらだ?」
「へぇ、二十文ですが」
少々高い気もするが、旅先の茶屋なら仕方がない。
「そうか、じゃあこれなら酒と合わせても足りるかい?」
平二は店主に先ほどの銀貨一枚を握らせた。店主がそれを見て「おおっ」と、先ほどの平二と同じ様に声を上げる。
「これじゃ、多すぎますよ」
「まあ、姉御がいいって言うからさ。これより細かいのを持ち合わせてないんだ。取っといてくれよ」
店主は円狐に頭を下げて礼を言った。それを平二がまあまあとなだめて、蕎麦の用意に戻らせる。
「これでもう余計な気を回すこともないだろ。――ところで、何でこんなに金を持ってるんだ?」
「お前はそういう事を気にしなくていい。――それより、ほら」
店主が盆に蕎麦を載せて戻ってきた。ざるに盛った細切れの蕎麦に、真っ黒い汁が添えられている。平二は、箸で蕎麦を汁につけると、ずずっという音とともに勢い良く啜った。汁は醤油と出汁を混ぜた辛口だ。咀嚼すると香ばしい蕎麦の味と、濃い醤油が交じり合って口内に広がっていく。汁は大根汁で薄めており、独特の臭味と辛味もある。それがますます食欲をそそる。
平二は、思ったよりも自分が腹を空かしていたことに気がついた。蕎麦を啜る瞬間まで、自分が空腹であったことを忘れていたのだ。もう何日も食べていないはずなのに。
「そうだ平二、忘れていたことがある」
黙々と蕎麦を啜る平二に、円狐が話しかける。
「お前、腹が減らないだろう?」
「…?」
「物怪ってのは腹が減らないんだよ。食べない訳じゃないけど、食べなくても死ぬ訳じゃない。だから味わう以外の理由で、何かを喰ったり飲んだりしない。でもお前は、『人』だ。きっと自分の腹が減っていることがわからなくなるはずだって、山ン本が言っていた」
「…ってことは、俺も喰わなくてもいいのか?」
「さあ、どうなんだい? 天狗の眼をもらった『人』なんて聞いたことがないからね。あたしらが教えて欲しいよ」
平二は自分の腹をさすって腹具合を確かめる。意識を集中すると、強烈な空腹感を感じ始めた。
「おお、なんかえらく腹が減ってきた。一体、どうしたんだ」
「難儀だねぇ。いちいち確認しなきゃ腹が減ったかどうかわからないんだ。――まあ、便利じゃないか、死ぬまで喰わなくていい体になったんだから」
あざ笑うように言う円狐を、一目が上から睨んだ。床に座っているはずなのに、頭の位置は円狐よりずっと上にある。
一目の視線に気付いた円狐は軽く咳払いすると、着物の袂から竹の皮でできた包みを取り出した。
「で、これが忘れていたものさ」
平二が包みを解くと、中から握り飯が二つ出てきた。
「お前に喰わせるようにって持たされたんだ。渡すのを忘れていたよ」
とっくに蕎麦を食べ終えた平二は、包みを開けると握り飯を頬張った。何日も食べていない胃袋は、まだまだ空腹を訴えている。
あっという間に二つの握り飯を食べ終えると、平二は円狐に向かって言った。
「たくっ、こんなに腹が減っていると思わなかった」
「腹が減るのは生きている証拠だよ。よかったねぇ」
「お前なぁ、芭尾を見つける前に、俺が飢え死んだらどうするつもりだ」
「だからその前に喰わせてやったろう。その蕎麦だって、あたしの奢りだよ」
どうにも怒りが収まらない平二を見て、円狐はおかしくてたまらないとばかりに、口元をにやつかせている。
苛立ち紛れに、竹皮を握りつぶそうとした平二を円狐が止める。
「おっと、その包みは捨てるんじゃないよ」
円狐は平二から包みを取り上げると、丁寧に畳んで袂にしまった。
そこへ店主が酒の入った大きめの徳利を持ってきた。
「さっきのお代じゃ、ちょっと多すぎますからね。お客さん、もう少し飲まれるでしょう?」
店主はそう言って、既に空いた平二の碗に酒をついだ。
「おやじさん、俺たち、まだ今日の宿が決まってないんだ。どこがいいかね?」
「今の時期だと、お大尽が泊まる脇本陣が空いてるんですが、あそこは今ちょっと…。まあ、伊都屋さんがいいですよ、あそこは飯もうまいし」
店主は平二の問に答えながら、一目と円狐の碗に酒を注いでいく。
「脇本陣って?」
「この宿場はね、小さいけれど江戸の方から身延参りに行くお偉方も通るんですよ。脇本陣はそういう方々が泊まるんです。空いている時は、誰でも泊まれるんですけどね。それが今はちょっと…」
物言いたげな店主の様子に円狐は業を煮やしたのか、自ら店主に声を掛けた。
「いいじゃないか、教えなよ」
すると店主は、身を乗り出して話し始めた。
「いやね、ここだけの話ですよ。今、脇本陣には異人さんが一人で泊まっているんですよ」
店主の言葉がよく理解できなかったのか、円狐が「はぁ?」と声を上げる。その素っ頓狂な声に、別の席の二人組が振り向いた。
「お客さん頼むよ、静かに。これはね、言っちゃいけない事になっているんですから」
そうは言いながらも、店主も本気で嫌がっている様子ではない。
「その異人さんね、昨日から体を壊して寝込んでいるんですよ。これがまた酷いらしくて…」
「どうして異人がこんな所に一人でいるんだ?」
「それが…」と店主が言おうとしたのを遮って、円狐が声を上げた。
「異人てのは、南蛮からきた奴らのことだろ? なんでこんな所にいるのさ?」
一度に幾つも質問された店主は、手応えの良さに調子に乗ったのか、どんどん冗舌になっていく。
「それがね、その異人さんは南蛮じゃなくて、もっと遠い『いたりあ国』ってところから来なすった切支丹の先生らしいです。お役人や他の異人さんとで、富士山参りやら温泉の帰りだったとか。それが急に病にかかったもんで、役人さんともう一人の異人さんが、医者を連れてくるって、慌てて行っちまったんですよ」
「それで、その病気の異人はここにおいてきぼりか」
「そりゃ本当は、役人さんが一緒にいないといけない。異人が一人でいるなんて、許されることじゃないでしょう。でも世話役の役人さんは一人だけだ。だから、脇本陣で臥せってる異人のことは内緒なんですよ」
「でも、ここの番所にだって役人はいるじゃないか?」
そう言う平二に向かって、店主は手を横に振って否定する。
「いやいや、ここの役人さんは異人さんの世話などできませんよ。言葉もわからないし、そもそもおかしな病にかかった異人なんて、誰も近寄りたがりません。だから宿に閉じ込めてそれっきり。食事だけは運んでやっているらしいですけどね」
頬杖をついて話を聞いていた円狐が言った。
「なんでわざわざ遠くまで医者を呼びに行ったんだい? ここいらにも、医者はいるだろうに」
「それが日本人の医者じゃ役に立たないって、異人の医者を連れに戻ったんですよ」
「…ふーん」
「それが昨日の話です。随分と慌てて三人で出て行きましたから、あと四、五日でお医者様と戻るでしょうね」
「三人? あんた役人一人と異人がもう一人って……」
「ああ、そうだ。言っていませんでした。それがね、この異人さんたち、この宿場に来る途中で若い女を助けたとか。追い剥ぎにあって身ぐるみ剥がれた素っ裸の女ですよ。その女も一緒に行きました。あれは、異人が妾にでもするつもりですかねぇ…」
そこまで聞いた平二は、手に持っていた銀貨を、飯台の上にばらばらと音を立てて落とした。
「おやじ、その話さ、女の事をもっと聞かせてくれよ」
平二の声色が変わったのに気付いた店主は、少し喋りすぎたかと焦りを覚えた。
※
茶屋の店主の話はこうだ。
日が暮れて宿場の門戸が閉まる寸前、ちょうど平二たちと同じような時間に、その異人たちは宿場にたどり着いた。二人の異人は見たことのない着物に身を包み、うち一人は一目程ではないにしても、相当に大柄であった。二人には役人が一人同道しており、その役人は到着するなり、件の女を連れて番所へ行ったという。
他に店主が知っていたのは、その女が異人に着物を買い与えられていたことぐらいだ。日が暮れた後にも関わらず、無理に店を開けさせたらしい。
宿場には、大名や旗本、役人が宿泊するための本陣と呼ばれる施設がある。萬澤宿の本陣は、宿場の有力者の居所がその役を担っていた。お万の方以来、徳川将軍家の奥方には法華経を信奉する者が多く、身延山参拝に来ることも多い。そのため、小さな宿場町とはいえ、本陣はそれなりに立派な構えになっている。
脇本陣は、本陣の予備的な施設で、本来は宿場町で別の藩同士がはち合わせた時に、格式の低い方を泊めるために用意されている。しかし、参勤交代で萬澤宿を通る藩は滅多にいないため、大きめの宿を形式的に脇本陣と呼んでいた。その方が高い宿賃が取れるからだ。そのため脇本陣は、宿場の大きな宿が、一年毎に持ち回りでその役を引き受けている。
本来なら役人が同道しているので本陣に泊めるべきなのだろうが、異人が二人もいるので、今年の脇本陣である森田屋に泊めろという事になったらしい。同道していた役人も、宿場の連中の考えをわきまえたのか、一切文句は言わなかった。
平二は店主に頼んで、その脇本陣に一番近い宿を手配させた。銀貨を四つ渡して三つは宿代、一つはお前の手間賃だ、と言うと、奥にいる誰かに声をかけて、すっ飛んで店を出ていった。
戻ってきた店主が案内したのは、脇本陣である宿の隣、木谷屋と呼ばれる宿であった。宿の主人は一目を見て驚いていたが、やはり商売人なのか、気前の良い客には愛想が良い。大きいお客様がいるからと、宿で一番広い部屋に通された。食事を持ってくると言う主人に、酒だけ持ってくるよう伝えると、早速部屋に徳利と茶碗が運ばれて来た。
平二は部屋に寝転んで酒を飲み始めるが、円狐と一目は、なぜか離れたところに座って、平二の方を睨んでいる。
「ん、あんたらは飲まんか?」
「……」
円狐と一目は、黙ったままで答えない。まあ一目は滅多に喋らないから、はじめから答えは期待していない。
しばらく平二が寝転んで酒を飲んでいると、円狐が口を開いた。
「…その刀、あっちにやっとくれよ。嫌気がするんだ」
円狐は顎で、平二が腰から抜いた太刀をさし示した。太秦坊から貰った錆だらけの太刀だ。先程寝転んだ時に、畳の上に転がしたままだった。
「これか? これがどうしたって言うんだ?」
「山ン本からもらった、『物怪を殺せる刀』だろ。とにかく気味が悪いんだよ、それ」
平二は体を起こして太刀を拾い上げた。
「どういうことなんだ? こんな錆だらけの太刀なんぞ…」
「それはね、人を斬った刀だよ。しかも一人二人とかの数じゃない」
円狐は目を細めた。
「多分、昔の合戦か何かで使われたんだろうね。沢山斬り殺した分だけ、『人』の恨みつらみがこびり付くんだよ。――山ン本も、なんでこんなもの持っていたのかねぇ」
円狐は同意を求めるかのように一目を見る。それに気付いた一目は、小さく舌打ちをしただけだ。
「そういう刀ってのは、邪な力を持っちまうのさ。そうなると、物怪だって切れるようになる。――とにかくさ、そいつをあっちにやっておくれよ」
「ああ」と返事をした平二は立ち上がって、刀を部屋の隅に立てかけた。それを見た円狐たちは、徳利の方へ寄って来る。平二は空いた茶碗に酒を注いで、円狐と一目に渡した。
「それでさ、聞こうと思っていたんだが、その妖力とかってのは一体なんなんだ?」
円狐は茶碗の酒を一口啜ると、わざとらしくため息をついた。
「ふぅ、そんな事も教えてやらなきゃいけないのかい。――お前、自分がなんで生きてるのか、考えた事あるかい?」
「……?」
「生き物ってのは、なんでも生きるのに力が必要。心の臓を動かすのにも力を使っているんだ。『人』は力を得るのに、いろいろ喰うだろう?」
平二は頷く。
「物怪はね、さっきも言った通り、物を喰わなくていい。その代わり、妖力で生きるんだ」
「で、その妖力はどこから持ってくるんだ?」
円狐は、平二のその質問に、少し沈黙してから答える。
「……まあ、手っ取り早いのは『人』を喰うことだね」
平二はその言葉に顔をしかめる。
「芭尾の奴は、そうやって強い物怪になった。――でも、あたしらは違う。山ン本はもう何百年も、『人』を喰うことを許してないし、あたしらもそれに従っている」
「なら、どうやって……」
続けて疑問を呈する平二の言葉を遮るように、円狐が言った。
「あたしらもよく知らないのさ。ただ山にいると妖力が減ることがない。でも、こうやって人里に降りてくると、どんどん妖力が減っちまうのさ。だから…」
そう言って円狐は、袂から小奇麗な巾着袋を取り出した。
円狐が袋を明けて取り出したのは、干からびた木の実や豆の様なものだった。円狐はそれを一つ摘むと、口に放り込む。何度か、かりこりと口の中で砕いて酒で流し込んだ。
「こうやって山のものを食べると妖力が湧いてくる。たくさんじゃあないけどね。腹が減るわけでないから、食べるのは少しでいい」
一目も円狐と同じように袋の中身を拾い上げると、ばりぼりと音を立てて食べた。
「なんだか、よくわからねぇよ。――それで、俺もその不味そうなもんを喰ったほうがいいのか?」
「馬鹿を言いよ。お前はさっき蕎麦も握り飯も喰ったろうに。もう腹は膨れただろ?」
「でも、妖力とかいうのはいいのか?」
平二は自分の右の眼を指差した。
「そんなの知らないよ。言ったろ、お前みたいのは、あたしらも初めてなんだって。――とにかく、腹が減ってなければいいじゃないか」
平二は「そうかい」と答えて、また寝転がった。確かに腹は膨れているし、右眼におかしな様子はない。
「それよりさ、異人のことはどうするんだい?」
円狐が茶碗を空にして言った。平二はその碗に酒を注いでやる。
「脇本陣には、異人以外は誰もいないんだ。だったら、黙って入り込んじまえばいいだろ」
「で、入り込んだ後は?」
「そいつに女の事を訊くんだろ」
「お前…、異人の言葉がわかるのかい?」
「そんな訳ないだろ、読み書きもできないのに」
さも当たり前だ、というふうに答える平二の言葉に、円狐は大きくため息をついた。
「馬鹿だねぇ。じゃあ、どうやって女のことを訊くんだい?」
「さあね、とにかくその異人に会ってみようじゃないか。もしかすると、俺らの言うことがわかるやもしれん」
「なんでそう思うのさ?」
「言葉もわからん奴を、一人で残していくとは思えん」
円狐は呆れた表情で鼻を鳴らした。的を射たような言いぶりだが、大した根拠はあるまい。
「夜が更けたら隣へ忍び込む。――俺と円狐の二人でいいよな?」
平二は一目を見やった。体の大きな一目では、夜だと言っても目立ちすぎる。
「…いや、二人じゃないよ」
平二の提案に、円狐が低く冷たい声色で答えた。
「お前とあたし――『人』は一人だ」
平二はうんざりした表情を隠そうともせず、「はいはい」と言って返す。
あてつけがましい返事も、円狐は涼しい顔で受け流した。
なんとなく円狐と眼が合った平二は、思い出したように口を開いた。
「…ところでさ、ひとつ聞いていいか?」
「…?」
「あんたら、『人』を喰ったことはあるのか」
平二の言葉に、円狐と一目は全く動じない。だが全く動く様子もなく、じっと黙っている。重苦しくなった雰囲気に耐えられなくなった平二は、思わず言葉を発した。
「いや、言い難いことならいいんだ。――ただ、なんとなく…」
少々慌てた風の平二に向かって、円狐が言った。
「…お前は、それを訊いてどうする?」
「……」
円狐の言葉に平二は黙ったまま、唾を飲み込んだ。
「人を喰う物怪は退治するってのなら、いつでも相手してやるよ」
平二を見つめる円狐の眼は冷たい。前髪から覗いた表情は、面が張り付いたように感情の色がない。先程まで会話を交わしていた相手のものとは、とても思えなかった。
その様子に、平二は右眼で見た円狐の姿を思い出した。姿が『人』だから意識していなかったが、目の前にいるものは、人外の化け物なのだ。
黙ったまま立ち上がった平二は、先程立て掛けた太刀のところに行くと、一言「寝る」と言って、太刀を抱えて横になった。
一目が舌打ちした音が、寝そべった平二の耳にも聞こえてきた。
天狗の眼(上) 二、逃避行 1幕 2幕