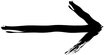天狗の眼(上) 三、道連れ 1幕 2幕
三、道連れ
ミケーレ・ラブティが日本に来たのは、一八六六年の春、半年ほど前のことだ。
イタリアの教会で神父をしていたミケーレは、三十歳の誕生日を迎えたことを機に、イエズス会が派遣する、未開地への布教活動に参加する決意をした。
港町のアンコーナで生まれたミケーレは、幼いころに親元を離れて、近隣の聖地ロレートにある修道院で暮らした。ロレートには、イエス・キリストの出身地であるナザレより天使が運んだという、聖母マリアが暮らした家が、そのまま安置されている教会がある。聖地とは言ってもローマから遠く、目立つ産業もない片田舎だ。ロレートに住む者のほとんどは、アンコーナに出稼ぎに出ている。
修道院での生活は清貧を強いられたが、自給自足が成り立っている田舎の生活では、餓えることはなかった。不自由なく信仰生活を邁進できることは、キリスト者にとって最も望むべき環境であった。祈りと共に息を吸い、神の教えに思いを廻らせる日々は、最上であると言っていい。
だからこそ、信仰と自分の境遇の間に生じた矛盾に悩んだ。何不自由なく恵まれている、それは信仰者としては貧しく惨めではないか。居心地の良い毎日に溺れ、このまま信仰の本質を見失うことを恐れた。日々の安心の代償を、自分に鞭打つ程度の痛みで賄っていくのは、あまりに安直すぎる。自己犠牲を是とする教えを説く自分は、一体何の犠牲を払うのだろうか。
そう思い始めた矢先、ミケーレの元にイエズス会から一通の手紙が届いた。それは、極東アジアに派遣されるフランス軍への、同行の誘いであった。近年イエズス会は、往来が活発になった極東アジアに向けて、頻繁に宣教師の派遣を行なっている。フランス軍は、キリスト教徒への弾圧を行う国に対しての外交交渉、また信徒の安全確保のために派遣されるという。ミケーレは、この誘いを二つ返事で引き受けた。苦悩する自分に試練が与えられた、殉教の精神が受け入れられたのだと思った。
行先は日本という、極東アジアで最も東にある島国だった。
四ヶ月近くにわたる船旅を経て、地球の裏側までやってきたミケーレを待っていたのは、思った以上に快適な生活であった。辿り着いた港から、まっすぐ連れてこられた横浜の外国人居留地は、決して大きくはないものの、存外整備が行き届いている。西洋風の建物が並び、道は石畳で舗装されている。ここに至るまでに、南印度や、澳門の外国人街にも立ち寄ってきたが、横浜居留地も、それらに次いで大きく、全く遜色ない。
不慣れな異国の地に住まう外国人には、原住民の助けが必要だ。ここの教会でも、居留地の外に住む日本人を数人雇っていた。
扁平な顔をした背の低い日本人はよく働く。ミケーレは到着してしばらく、彼らから日本の言葉を習い覚えた。しかし、読み書きは難解らしく、手伝いの日本人にもよくわからないらしい。
居留地に滞在している各国の軍人や商人、政府関係者は、ある程度の制限はあるとはいえ、外部との接触もあり、昼間なら横浜近隣であれば比較的自由に出歩くこともできる。そのため横浜居留地を囲む日本人街には、外国人目当てに物を売る商店が並ぶようになり、幕府の管理下ではあるが、売春街まで用意されている。
しかし日本の幕府は、ミケーレのような宣教師が居留地外へ出ることを厳しく管理していた。。特にミケーレのような宣教師たちは、キリスト教の禁教令のために、不特定多数の日本人と接触することを厳しく制限されていた。居留地の近隣の外に出るには許可が必要で、出れたとしても必ず役人の監視がついた。
日本に来たものの、布教もままならない日々を強いられていたミケーレであったが、ついに居留地から出る機会を得た。オランダ商業使節団の団長であるヨハン・オールトの富士山見物に、通訳として同行できる事になったのだ。西洋人相手の説教に辟易していたミケーレを見かねたオールトが、手を回してくれたのだ。オールトに付き添うのが、いつも教会へ様子を見に来る、相馬長次郎という役人だったことも幸運だった。知った仲であった長次郎も、許可を得るために随分と奔走してくれた。日々滅入った気持ちを奮い立たせて、日本語を学び続けた甲斐があった。
およそ二十日間の旅程で、富士山を間近で見物し、温泉へも行った。長次郎が一緒である以上、宣教師としての布教活動はできなかったが、横浜では見られない日本の様子を窺い知ることもできた。
そうして横浜へ帰る道中、野盗に襲われたという女性を助けた。名前をおふうと言った。それが一昨日のことだ。
身ぐるみ剥がれた彼女を、近くの町まで連れて来た。長次郎は役人に届けたが、事情を聞くと、彼女も東の方向へ行く道中であると言う。それを聞いたオールトは、彼女をエスコートしようと言い出した。はじめは乗り気でなかった長次郎も、いつの間にか届けた役人にも話をつけて、一緒に横浜まで連れ行くと言いだした。
二人の様子はおかしかった。オールトはまるで、十代の少年の様におふうにのぼせ上がった。是が非でも彼女を守るのだと言い張り、彼女の美しさをオランダ語で何度も褒め讃えた。常日頃から、日本人女性を「雌猿」と揶揄していたオールトとは思えない変わり様だ。確かにおふうは美しい女性ではあった。日本人にしては目鼻立ちが濃く、それでいて時折、幼さの残る表情を見せる。小柄で細い体に、肌は東洋人とは思えないほど白い。
だが、長次郎はもっとひどかった。ひどく興奮したように喋りだすかと思えば、また急に呆けたように一点を見つめて黙ってしまう。話していることも支離滅裂で、全く理解出来なかった。
この二人に共通しているのは、とにかくおふうを一緒に連れて行くと頑なに言い張っていることだ。オールトも長次郎も、自分が知らぬ間に気が触れてしまったのだろうか。あのおふうという女性に出会ってから、どんどん二人がおかしくなっていく。
そうした様子を笑顔で見ているおふうは、如何にも気味が悪かった。時折、彼女はミケーレをじっと見つめてきた。まるで何か説き伏せるかの様に、力のこもった視線を向けられる度に、背中に悪寒が走った。眼が合った時など、立ちくらみまで起こしたのだ。訳がわからない感覚に襲われて、正気を保てなくなり始めた頃に、ミケーレは高熱を出して倒れた。指先が痺れて感覚がなくなっていく。その痺れの範囲は時を追うごとに拡がっていき、ついには全身が痺れて動けなくなった。
長次郎は、臥せっているミケーレに「医者を連れてくるから待っていろ」と言った。その横で笑顔のオールトと、冷たい眼をしたおふうが見下ろしている。三人はお互いに言葉も交わさないのに、示し合わせたように立ち上がると、そのままミケーレを置いて出て行ってしまった。
それから、もう丸一日が経った。昼の間に一度、水の入った器と、米を柔らかく煮た味のないスープが運ばれてきたが、あとはずっと一人きりだった。はじめは自分でそれらを口にすることもできたが、もう今では体を起こすこともできなくなった。
ロザリオは、長次郎たちが荷物と一緒に持って行ってしまった。祈りを唱えるものの、縋るもののない寂しさで、心身ともに押しつぶされそうになる。キリスト者である自分は、あれを決して手放してはいけないのだ。それは分かっていたはずなのに。せめて十字架の下で死にたいと何度も後悔した。
虚ろに開いた目で、じっと木張りの天井を見上げる。もうずっとこの光景は変わっていない。体を動かせぬままに寝転んでいるからだ。暗い部屋の中で、自分のか細い息遣いだけが聞こえてくる。きっと、朝を迎えることは出来ない。
死期を確信したミケーレは、祈りの言葉を心の中で唱え続けた。
※
平二と円狐は、存外簡単に脇本陣に入り込むことができた。建物の中には誰もいなかったのだ。茶屋の主人曰く、得体の知れない病で倒れた異人に、誰も近づきたがらないらしい。異人の具合は悪くなる一方で、ついに宿の者たちまで逃げ出してしまった。おかげで平二たちは、人気のなくなった夜中に、鍵の掛かっていない表戸から堂々と脇本陣へ入っていくことができる。
念のため、こっそり音を立てずに中を探るが、人の気配はない。客室のある二階に上がって、一部屋ずつ確かめていく。
「平二、こっちだよ」
円狐は、細く開いた襖から部屋の中を覗いている。円狐の頭越しに平二も中を覗いた。確かに男が一人、布団の上で寝そべっている。
「さあ、お前が言い出したんだから、ちゃんと話しておいでよ」
脇に退いた円狐は、襖を広く開けた。すると異人の早く荒い息遣いが聞こえてくる。天井の一点を見つめるように目を見開いて、呼吸に合わせて胸を上下させている。しかし人が入って来たことに気付いた様子はない。平二は近づくと、布団の傍らに腰を下ろした。
――さて、どうしたものか。
思案するように顎を撫でている平二の肩越しに異人の姿を見下ろしていた円狐は、布団を挟んで平二の反対側に行くと腰を下ろした。
「こいつは酷いや。とても話せるような具合じゃぁないね」
円狐は異人に掛かっている布団を剥ぐと、着ている白いシャツの胸元に手をやった。
「おい、あんた、一体、何してんだ?」
平二の問いに、円狐は鼻をフンッと鳴らして答えた。
「…なんだい、こりゃ。どうやって脱がせりゃいいのさ?」
円狐にとっては初めて見る洋服だ。ボタンの外し方が分からないらしい。
「なんだ、異人の裸が見たいのか?」
薄ら笑いを浮かべる平二に、円狐が睨みを利かせた。
「下種なことを言うんじゃないよ。――こいつ、芭尾の術にやられているのさ」
「どうして分かる?」
「もっと体を見なけりゃ、きちんと分からないさ」
平二は異人の着ているシャツの丸いボタンに手を掛けた。平二にとっても初めて見る西洋の服装だ。ボタンをつまんで引っ張ると、糸が切れて取れてしまった。すると、その部分の合わせがずれて肌が露わになる。それを見た円狐が、他のボタンを指先でつまんでちぎっていく。そうしてはだけた異人の腹の上に、円狐は自分の手を置いた。
「間違いないね、こいつは芭尾の巫蟲にやられているよ」
初めて聞く言葉に、平二は首をかしげた。
「芭尾が好んで使う外道の術さ。『人』の肝やらを絞ったものに妖力を混ぜて、気味の悪い蟲を作る。そいつが体の中に入るとね、物怪だって、体の自由が利かなくなっちまうのさ」
平二が見ても、さっぱりわからない。毛深い異人の胸元には、何らおかしなところは見られないのだ。
「なんでわかるんだよ?」
「……」
「教えてくれてもいいだろ? どうして毛むくじゃらの胸を見ただけでわかるのさ?」
「お前さ…山ン本の眼で見てご覧よ」
平二の動きが一瞬止まる。平二は、右眼に巻いた布を太秦坊から手渡されてから、まだ一度も外してはいない。
怖気づく平二の様子を察したのか、円狐が言葉を続けた。
「…良くお聞き。お前が怒ったり泣いたりすると、山ン本の眼が暴れる。それはもう分かってるだろう? 心を乱さないでいれば、眼はちゃんと見えるものを見せてくれる。うまくすれば、眼が持つ妖力だって、自分のものみたいに使えるんだ。――いいかい、怖がったりするのもいけないよ。酒を飲んで眠りこけそうになる時みたいに、何も考えない。わかったかい?」
「それも、太秦坊から伝えるように言われたのか?」
「忘れていた訳じゃないさ。その時が来たら教えてやれってさ。山ン本に言われたことは一言一句忘れるものかい」
ならば、先ほどの握り飯のことはどうなのだ、やっぱりこの女狐はわざと忘れていたのだ。
心の中で愚痴った平二は、心を落ち着かせるべく、深く息を吸っては吐くを繰り返す。そして頭に巻いた布を、ゆっくり上にずらして右眼を晒した。
そうっと右眼を開ける。すると赤色の世界が広がって、左眼とは違うものを映す。異人の腹に置いた円狐の手がだぶって見えている。白く細い指と、毛むくじゃらの短い指だ、
平二はゆっくりと円狐の手から視線を上へと移した。黄金色の毛を生やした狐が、品の良い紫の無地袖の着物に身を包んでいる。その姿は、自分を襲った芭尾に似ている。だが違うと確信できるほど、平二はその姿を落ち着いて見ることができた。特にその眼は、『人』の姿をしている時と全く変わらない。芭尾の冷たい殺気を放つ眼とは違う、涼やかで鋭いが、穏やかだ。
「そんなにあたしの姿が珍しいかい? 一度、見ているだろうに」
円狐を見つめていた平二は、声を掛けられると、慌てて視線を元の場所に戻した。
円狐は異人のみぞおちに手を置くと、それをぐいっと押し込んだ。すると、異人の口腔から太く黒い筋が束になって飛び出してくる。それを見た平二が思わず声を上げた。よく見ると、その黒い筋の一本一本が蠢いている。円狐がはだけた胸元も所々が上下し、口から飛び出したものは体の上でのたくっている。醜悪な光景に、喉の奥から吐き気が込み上げてくる。
平二はえずきながらも、それを見て気付いた。右眼で見た光景が赤色の世界なのにも関わらず、物の色が分かるのだ。先程も、円狐の毛が金色にみえたし、異人の体でのたうつそれが、黒いというのも分かる。
「どう、黒い大きな蚯蚓みたいのが見えてるかい?」
「これは…芭尾がやったことなのか?」
「これが巫蟲さ。こんないやらしい術を使うのは芭尾ぐらいのもんだ」
「……それで、こいつは死ぬのか?」
「この蟲が体の中に入ると、はらわたから何から全部喰われちまうんだ。――でもね、この異人はどういう訳か、はらわたを喰われてない、まだ間に合うかもしれないよ」
円狐は、異人の体の上を這っている黒い筋を指先で摘んだ。それは持ち上げられると、緩慢な動きでのたうち回る。円狐はそれを見て、「うえっ」と言って放り投げた。
「こいつらを、異人の体から追い出すんだ」
そう言って円狐は、袂から大きめの印籠を取り出した。それを開けて、中から黒い親指の先ほどもある丸薬をつまみ出す。
「それは?」
平二が訊くのにも構わず、円狐は異人の枕元にある盆を手繰り寄せた。その上には水と粥の入った碗が一つずつ載っている。粥のほうに先ほどの丸薬を放り込むと、木の匙でかき混ぜ始めた。硬そうな丸薬を匙で潰しながら粥と混ぜる。すると粥は、赤茶色のどろどろとした液体に変わっていく。
「…こいつはね、あたしが山で採った薬草を練って合わせたもんさ。こんなものでも妖力を込めれば、悪い蟲だって体の外に出してくれる」
匙を置いて、碗を両手で掬うようにして持った円狐は、平二に眼をやった。
「お前が訊いた『妖力』ってのを見せてあげるよ。山ン本の目でよく見てるんだよ」
円狐の手と、持っている碗の間からうっすらと青い光が漏れ始める。その光は徐々に碗を包んでいき、ついには丸い光の玉のようになった。右眼には光が見えているのに、左眼で見ると、円狐が碗を持ってじっとしているようにしか見えない。
円狐が光の玉に向かって、ふうっと息を吹きかけると、光が散って辺りに飛んだ。その神秘的な様子に、平二は見蕩れている。
すると、黙って見ている平二に向けて、円狐が碗を差し出した。
「この粥を異人に食べさせるんだ。そのぐらい、あんたも手伝いな」
円狐の息が心持ち荒い。平二に碗を渡すと、円狐はそのまま後ろの壁に寄りかかった。疲れた様子の円狐に碗を突き返すこともできず、平二は仕方なく、盆から匙を拾い上げる。
平二は半開きになった異人の口へ、匙で掬った粥を寄せた。異人は何も反応しない。異人の口を押えた平二は、のたうつ蟲の隙間に匙を突っ込む。しかし、飲み込むほどの気力もないのか、喉が動く気配もない。
「そうじゃない。まず、あんたが自分の口で食べやすいようにしてやるんだ。そしたら口移しで、異人の喉に押し込んでおやり」
「……おい、本気かよ」
「女房の仇を討つ覚悟はどこにいったんだい? 男に口移しするぐらい、どうってことないだろうに」
円狐は神妙な顔をして平二を見ている。
平二はなんとも言えない、苦々しい顔で円狐を見返した。気味の悪い蟲に触ることさえ嫌なのに、どうして口移しなどできるものか。しかも相手は異人で男だ。
しかし、人が嫌いという円狐が、この男に口移しなどするはずもない。やはり平二が、どうにかこの粥を異人に食べさせるしかない。
意を決した平二は、口に粥を放り込んだ。口内に米の甘いのと、なにやら苦いのやら酸っぱいのやら、いろいろ混ざった味が広がっていく。吐き出しそうになるのを抑えて、異人の口元に視線をやった。
すると今度は、円狐が大声を上げて笑い始めた
「あっはははっ――男同士でなんて、いくらなんでも見てらんないよ」
平二は、口の中のものを慌てて吐き出す。
「おまえがやれと言ったんだろうが。何を笑ってるんだ!」
平二が声を荒げると、右の眼が赤く光り始めた。
「わっ、ごめん、ははは、ごめんよ。いい方法を教えてやるから、怒っちゃだめだよ。あたしが悪かったからさ、ね」
笑いを堪えながら謝る円狐の姿に、平二の右眼も光を失っていく。
黙って睨む平二に、円狐が言葉を続けた。
「いいかい、その黒いやつをさ、退かしてやるんだ。さっき、あたいが手でつまみ上げたみたいに」
平二は、恐る恐る手を伸ばすが、指先が蟲に重なっても、まるで感触はない。
「そうじゃない、手で触るんじゃない、妖力で触るんだよ」
「そんな言ったって、どうやるんだ?」
「こう…なんて言ったらいいかね、力を入れるんじゃなくて、力を込めるっていう感じだね。力まないで、でも、力は入ってるっていうか」
「わからねえよ。お前がやってくれ」
「あたしはもう無理さ。暫く休ましておくれよ。――とにかく何度か試してごらん。上手くできたら褒めてやるから」
円狐は、眼の力に早く慣れさせるよう、太秦坊から言われている。平二は右眼の力が、どのようなものか全く分かっていない。芭尾に相対するまでに、その力を少しでも使えるようにさせておかねばならない。
壁に寄りかかって眺めているだけの円狐が動く様子はない。平二は諦めて、また手を伸ばす。右眼には、大の男十数人を一度に怯ませるほどの力があった。その気になれば、円狐でさえ敵わない程の力が備わっているのだという。それを上手く使えばいいだけのことだ。「力を入れずに力を込める」がよくわからないが、どのみち習い覚えるようなことでないのだろう。
平二は、暫く指先を開いたり閉じたりしているうちに、なにか不確かな感触があるのを覚えた。感触を意識すると、それはすぐに消えてしまう。そうしている内に、指先が弾力のある何かを掴む。しかし掴んだ拍子に意識して力を入れると、また感触が消える。それを何度も繰り返している内に、平二は巫蟲と呼ばれる黒い蚯蚓のようなものを、指先に引っ掛けた。それを意識せぬよう、素早く放り投げていく。放られた巫蟲は畳の上に落ちると、霧散したように消えてしまった。要領を掴んだ平二は、大小様々な巫蟲を次々と放り投げていく。
「ふふん、案外上手にできるようになったじゃないか」
「掴むのは無理だけどな」
異人の口から出ていた巫蟲は、おおよそなくなった。すると異人は咳き込んで、口に流し込まれた粥を吐き出した。呻きながら、平二の方に眼を向ける。
「今の内だ、食べさせてやんな。蟲を退いてやったから、精気が戻ってきたんだ」
平二は巫蟲を払う手を止めると、粥の碗を取り上げた。
異人は平二の姿を見て後退ろうとするが、体が上手く動かないのか、寝返りを打っただけになった。平二はそれを抱き起こすと、異人の顔を自分に向ける。
「おい、薬だ。俺の言うことが分かるか? く・す・り だよ」
平二がそう言うと、異人の尻込みする様子がなくなった。しかし匙を近づけても、口を開かない。
「口を開いてくれよ、これを食べなきゃ治らないぜ」
平二は、あーんと大きく口を開いて、異人に粥を食べるよう促す。すると、異人は少し口を開いて匙を受け入れた。粥を口にした異人は、碌に体も動かせないのに、粥の味には顔をしかめる。それを見た平二は、先程味わった、なんとも言えない不味さを思い出した。
「全部でなくてもいいけど、半分くらいは食べさせな。あと、腹から出てくる奴を忘れちゃだめだ」
円狐に言われて異人の口元に目を向けた平二は、また口の端に巫蟲を見付けた。それが這い出てくると、片手で引っ掛けて、口の中から引きずり出す。
円狐は平二の様子を見て。少なからず驚きを感じていた。妖力が何かを知らなかった『人』が、少しそれを見せただけで、もう使いこなしている。無論、太秦坊の眼があればこそではあるが。
『人』という生き物が状況に順応していく様は、都度驚かされる。だからこそ円狐は『人』が嫌いだ。どこでも生きられるくせに、なぜ山に分け入ってまで住処を作るのか。何を喰っても生きられるくせに、なんでわざわざ、他の生き物を殺して喰うのか。それを思う度に怒りがこみ上げてくる。『人』である平二に、心を許しそうになる自分が腹立たしい。
言われた通り、碗の半分を食べさせた平二は、異人に寝るよう言って、その場に胡座をかいた。
「とにかく半分はこいつの腹に押し込んだ。後はどうすれば…」
平二が言いかけたところで、円狐が低い声色で言う。
「もう、やることはないよ。あとはこいつ次第だ」
「どうした、具合でも悪いのか?」
先ほどまで大声で笑っていた円狐の様子が急に変わった。心配した平二が言う言葉にもそっぽを向いて、黙ったまま答えない。
平二は円狐の様子を見ようと、立ち上がって一歩前に出る。すると円狐が言った。
「近寄るな。『人』は嫌いだって言ったろう」
冷たい言葉を浴びせる円狐に、平二は黙って元の場所に座る。粥を腹に収めた異人は、今は落ち着いた息遣いで目を閉じている。眠ったのだろうか。
そっぽを向いたままの円狐は、障子紙を通して落ちる月明かりに照らされている。平二には、人と物怪の姿が重なって見えている。
いずれの円狐も、その眼は悲しげに見えた。
天狗の眼(上) 三、道連れ 1幕 2幕