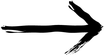天狗の眼(上) 三、道連れ 1幕 2幕
※
目が覚めた異人がまず初めにしたことは、厠へ行くことだった。夜明け前に目を覚ました異人は、飛び起きるなり、その場で待っていた平二と円狐に目もくれず、建物の外にある厠へと走って行った。
悪いものを全て出し切ってきたらしい異人は、戻ってくるなり平二に向かって言った。
「薬を有難う御座いまシタ」
言葉の調子はおかしいが、はっきりと分かる日本語を喋った事に、平二も円狐も驚いた。多少は意思の疎通に苦労するだろうと思っていただけに、これは予想外であった。
「おれは平二、こいつは円狐だ。あんた、名は?」
円狐は畳に座り込んでいる異人の方を向き直った。
「私はミケーレ・ラブティと言いマス」
「随分と言いにくい名前だな」
「日本では、皆さん私を『ミケーレさん』と呼びマス」
そこまで聞くと、円狐が声を上げた。
「名前なんてどうでもいいよ。なあ、お前に聞きたいことがある」
円狐はミケーレの目の前に正座する。
胡座をかいて座るミケーレの体は、異人の割に大きくはない。髪は黒く、短く切り揃えられている。髭で埋まっている彫の深い顔には、濃い緑色の瞳があった。面妖な顔つきの異人、ミケーレ・ラブティを前にして、幾分円狐は緊張している。言葉が通じるからとはいえ、相手は自分が知らぬ、海の向こうから来た『人』だ。
「お前、街道で女を拾ったね」
「女? おふうさんのコトデスカ?」
「おふうって名乗ったのかい。それで、その『おふう』ってのはどこに行った?」
その会話を聞いて、平二が眉間に皺を寄せる。女の名前がおゆうに似ている。偶然ではあるまい。
「…あなた方は一体誰デスカ? 長次郎サンに言われて来た医者ではないでショウ?」
「医者じゃ、お前の病は治らなかったさ。――あたしらのことは気にしないでおくれ。とにかく、そのおふうがどこに行ったのか、心当りはないのかい?」
「……」
「病を治してやったのはあたしたちだ。礼だと思って、あたしらの知りたいことを教えておくれよ」
「…おふうは、一体何者なのデスカ?」
「訊いているのはあたしじゃないか。お前は余計なことを知らなくてもいい。さあ、そのおふうっていう女がどこへ行ったのか、行き先を言っておくれ」
円狐の語気が強まると、ミケーレも黙ってしまった。その様子に円狐がため息をつくと、今度は平二が口を開いた。
「そのおふうってのは、俺の女房を殺した仇だ。だから追っている」
「……女房トハ?」
どうやら、言葉の意味がわからないらしい。
「連れ合いのことだよ。家族って言えば分かるか?」
「オゥ…そうデスカ」
少し考えこんだミケーレが話し始めた。
「あの、おふうという女性を助けてから、みんながおかしくなりまシタ。一緒にいたオールトサンや、長次郎サンも、急におふうを連れて行くと言い出したのデス。わたしのような外国人に厳しい役人たちも、誰も反対しませんでシタ」
それを聞いた円狐が口を開いた。
「それじゃ、そのオールトとか言うのが、おふうって女を連れてったのかい?」
「ええ、おふうを横浜まで連れて行くのだと言っていまシタ。私は倒れてしまったので、ここに置いていかれたのデス」
「横浜って? 一体それはどこなのさ」
「知りまセンカ? 日本の幕府が作った、外国人の滞在地デス。横浜居留地と呼ばれてマス」
「そうかい」
そう言うと円狐は立ち上がった。芭尾の行き先がわかれば、もう異人に用はない。襖を明けて部屋を出ようとする円狐を追って、平二も立ち上がった。
「ちょっと待って、待ってくだサイ。あなたたちは、横浜に行くのデスカ?」
「ああ」と平二が答えると、ミケーレが立ち上がった。
「なら、私も連れて行って下サイ。わたしも戻らなければ…」
平二は、そう言うミケーレの言葉を遮った。
「無理だ。異人を連れて旅するなんて、出来るはずないだろ」
今でさえ、物怪と一緒だというのに、この上、異人まで増えたらどうなることか。
「オールトサンは、横浜居留地におふうを連れて行きマシタ。そこへは、あなた方だけでは入れナイ」
「…どういうことだ?」
「横浜居留地は、幕府が外国人を閉じ込めておく場所デス。そこへ入れる日本人は、幕府の許しを得たものだけデス。もしおふうを追うのなら、どうやって居留地の中に入るのデスカ?」
「……」
「入れたとしても、あなたたちは居留地の中では目立ちマス。中は、その、私みたいな異人だらけデス。でも、私が一緒なら入れマス。私が雇った日本人だと言えば、誰も疑わナイ」
ミケーレは必死だ。一人では絶対に横浜へは戻れない。誰か道案内は必要なのだ。オールトや長次郎が心配だし、何よりこれ以上、異国の地で捨て置かれたまま、心細い思いはしたくない。
すると、先に行ったはずの円狐が戻ってきて言った。
「言っている意味はわからないが、とにかく一緒なら、その場所に入れるんだね?」
そう言って着物をミケーレに投げた。きっと宿の物を持ってきたのだろう。寒い時期なので、綿詰めの胴服もある。
「お前の着ている物は目立つからね、それに着替えるんだよ」
「おい、異人なんか連れて、どうするつもりだ⁉」
円狐は、平二の言葉に答えない。
「聞いているのか? 横浜に行くなら、箱根の関所を通らなきゃいけない。俺たちだけでも、通るのに苦労するはずだ。なのに異人までいたんじゃ、通れるはずがないだろ。それに道中だって……」
喚きたてる平二の言葉を遮って、円狐が言った。
「それは、『人』が作った道を行けば、の話だろう? もう芭尾の行き先がわかったんだ、別に街道沿いに歩く必要はないよ」
円狐が言うほど簡単なことではない。どの道を行こうが。人目を避けることは不可能だ。異人を連れて横浜に着くまで、山の中を歩くつもりなのだろうか?
「それに、この異人はお前よりも役に立ちそうだ。なにより芭尾の顔を見ている」
その言葉に平二は目を細めた。円狐が自分をここまで連れてきた理由は、芭尾の今の姿、おゆうの皮を被った姿を知っているからだ。
「そうかい。でもそれはこっちも一緒だぜ」
「どういうことだい?」
「もう臭いなんて追わなくてもいい。芭尾の行き先はわかった」
平二が言った言葉に、円狐も目を細める。お互いこの異人の存在によって、一緒に行動する理由がなくなった。それを口にしたことで、はっきりと認識したのだ。
「なら、一緒に行く理由もないねぇ」
円狐が低く冷たい声を発する。
関係は振り出しに戻った。元より『人』と『物怪』が一緒にいていい道理はない。
平二と円狐は、お互い睨み合ったままで黙って動かない。
ミケーレも二人の様子を察したのか、着替えを抱えて、その場で座り込んでいる。
その時、階下で扉の開く音が聞こえた。
明け方も近い頃だというのに、無造作に引き戸を開くがらがらと言う音が、静まり返った宿の中に響き渡った。睨み合っていた平二と円狐は、互いに視線を逸らすと、聞こえてくる音に集中する。足音が一つ、二つ…数が多い。およそ四、五人というところか。
階下で襖を勢い良く開く音が聞こえてくる。ばしんっという襖が開く音が、次々と響きわたる。平二たちが忍び込んだのが見つかったのか? それにしてはあまりに荒っぽい。まるで逃げろと言わんばかりに、大きな音を立てている。
円狐は、部屋に入って襖を閉じた。
「ミケーレとやら、ここから飛び降りるよ。着物は持ったかい?」
只事でない様子に、ミケーレも無言で頷くしかない。部屋の窓は宿場町の中心を通る道に面している。そこから飛び降りて闇に紛れるしかない。そこしか行き場がないのだ。
円狐は、部屋の障子窓を開けた。道に男が二人、突っ立ったまま円狐を見上げる。確かに円狐と視線が合ったのに、微動だにせず、声を上げようともしない。刺又を持って円狐の顔を眺めているだけだ。ミケーレも、円狐の肩越しにその男たちを見た。その濁った眼とぼうっとした様子には覚えがある。長次郎と同じだ。
「何をぼうっとしてんだ! 後がつかえてるんだ、早くしろ!」
平二が怒鳴る声に、円狐が振り向いた。
「様子がおかしい。役人みたいだけど、なんか変なんだよ」
そう言う円狐を押しのけて、平二も外を見る。眼下の男たちは平二を見ても、やはりぼうっと見上げているだけだ。
すると、幾人もが階段を上がってくる音が聞こえてきた。
平二は腰に差した刀の短い方を抜いた。相手は『人』だ、物怪の切れる刀でなくていい。それに、狭い場所は、小回りの利く短いほうが有利だ。
二階に上がってきた者たちが、次々と襖を開ける音が聞こえてくる。ついに、平二たちのいる部屋の襖が開け放たれた。そこには、刀や刺又を持った男が三人立っている。男たちは平二らと相対すると、そのまま動かなくなったしまった。じっとしたままで、何も言わずに立っている。
「なんだ、こいつらは?」
平二が言った。男らの中には、両頬に血をこびり付かせたものもいる。眼孔に眼玉がなく、真っ黒い空洞が二つ空いていた。他にもはだけた胸元から、桃色の肉と白い骨をはみ出させている者もいる。
「きっと…この異人が目を覚ますと、こいつらが来るように仕掛けてたんだ。――芭尾の仕業だよ」
眼玉がない者、腹を割かれた者、いずれも芭尾に喰われたのだろう。その喰い残しが、平二たちを追いつめる。これも外法が為せる業か。
ミケーレはその光景に恐怖しながらも、必死で祈りの言葉を唱えた。円狐が竦んで動けなくなったミケーレの腕を引き上げて、無理やり立たせる。
「とにかく、ここから飛び降りるんだよ。早く!」
立ちあがったミケーレの腋に円狐が手を通すと、そのまま一緒に窓から飛び降りた。ミケーレは結構な高さにも関わらず、降りた時の衝撃をほとんど感じなかった。まるで綿毛のようにふわりと浮かんで、音もなく降りたのだ。
それに続いて平二も降りてきた。すぐに立ち上がった平二は、立っていた男二人に刀を向ける。
「異人、離れてろ!」
男らが平二に刺又を振り上げる。本来、刺又は、その二股にわかれた形状で相手を押さえつける道具だ。それを振り上げてくるというのは、端から捕らえるつもりがないのだろう。平二は刀で刺又を受けるも、その勢いで後ろへ押される。男二人が狂ったように刺又を振り上げては打ち下ろしてくる。平二は受けるのが精一杯で、近づくこともできない。
すると男たちが後ろへ下がった。二人の男の足は宙を掻いている。その後ろに立つ大きな影、一目だ。後ろから持ち上げられた男たちは、まだ刺又を振っている。それを一目が軽々と放り投げた。
「一目、この異人さんを抱えておやり」
円狐に言われた一目は、病み上がりで足元のおぼつかないミケーレを、掬い上げるように抱える。ミケーレも一目の大きさには驚いたのか、見た瞬間に「オウッ」と声を上げた。それでも状況は察しているのか、抵抗もせずにじっと抱えられている。
そこへ脇本陣の二階にいた男たちが、次々と飛び降りてきた。平二がそちらに向けて刀を構え直すと、円狐がその横に並んだ。いつの間にか、手にはあの白い霊刀・黙儒を持っている。平二と円狐はミケーレを抱えた一目を背にして、男たちと相対する。
「こいつら、一体、何なんだ?」
「…さあ、あたしにもさっぱり」
「とぼけるなよ、わかってるんだろ? 言えよ」
「嫌だね、知りたけりゃ、自分の眼で見てご覧よ」
先程ミケーレの回復を待つ間、右眼を布で隠していた。それを円狐は言っている。
平二は右眼を覆う布を引き上げて男たちを見た。
近づいてくる男らの顔には、先程ミケーレの腹から湧きだしていたものと同じ、黒い大きな巫蟲がまとわり付いている。よく見るとそれは、鼻や耳の穴から出入りを繰り返し、時折漏れ出たものが地面に落ちて、霧散するように消えていく。もう既に男たちの体の中は、巫蟲でいっぱいになってしまったのであろう。その醜悪な光景に、平二は吐き気を覚えた。
怯んだ平二へ向かって、刀を持った男が切りかかる。それを避けて後退した平二は、足を滑らして転げた。それを追う男の前へ円狐が出る。円狐の振るった黙儒が、飛び出してきた男の頭を叩くと、周りを照らすほどの青い火花が散った。男はその場で崩れ落ちて、全く動かなくなる。
「すげえな、それ」
平二が思わず感嘆の声を漏らす。
「ぼさっとしないで、早く立ちな」
他の男たちもゆっくりと、だが確実に間合いを詰めてきている。円狐は、ばちばちと火花を散らす黙儒を、狭まる輪にむけて振る。それに怯んだのか、男たちの動きが止まった。それを見た平二は、持っていた短い刀を鞘に収めると、太秦坊にもらった太刀に手を掛けた。相手は芭尾に何かをされた者たちなのだ。普通の刀より、物怪を切れる得物のほうがいいに違いない。
太刀の柄を握って一気に引きぬいた平二は、思わず「うわっ」と悲鳴を上げた。
右眼で見た太刀は、どす黒い血に濡れている。錆びついていた刀身から、血のごとく赤い煙のようなものが立ち上っている。掴んでいる柄まで血濡れていて、平二の手までその色に汚れているのだ。
「びびってるんじゃないよ! さっさと手伝いな」
円狐が語気を強めて言った。平二は気を取り直して太刀を構える。
正眼に構えると、立ち上る血の煙が視界を遮った。その煙の向こうから、先程一目に投げ飛ばされた男が、また刺又を振りかぶって迫って来る。平二は太刀を横に振って後ろへ引くと、一気に前に突き出した。刀は男の胸に深々と突き刺さる
「すまん、恨むなよ」
平二がそう言って太刀を引き抜くと、刺した傷から血とともに、黒い巫蟲が何匹も飛び出してきた。平二は飛んできたそれを必死に手で払う。男が前のめりに倒れると、地面に血溜まりが広がっていく。
円狐はその間に、三人の男を地面に転がしていた。残るは一人。平二は刀を構える男に向かって一気に走り寄ると、上段から斜めに切りつけた。男が突き出した刀に当たって、平二の太刀が跳ね返る。勢い余って後ろへよろけた平二は、くるりと回って、そのまま横一文字に切り払った。うまく男の腹の下あたりを捉えた刃が、鮮血を飛び散らせる。それでも怯まず切り掛かってくる男の刀が、平二の肩の辺りを浅く切りつけた。しかし平二は動きを止めない。切りつけられた肩から、男に向かってぶつかっていく。突進されて仰向けに倒れた男の腹に、平二は思い切り太刀を突き下ろした。肉に刃がめり込んでいく感触が、手に伝わってくる。
男の手が、突き刺された太刀を握りしめた。巫蟲が顔から落ちていくと、男の表情が見えた。男は何が起こったのかわからないという顔で、自分の腹に刺さった太刀を見ている。
その視線が、平二を見た。
思わず、平二は顔を背ける。
視線は徐々に虚ろになって、頭をゆっくり後ろへ反らしていくと、男はそのまま絶命した。
「平二、もういい。行くよ」
呆然と立ち尽くす平二は、円狐の声で我に返った。振り向いた平二の眼に、円狐たちが宿場の門戸の方へ向かっているのが見えた。もうすぐ日が昇る。長居は無用だ。
刺さった太刀を引き抜くと、平二は拭かずにそのまま鞘に収める。血の煙も、鞘に納めてしまうと消えてしまった。太刀から離した手も、もう元通りになっている。
額に押し上げた布を元に戻すと、平二は円狐たちの後を追った。
天狗の眼(上) 三、道連れ 1幕 2幕