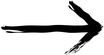※
フローニゲン号の甲板から横浜の港を見ていた芭尾は、炎とは違う、赤い光を認めていた。それは見覚えのある光だ。封印から逃げ出した夜に見た、自分を追ってきた太秦坊の眼の光だ。
芭尾はその光を認めた瞬間、背筋が凍る思いがした。如何に『人』を食べて妖力が強くなろうとも、太秦坊には敵う気がしない。
相手は千年生きている天狗だ。天狗は元々が強い物怪だ。千年も生きれば、『人』から拝まれるほどの存在にもなる。現に太秦坊は山神となって、海千山千の物怪たちを束ねているのだ。
芭尾にとって唯一の救いは、太秦坊が山から出られないことだった。山神である太秦坊がいなくなれば、山にいる物怪たちを縛るものがなくなる。だから太秦坊は山を出ない、追ってはこないと侮っていた。
だが、暗闇に浮かぶその光は、あの忌々しい太秦坊の眼の光だ。光の数は一つ。そしてそれは、漆黒の海の上を滑る様に近づいてくる。いったい何が起こっているのか、芭尾は酷く混乱した。
とにかく、近づいてくるものに応じるほかあるまい。海上へ逃げたことで安心しきっていた。もう逃げ切ったと確信していた。用意がないではないが、あの赤い光が太秦坊の眼なら、全く十分でない。むしろ海に逃げたことで、逃げ場を失ってしまった。
芭尾は、寄り添うようにして立っているオールトの手から逃れると、関兵衛を呼んだ。離れた芭尾を引き寄せようとするオールトを蹴り飛ばすと、関兵衛にありったけの『人』を甲板に集めるよう命令する。
ほとんどの船員や軍人は、フローニゲン号をけん引する蒸気船のエンホーン号に乗っている。帆船であるフローニゲンには、芭尾たちの他には十数人の船員と貨物しかない。船員たちだけでも使えるようにしておきたい。全員に小銃を持たせて迎え撃つ。
隠しきれない不安感を紛らわすように、蹴られて転んだオールトを足蹴にする。そうしている間にも、赤い光は真っ暗な海の向こうから近づいて来ている。
呻くオールトをよそに、芭尾は船縁から身を乗り出すようにして、光の方を見た。
すると突然、その光は宙を飛んだ。空高く上った光が、真っ直ぐ芭尾の頭上へ飛んでくる。
芭尾は、その時初めて赤く光る眼の主を見た。太秦坊ではない。褌姿の若い男、封印を解かれてすぐに襲った夫婦の片割れだ。確か腹を裂いて、目玉を一つ抉り取った。とうの昔に死んでいるはずの男が、なぜ空から降ってくるのか。
混乱した芭尾は、驚きと恐怖の混じった叫びを上げた。真上から落ちてくる男の手に持った物が、青白い火花を散らしたからだ。それも見覚えがある。殺した妖狐の持っていた白い剣。狐の死骸とともに燃えたはずだ。
放り投げられた平二もまた、フローニゲン号の甲板に、おゆうの姿を借りた芭尾を認めた。平二は握りしめた黙儒に精一杯の力を込める。すると黙儒が青白い火花を散らし始めた。芭尾と眼の合った平二が、腹の底から精一杯の咆哮を上げる。
飛んできた勢いでフローニゲン号の太い帆柱に切迫した平二は、黙儒を柱に叩き付けた。その一撃が柱の真中を吹き飛ばす。そのまま真下落ちていった平二は、どんっと大きな音を立てて、帆柱の根元へ降り立った。
黙儒で横殴りにされた帆柱が、めりめり音を立てて折れていく。芭尾はその威力に戦慄した。芭尾の手を吹き飛ばした時とはまるで別物だ。まるで雷が帆柱に突き刺さったかのようであった。
降り立った平二は芭尾を見据えると、片手で黙儒を構える。もう一方の手で太刀を一振りすると、鞘が甲板に転がった。鞘から姿を現した半身の刀身は、赤い血の煙を立ち上らせている。
芭尾は改めて平二の姿を見た。褌姿で体中が血で汚れている。確かに殺したはずの男だ。間違いない。裂いたはずの腹には傷跡がある。そして赤く光る右の眼は、芭尾が抉ったはずの方の眼だ。
「…貴様、何者だ?」
芭尾が訊いた。
「知っているだろ」
「なんで、貴様の右眼に、太秦坊の眼が入っている?」
「もらった。お前を殺すために」
芭尾は歯ぎしりをした。太秦坊が差し向けた追手の本命は、この男だったのだ。『人』であるにも関わらず、ありえないほどの妖力を剣から放っている。天狗の眼のお蔭であろうが、それは太秦坊の力にも劣らない。物怪である狐や大男に気を取られていて、この男に気が付かなかった。
うろたえる芭尾に向けて、平二が黙儒を振り上げる。力を込められた黙儒の刀身は、火花が重なり合って、青白い光に包まれている。
迫ってきた平二を、芭尾は後ろへ飛んで避けた。するとそれまでいた場所に、青い火柱が立った。平二の振るった黙儒が、勢い余って甲板を叩いたのだ。叩かれた場所には、船底が見えるほどの大きな穴が開いた。その穴を挟んで、平二と芭尾が向かい合う
焦った芭尾が尾を繰り出した。広がったスカートの中から、目にもとまらぬ速さで尾が飛び出す。
堅い毛の束が捻じれて尖ると、平二に向かって真っ直ぐ伸びた。ぎりぎりまで尾を引きつけた平二が黙儒で横一閃に払う。鋭く尖った尾が吹き飛ばされて、壊れた筆のように先端が裂ける。
芭尾は、狼狽えながら尾を引き戻す。怯んだ芭尾に、すかさず平二が襲いかかった。戻る尾に隠れるようして芭尾に迫っていく。死角から飛び出してきた平二に応じきれない芭尾は、思わず両腕を上げた。しかし、黙儒は上からは来ない。斜め下から振り上げられた黙儒が、芭尾の脇腹を浅く抉った。
黙儒が触れた瞬間、青い閃光がほとばしる。芭尾が着ている外套に穴が開いて、中から大量の巫蟲が流れ落ちた。そのまま黙儒を振り抜いた平二は、芭尾のみぞおちを渾身の力で蹴り飛ばす。
平二は、周りの動きが遅くなるような、不思議な感覚を味わっていた。長次郎と刀を交えた時もそうだった。右眼で見る世界は赤いだけでなく、全てのものがゆっくりと動く。元より平二には、武術の経験などはない。向かってきた芭尾の尾を見極めることができたのも、この太秦坊のくれた右眼のおかげだ。
芭尾は、着ていた外套の合わせを持つと、平二に向けて開いた。黙儒に吹き飛ばされたものの、巫蟲はまだ残っている。外套の下にうごめく黒い蟲が、一斉に平二めがけて飛びかかった。
襲いかかる巫蟲に向けて、平二は折れた太刀を投げた。唸りを上げて回転する太刀は、血煙を撒き散らしながら巫蟲を蹴散らすと、まっすぐに芭尾の胸元へ飛び込んでいく。すんでのところで避けた芭尾の右肩を太刀が掠めた。
体制を崩してその場に膝をついた芭尾は、呻き声を上げて肩を抑えた。掠めたにしては、ありえないほど深く斬られている。しかも斬られた傷から流れる血と共に、妖力まで漏れ出していく。ただの刀でないのは一目見てわかったが、これほどの威力を持っているとは。
あまりにも芭尾に分が悪い。太秦坊の眼の力を存分に発揮する平二は、自身の感情と相まって、凄まじい妖力で向かってくる。
「ま、待て。もう、人は殺さない。人は喰わない。だから、頼むから見逃してくれ」
芭尾は膝をついて懇願した。飛びかかろうと黙儒を振り上げていた平二は、その場で足を止める。
「五百年も封印されていた。腹が減っていた。仕方なかったんだ。頼むから命だけは…」
平二は黙って聞いている。芭尾は思いつく限りの言葉を並べた。この場だけ取り繕えばいい。相手は所詮『人』だ。目線さえ合えば、この男も術中に嵌まる。
顔を上げた芭尾は、平二と視線を合わせる。芭尾の眼の奥に、うっすらと青い炎が燃える。
「お前、俺に術を使ってるのか?」
平二の言葉で、芭尾の眼の光が失せた。その表情に、みるみる焦りの色が浮かんでいく。
「効かないぜ、円狐には騙されたが、お前じゃ無理だ」
あっさりと術を跳ね返されて、芭尾は絶句する。太秦坊の眼が術を打ち消したのか。
「お前、腹が減っていたと言ったか?」
平二は静かに言った。
「ああ、そうだ。貴様も腹が減れば喰うだろうに」
「そうか」
黙儒の放つ火花が一気に激しくなった。芭尾に飛びかかった平二が黙儒を打ち下ろす。転げて避けた芭尾に、飛び散った木片が突き刺さった。芭尾がいた所には穴が開いている。その穴の中心には、平二が振るった黙儒が突き刺さっていた。
「物怪は、腹が減らないんじゃないのか?」
平二の声色は相変わらず落ち着いているものの、黙儒の火花は激しさが衰えない。
「人を喰わなくても生きられるくせに。なんで俺たちだった? なんでおゆうを喰った?」
一歩一歩近づく平二に、芭尾は後ずさりながら答えた。
「うまいから喰う、それだけだ。貴様らだってそうだ。『人』だって、米や野菜だけでも生きられるだろうに。なんでわざわざ、他の生き物を殺して喰う?」
近づいてくる平二を、芭尾は鋭い目つきで睨みつけた。
「私が『人』を喰うのと何が違う? 『人』が獣を喰う、私が『人』を喰う、何かおかしなことがあるか?」
「……」
平二は歩みを止めた。黙儒を振るえば届く距離だ。しかし、黙って芭尾を見下ろしている。
「貴様らは、獣の皮を剥いでそれを着る。私も同じことをした。それでなぜ許されない? 『人』が許されることを私がして、一体何が悪い?」
「…お前は、おゆうを殺した。俺が許さない。それだけだ」
「だったら、お前はどうなんだ? 許されるのか? 私を殺して許されるのか?」
「俺には、よく分からねえ。――でもな、地獄行きは覚悟の上だ」
芭尾は愕然として平二を見上げた。理屈でどうこうできる相手でないことを悟った。どんな言葉でも、この男の心は揺れない。ただ、女房の仇を討つことだけしか頭にないのだ。
いよいよ観念した様子の芭尾に、平二が黙儒を振り上げた、芭尾が後ずさろうとすると、背中が壁に当たる。下がり続けた芭尾は、ついに船縁まで行き着いたのだ。大きく一歩前に出た平二は、黙儒を芭尾の頭頂部に真っ直ぐ打ち下ろした。
しかし、黙儒が芭尾の頭を割る寸前、平二が腕を止めた。黙儒は芭尾の目の前で止まったまま、火花を散らしている。
平二は悲痛な表情を浮かべた。黙儒が当たる瞬間、おゆうの顔を見たのだ。諦めで毒気が抜けたその顔は、優しく平二を気遣う、見慣れたおゆうの顔だった。
「……おゆう」
平二は、抑えていた感情が一気に膨れ上がってくるのを感じた。体中がどんどん熱くなり、肌の色が赤くなっていく。悲しみの量が増えた分だけ、自分の意識が押し込められて、何か別のものに支配されていく。
訳がわからない芭尾は、落とされかけた剣の下から這い出ると、平二から離れて立ち上がった。
その時、平二の背後で扉が開いた。船倉へ行っていた関兵衛が、船員たちを連れて戻ったのだ。芭尾はすぐさま船員たちに眼を向けた。次々と芭尾と眼を合わせた者から、その場で足を止めていく。
平二が雄叫びを上げた。肌は赤銅色になっていく。右眼の光は辺りが煌々と照らす。
「うおおぉぉぉぉぉっ!」
平二は芭尾に飛びかかった。だが既に立ち上がっていた芭尾には届かない。右眼の力を抑えきれなくなった平二は、完全に自分を見失った。
「関兵衛、やれ!」
芭尾が言うと、関兵衛がオランダ語で他の者たちに指示を出す。すると全員が手にした小銃を構えた。芭尾に襲い掛かろうとする平二に向けて引き金を引く。平二を捕えきれず、次々と銃弾が甲板にめり込んでいくものの、その内の一発が平二の太ももに命中した。動きの鈍った平二に、次々と銃弾が撃ち込まれていく。弾が皮膚を裂くたびに、平二が呻き声を上げた。
勢い余って船縁に激突した平二は、その場で倒れてしまった。
体中から血を流して倒れている平二に、芭尾が歩み寄る。うつ伏せになった平二の体を、足で押し上げて仰向けにすると、荒く呼吸する平二を見下ろした。いつの間にか皮膚の色は元に戻り、右眼はもう光を失っている。
ぼんやり開いた平二の両眼には、自分を見下ろしているおゆうが見えている。左眼には暗がりにぼんやりと浮かぶおゆうが。そして右眼には、赤く染まった世界に、青く目を光らせるおゆうがいた。
それは芭尾だ。おゆうの顔を盗んだ芭尾なのはわかっている。それでも、おゆうの顔を吹き飛ばすのをためらってしまった。もう二度と会えないはずだったおゆうが目の前にいる。生きてきて、初めて愛おしいと思った女性だ。例え奪われたものとはいえ、その姿へ剣を振り下ろすことに、間際でためらいが生じた。
一度感情のたがが外れると、溢れ出す右眼の力を抑えられなかった。折角少しは使えるようになったかと思った矢先であったのに。円狐がいればなんと言うだろう。また馬鹿にされるに違いない。おゆうの仇もとれない、円狐の無念も晴らせない、俺もとうとう芭尾に殺されるか。
平二の両目に映った芭尾が、ゆっくりと首に手を伸ばしてくる。
「平二サン!」
その時、ミケーレの叫ぶ声が聞こえた。一目に甲板へ押し上げられたミケーレは、銀の大きな十字架を胸前に掲げている。
「芭尾、あなたに平二サンまで殺させまセン! 神とイエス・キリストにひれ伏しなサイ!」
ミケーレの声で、平二以外の全員が振り向いた。目の前には、倒れた平二に手をかけようとする芭尾と、それを囲むように小銃を持った船員たちがいる。
芭尾はともかく、船員たちまでが、眼の奥に薄ぼんやりとした青い光を湛えている。
平二に伸ばしかけた手を戻した芭尾は、ミケーレに言った。
「貴様は、なんで生きている…?」
腹を貫かれたはずのミケーレが目の前にいることに、芭尾は少なからず動揺した。『人』は簡単に死ぬはずだ。物怪とは違って、『人』は少し肉体が傷ついただけで死んでしまう。これまではそう思っていた。
なのに、平二といい、このミケーレといい、とっくに死んでいるはずなのに、なぜこうも追い縋ってくるか。芭尾は、初めて『人』に対して感じた気味悪さに、苛立ちを覚えた。
「円弧サンが…、あなたを倒すために、円弧サンが助けてくれたのデス」
そう言ってミケーレは、十字架を手に一歩踏み出した。それを見て芭尾が目くばせすると、関兵衛が銃口をミケーレに向ける。ほかの船員たちもそれにならった。
ミケーレは、小銃を構えている関兵衛に言った。
「関兵衛サン、私がわかるデショウ? いや、私がわからなくても、この十字架はわかるはずデス。あなたが、そんなものをイエスに向けてはいけナイ」
ミケーレは穏やかな口調で言うと、続けて船員たちに片言のオランダ語で話しかける。すると船員のたちは、次々と銃を下げていく。
オールトと同じく。芭尾の瞳術は異人を幻惑するものの、その意思まで縛り切れない。言葉がわからないせいだ。おかげで術にかけても、少しのきっかけですぐに正気に戻ってしまう。
いつの間にか船員ら全員が、ぼうっと立っているだけになった。少しずつ正気を取り戻している。銃を構えているのは関兵衛だけだ。
「関兵衛、撃て!」
芭尾が叫んだ。しかし、関兵衛の持った銃から弾は出ない。その指は激しく痙攣し、引き金を引くことに抗っている。
「デュボワを殺したことを忘れたか、同じだ、そいつも殺せ!」
「関兵衛サンが殺したんジャナイ! 芭尾が殺したんデス」
関兵衛の銃を持つ腕まで痙攣を始めた。それを見た芭尾が、苦々しい表情を浮かべる。
「ミケーレ・ラブティ、やっぱり貴様は違う。一体デュボワと何が違う!」
銃を持つ手を下げ始めた関兵衛のこめかみを、黒い一閃が貫いた。芭尾の手から伸びた鋭い爪が、関兵衛を刺し貫いたのだ。
関兵衛が持った銃が甲板に向けて火を吹くと、その勢いで体が仰向けに倒れた。
「関兵衛サン!」
ミケーレが悲痛な叫び声を上げた。
爪が関兵衛のこめかみから抜けると、血飛沫とともに脳漿が甲板に飛び散った。
芭尾は血の滴る指先を、今度はミケーレに向けた。指差すように人差指を構えた芭尾は、ミケーレと眼が合うとにやりと笑う。
その刹那、船の甲板が傾いた。呆けたように立っていた船員たちは、皆転んで傾いた方へ落ちていく。立っていられないミケーレと芭尾は、その場に膝をついた。
船縁に手をかけた一目が、甲板によじ登ってくる。ミケーレの声を聞いて船を揺すったのだ。
甲板に足が掛かると、一目は一気に駆けて、芭尾の前に躍り出る。
一目が振り上げた拳と腕に、次々と芭尾の爪が突き刺さっていく。爪が腕を突き抜けていくのにも構わず、一目は一気に拳を振りぬいた。その大きな拳は風圧をまとって、芭尾の顔面へと迫る。
しかし拳は芭尾に届かず、その肘から先が甲板に音を立てて落ちた。芭尾の爪で切り落とされたのだ。しかも親指の爪は、一目の胸のあたりを貫いている。
それでも一目は怯むことなく、残った左手で、伸びきった芭尾の爪を束ねると、それをむしり取るように手を捻った。芭尾の体はその拍子に転がって、爪も粉々に砕けて折れる。
そこで力尽きたのか、一目が膝を着いた。爪を折られた芭尾は、歯噛みしながらも、すぐさま立ち上がった。
芭尾の形相は痛みと恐れ、そして怒りで醜く歪んでいる。その背後から、蛇が鎌首を上げるかの如く、尾が持ち上がった。その先端は黙儒で打たれたままに、ばらばらに割れている。怒りが頂点に達した芭尾は、後先構わずありったけの妖力を尾に込める。すると、先端がなくなっていた尾が、見る見るうちに元の姿を取り戻していく。
尾は元通りの太く大きな芭蕉の葉になった。それが、きりきりと捻じれて尖っていく。
「死ねぇ!」
芭尾が尾を突き下ろすより早く、ミケーレは駆け出していた。 あの尾で円弧も殺された。このままでは一目も殺される。そう思った時には、すでに平二から渡された小刀を握っていた。
しかし、ミケーレが眼の前まで迫っても、芭尾はその場に立ち尽くした。いつの間にか這い寄った平二が、芭尾の両足首を握っている。
ミケーレが手に持った刀から、血煙が上がるのが見える。平二が振るっていた太刀と同じだ。あれは避けないとまずい。
芭尾は咄嗟に右手を伸ばした。しかしそれは、円狐に吹き飛ばされた方の手だ。手首までしかない腕はミケーレを掠める。伸ばした腕に先がない事に気付いた芭尾は、湧き上る焦りと困惑を押さえきれず、悲鳴を上げた。
ミケーレが持った小刀が、ずぶりと芭尾の胸元に潜り込んだ。芭尾の眼に、ゆっくりと自分に突き刺さっていく小刀が見える。だが刺された痛みは、電撃のごとく体中を駆け巡った。
必死で逃げようとするものの、足首に食い込んだ平二の指が離さない。喉が枯れんばかりに声を上げる芭尾は、尾をミケーレに向けて振り下ろそうとするが、これもまた動かなかった。
いつの間にか後ろへ回った一目が、残った腕で芭尾の尾を抱えている。一目の腕がめり込んだ尾は、奇妙な形に折れ曲がっていた。
芭尾は爪の折られた左手で、自分に刃を突き刺したミケーレの首を掴んだ。喉を潰さんばかりの力で指を食い込ませる。
「き、貴様らぁ! 離せっ! 離せっ! 離せっ!」
叫ぶ芭尾に応える者はいない。平二も一目も、手を放そうとはしない。ミケーレも喉を絞められながらも、更に力を込めて刀を押し込んでいく。
芭尾が一際高い声で吠える。胸に突き刺さった小刀から、体中に激痛がほとばしる。しかも小刀が刺さった傷から、妖力まで漏れ出していく。
しぼむように体の力が抜けていく芭尾は焦った。手のない右腕でミケーレを殴りつける。露出した手首の骨が、ミケーレの頬の肉を抉る。
芭尾と激しくもみ合うミケーレは、握りしめていた十字架を芭尾に向けた。絞められた喉からは、祈りの言葉どころか、息を吐き出すことさえできない。それでもミケーレは、十字架を芭尾の目の前に突き付けた。効くか効かないかではない、もうこれしかできることがないのだ。
芭尾の眼前にイエス・キリストの姿が迫った。まるでミケーレを守るかの様に、両腕を大きく広げて立ちはだかる。 それは、芭尾にとって何ら価値のない、けっして恐れをなすようなものでないはずだ。それにも拘わらず、処刑される無残な男は、威圧感をもって迫って来る。
十字架が芭尾に触れた。朦朧としたミケーレの腕が下がったのだ。額に押し付けられた十字架が、のし掛かるように重くなっていく。十字架は芭尾の体を押しつぶさんばかりに、その重みをどんどん増していく。刺さった刀の痛みと十字架の重みで、ミケーレを殴っていた腕が下がる。
デュボワを殺した時に試したはずだ。死を前にデュボワが振り回していた十字架でさえ、触れば少々痛い程度、決して抗えない程のものではなかった。
しかし今、押し付けられた十字架は、まるで大岩のごとく自分の体に圧し掛かってくる。体がぴくりとも動かせぬ。一体デュボワとミケーレの何が違うというのだ。
「なぜだ…なぜ…」
その理解しがたい現象に、芭尾は為すすべもなく膝を着いた。
芭尾は、いつの間にか足首を握っていた手が離れていることに気が付いた。枷を失っても、十字架に押さえつけられた体は動かない。
「あとは…、俺がやる」
立ち上がった平二は、虚ろに芭尾を睨み付ける。大量の銃弾を受けた体は、あちこちから血を流し、両足はがくがくと震えている。だが、その右眼は光を取り戻し、構えた黙儒は再び青白い火花を飛び散らしている。
いよいよ黙儒を持った平二が踏み出した時、鋭い銃声が響き渡った。音がした先には、小銃を構えたヨハン・オールトが立っている。銃弾は、平二の脇腹にめり込んだ。
しかし、渾身の力を込めた黙儒は止まらない。芭尾は避けることもできず、その一撃を右肩に食らう。肩の肉を吹き飛ばされた芭尾は、甲板の上に転がった。
「くそっ…くぅ…」
転げた芭尾は、這いずるように平二から逃げる。
再び芭尾にとどめを刺そうと、追い縋る様に平二が飛び掛かった。
「地獄へ落ちろ、芭尾!」
うつ伏せになった芭尾の背中に、平二が黙儒を突き立てようと振り上げた時、再びオールトの持つ小銃が火を吹いた。
放たれた銃弾は、平二の側頭部を撃ち抜いた。
頭が大きく横へ振られ、穿った傷から血が飛び散る。手に持った黙儒を落とした平二は、棒切れのようにその場に崩れ落ちた。